昨日、京都の祇園祭の映像をテレビで見かけました。去年はナマで見て、この三連休はスクーリングに行っていたんだっけ、と思い出しました。去年はスクーリング・卒論の遺跡調査などで休日もかなりアクティブでした。
今年は、学芸員のレポートのために、博物館にいくつか行かなければいけません。私立の小さめの博物館で、おすすめのがありましたら教えてください。
三連休の最終日くらいは、午前中の時間を生かして、記事を一つアップしようと書き始めたところです。
神話伝承論スクーリングの続きです。
二日目の午後は学外授業で、バスに乗って平城宮跡に行きました。

平城宮の東院の復元を行っている現場を軽く見学しました。普段は開けていない扉を開けていただいて、入って行きました。

先生は、東院の復元事業に関わっているそうで、建物の上に金色に輝く鳳凰は、先生の意見が反映された結果だとか(笑)。考古学、歴史学、国文学などの各先生の議論の結果らしいですが。平城京の時代にこんなものがあったかどうか、いろいろ意見があったらしいですが、最終的にそうなってしまったようです。

池の石の置き方なども、当時そのままで復元しているのだとか。
付近は、梅の香りが漂っていました。奈良・平城京には梅が似合います。奈良時代は、「花」といえば梅、平安時代になると、桜になったようですから。
お天気はよくなかったのですが、梅の季節に平城京跡を訪れることができたのは、よい思い出です。

その後、朱雀門に移動して、この講座のハイライトともいえるでしょうか、朱雀門に立って、平城遷都の詔を読み上げました。
朱雀門から南に向かって立ち、先生の後について、元明天皇になったつもりで、みんなで読み上げます。

この写真は、朱雀門に向かってぞろぞろ歩いている図です。
読み上げるのは、この門の上に立って南を向いて行います。
「まさにいまへいじょうのち、しきんとにかない、さんざんしずめをなす。きぜいならびにしたごう、よろしくとゆうをたつべし。よろしくとゆうをたつべし。」(『続日本紀』和銅元(708)年2月15日条)
「しきん」は四禽で、青龍、白虎、朱雀、玄武です。「さんざん」は三山で、藤原宮では耳成山、香具山、畝傍山ですが、平城宮ではそれが、平城山、御蓋山(春日山)、生駒山になるのだそうです。
先生は、これを暗誦しながら、最後は怪しい教祖のように、両手を挙げて「よろしくとゆうをたつべし。」とやりました。
この朱雀門での怪しい集団の行為が名物になって、取材も入ったこともあるとか?
まあ、まさにその現地に立ち、声に出して読むというのはすてきなことです。思い出に残ります。奈良ではそういう行為が似合う場所がたくさんありそうですね。
そこで解散となりました。大極殿は閉まっていて、そっちの方は皆さん行ったこともあるのか、私もありますが、そのまま帰る人あり、私は、平城宮跡資料館に行ったことがなかったので、行ってみました。本当は、歩いて、海龍王寺の方まで行ってみたかったのですが、雨が強くなってきたので、断念しました。

資料館のミュージアムショップで、考古学の発掘スコップ型のスプーンを購入しました。
さらに次回に続けます。
☆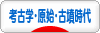 にほんブログ村
にほんブログ村
今年は、学芸員のレポートのために、博物館にいくつか行かなければいけません。私立の小さめの博物館で、おすすめのがありましたら教えてください。
三連休の最終日くらいは、午前中の時間を生かして、記事を一つアップしようと書き始めたところです。
神話伝承論スクーリングの続きです。
二日目の午後は学外授業で、バスに乗って平城宮跡に行きました。

平城宮の東院の復元を行っている現場を軽く見学しました。普段は開けていない扉を開けていただいて、入って行きました。

先生は、東院の復元事業に関わっているそうで、建物の上に金色に輝く鳳凰は、先生の意見が反映された結果だとか(笑)。考古学、歴史学、国文学などの各先生の議論の結果らしいですが。平城京の時代にこんなものがあったかどうか、いろいろ意見があったらしいですが、最終的にそうなってしまったようです。

池の石の置き方なども、当時そのままで復元しているのだとか。
付近は、梅の香りが漂っていました。奈良・平城京には梅が似合います。奈良時代は、「花」といえば梅、平安時代になると、桜になったようですから。
お天気はよくなかったのですが、梅の季節に平城京跡を訪れることができたのは、よい思い出です。

その後、朱雀門に移動して、この講座のハイライトともいえるでしょうか、朱雀門に立って、平城遷都の詔を読み上げました。
朱雀門から南に向かって立ち、先生の後について、元明天皇になったつもりで、みんなで読み上げます。

この写真は、朱雀門に向かってぞろぞろ歩いている図です。
読み上げるのは、この門の上に立って南を向いて行います。
「まさにいまへいじょうのち、しきんとにかない、さんざんしずめをなす。きぜいならびにしたごう、よろしくとゆうをたつべし。よろしくとゆうをたつべし。」(『続日本紀』和銅元(708)年2月15日条)
「しきん」は四禽で、青龍、白虎、朱雀、玄武です。「さんざん」は三山で、藤原宮では耳成山、香具山、畝傍山ですが、平城宮ではそれが、平城山、御蓋山(春日山)、生駒山になるのだそうです。
先生は、これを暗誦しながら、最後は怪しい教祖のように、両手を挙げて「よろしくとゆうをたつべし。」とやりました。
この朱雀門での怪しい集団の行為が名物になって、取材も入ったこともあるとか?
まあ、まさにその現地に立ち、声に出して読むというのはすてきなことです。思い出に残ります。奈良ではそういう行為が似合う場所がたくさんありそうですね。
そこで解散となりました。大極殿は閉まっていて、そっちの方は皆さん行ったこともあるのか、私もありますが、そのまま帰る人あり、私は、平城宮跡資料館に行ったことがなかったので、行ってみました。本当は、歩いて、海龍王寺の方まで行ってみたかったのですが、雨が強くなってきたので、断念しました。

資料館のミュージアムショップで、考古学の発掘スコップ型のスプーンを購入しました。
さらに次回に続けます。
☆









