夏休みのスクーリング・学外授業の続きを紹介します。唐古・鍵遺跡→纏向遺跡を見学した後、お昼をはさんで箸墓古墳に向かいました。
箸墓古墳は、高校教科書(山川日本史B)にも、「出現期の前方後円墳として最大の規模をもつ」として、写真入りで掲載されています。卑弥呼の墓とは教科書には書いてありませんが、卑弥呼の墓ではないかと考える人達もいます。

宮内庁では「大市墓(おおいちのはか)」=孝霊天皇皇女の倭迹迹日百襲姫(ヤマトトトビモモソヒメ)命の墓として管理しています。
『日本書紀』でも倭迹迹日百襲姫が箸墓に葬られたことが記述されています(崇神記10年条)。
宮内庁が管理している陵墓のため、古墳に立ち入って調査をすることは基本的にできない状態ですが、卑弥呼かどうかはともかく、女性が葬られている墓なのだろうと思われます。
小雨の中、バスで現地に到着し、箸墓古墳脇の、ため池に面した小高い場所に登り、先生の説明を聴きました。内容についてはあまり記憶がありません(笑)。
その特徴の一部をレジュメから抜き出すと、
「特殊器台型埴輪、特殊壺、二重口縁壺など吉備系の祭祀土器出土」
「出土土器が布留0式に属し、最近のC14年代測定では紀元240~260年とされる」(2009年5月29日付朝日新聞の記事のコピーもあり)
「後年、壬申の乱でここが戦地となった記述(『日本書紀』天武天皇元年7月2日条)
古墳は本当に巨大で、私が見た古墳の中では一番規模が大きいものでした(そもそも関西の古墳を見たのは初めてというくらい古墳に関してはビギナー)。
大きな山のようで、あの前方後円の、鍵穴型の形をしているかどうかなんて、全然わかりません。やはり上空から見ないとわからないくらい巨大なものです。
女性一人のために、こんなに巨大な墓を作ったのか・・・?と改めて考えさせられます。

お話を聴きながら観察していると、古墳の横に広がる大きなため池に、文字通り縦横無尽に、釣り糸のような透明な糸がはりめぐらされています。何の目的でそんな状態になっているのか、その場ではわからず、人間が舟などでこっそり池を渡って古墳に上陸したりするのを防ぐためかなあ、などと考えていたのですが、後で調べると、そのため池で金魚を養殖していて、鳥が金魚を食べに来るのを防ぐためらしいです。

その箸墓古墳の周囲の南側を歩いて通過し、JR桜井線の線路をはさんで向こう側にあるホケノ山古墳に向かいました。
箸墓古墳は入っちゃいけないのですけれども、地続きの部分は、厳重な高い柵などがあるわけでもなく、道路から簡単に入って行けそうな状態なので驚きました。もしかして、侵入すると赤外線か何かにひっかかって警備員が駆け付けて来るのかもしれませんけれども。
こういう場所のすぐそばで暮らしている人達は、どういう気持ちでこの古墳と共存しているのでしょうか?

↑簡単に入れそう
この日は雨で、夏にしては気温が低めでしたが、それでもいくらか蒸し暑く、普段運動不足の私は、くたくたでダウンしそうな気分でした。ホケノ山古墳まで歩き、また歩いて戻ると思っていなかったし。しかし、かなり高齢の方や、足が少し不自由そうな方も、みんな歩いているので、このくらい何でもないと思って歩くしかないかな、と考えました。もしカンカン照りだったら、私は間違いなくリタイヤしていたでしょう。天気が悪くてよかったのかもしれません。夏の奈良盆地での学外授業は過酷ですね。

纏向遺跡の時にも使った「卑弥呼さん」という呼び方は、講師の先生がしていたもので、なんだか親しみを感じてよいなと思ったので、ここでもそうしました。
今年は、関西弁・・・奈良弁てあるんでしょうか?それに接することの多かった年でした。科目修得試験を東京で行う時にも、職員は奈良からいらっしゃっていたようで、関西弁でお話しされるので和みました。大阪や京都ともまた奈良は違うんだろうと思います。私は、奈良の人達のお話しする雰囲気は、のどかで、気圧される感じもなくて、嫌いではありません。
いったんここで切りましょうか。箸墓古墳が「卑弥呼さん」の墓なのかどうか、私の考えについては、次の機会に整理したいと思います。
次は、ホケノ山古墳から続けて書きたいと思います。
↓ クリック応援していただけますとありがたく存じます。ご訪問ありがとうございます。
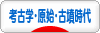 にほんブログ村
にほんブログ村
箸墓古墳は、高校教科書(山川日本史B)にも、「出現期の前方後円墳として最大の規模をもつ」として、写真入りで掲載されています。卑弥呼の墓とは教科書には書いてありませんが、卑弥呼の墓ではないかと考える人達もいます。

宮内庁では「大市墓(おおいちのはか)」=孝霊天皇皇女の倭迹迹日百襲姫(ヤマトトトビモモソヒメ)命の墓として管理しています。
『日本書紀』でも倭迹迹日百襲姫が箸墓に葬られたことが記述されています(崇神記10年条)。
宮内庁が管理している陵墓のため、古墳に立ち入って調査をすることは基本的にできない状態ですが、卑弥呼かどうかはともかく、女性が葬られている墓なのだろうと思われます。
小雨の中、バスで現地に到着し、箸墓古墳脇の、ため池に面した小高い場所に登り、先生の説明を聴きました。内容についてはあまり記憶がありません(笑)。
その特徴の一部をレジュメから抜き出すと、
「特殊器台型埴輪、特殊壺、二重口縁壺など吉備系の祭祀土器出土」
「出土土器が布留0式に属し、最近のC14年代測定では紀元240~260年とされる」(2009年5月29日付朝日新聞の記事のコピーもあり)
「後年、壬申の乱でここが戦地となった記述(『日本書紀』天武天皇元年7月2日条)
古墳は本当に巨大で、私が見た古墳の中では一番規模が大きいものでした(そもそも関西の古墳を見たのは初めてというくらい古墳に関してはビギナー)。
大きな山のようで、あの前方後円の、鍵穴型の形をしているかどうかなんて、全然わかりません。やはり上空から見ないとわからないくらい巨大なものです。
女性一人のために、こんなに巨大な墓を作ったのか・・・?と改めて考えさせられます。

お話を聴きながら観察していると、古墳の横に広がる大きなため池に、文字通り縦横無尽に、釣り糸のような透明な糸がはりめぐらされています。何の目的でそんな状態になっているのか、その場ではわからず、人間が舟などでこっそり池を渡って古墳に上陸したりするのを防ぐためかなあ、などと考えていたのですが、後で調べると、そのため池で金魚を養殖していて、鳥が金魚を食べに来るのを防ぐためらしいです。

その箸墓古墳の周囲の南側を歩いて通過し、JR桜井線の線路をはさんで向こう側にあるホケノ山古墳に向かいました。
箸墓古墳は入っちゃいけないのですけれども、地続きの部分は、厳重な高い柵などがあるわけでもなく、道路から簡単に入って行けそうな状態なので驚きました。もしかして、侵入すると赤外線か何かにひっかかって警備員が駆け付けて来るのかもしれませんけれども。
こういう場所のすぐそばで暮らしている人達は、どういう気持ちでこの古墳と共存しているのでしょうか?

↑簡単に入れそう
この日は雨で、夏にしては気温が低めでしたが、それでもいくらか蒸し暑く、普段運動不足の私は、くたくたでダウンしそうな気分でした。ホケノ山古墳まで歩き、また歩いて戻ると思っていなかったし。しかし、かなり高齢の方や、足が少し不自由そうな方も、みんな歩いているので、このくらい何でもないと思って歩くしかないかな、と考えました。もしカンカン照りだったら、私は間違いなくリタイヤしていたでしょう。天気が悪くてよかったのかもしれません。夏の奈良盆地での学外授業は過酷ですね。

纏向遺跡の時にも使った「卑弥呼さん」という呼び方は、講師の先生がしていたもので、なんだか親しみを感じてよいなと思ったので、ここでもそうしました。
今年は、関西弁・・・奈良弁てあるんでしょうか?それに接することの多かった年でした。科目修得試験を東京で行う時にも、職員は奈良からいらっしゃっていたようで、関西弁でお話しされるので和みました。大阪や京都ともまた奈良は違うんだろうと思います。私は、奈良の人達のお話しする雰囲気は、のどかで、気圧される感じもなくて、嫌いではありません。
いったんここで切りましょうか。箸墓古墳が「卑弥呼さん」の墓なのかどうか、私の考えについては、次の機会に整理したいと思います。
次は、ホケノ山古墳から続けて書きたいと思います。
↓ クリック応援していただけますとありがたく存じます。ご訪問ありがとうございます。















