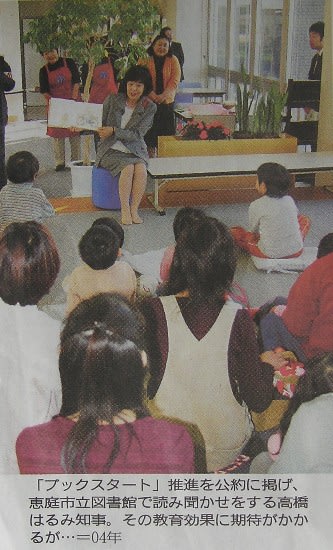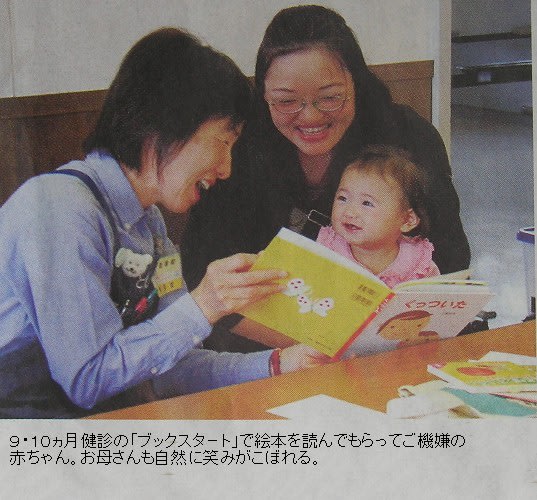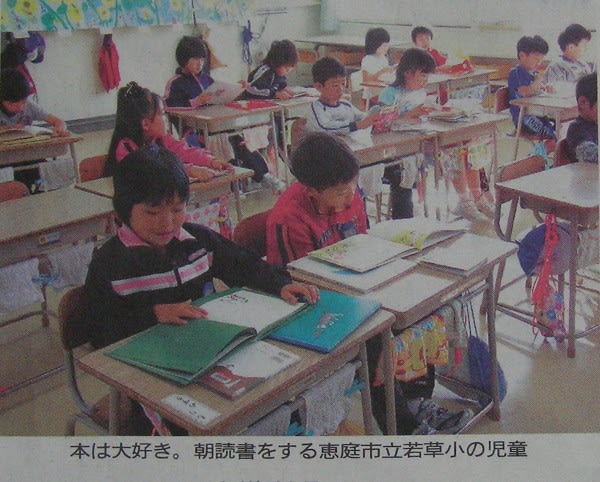パン教室「カフェ・タブリエ」主宰 森本 まどか 酵母の働きで大きく膨張
 パンはなぜ膨らむのでしょう?それは酵母の持 つ不思議な力によるものなのです。パン生地の 中で、酵母は粉に含まれる糖分をエサに、炭酸 ガスとアルコ-ルを発生させながら増殖していき ます。この炭酸ガスは行き場を求め、生地をこねる時に取り込まれた 無数の空気の穴、つまり「気泡」に、中身の空気を押し出す形でな がれこんでいきます。こうして気泡の内部のガス圧が高まり、パン 生地はゆっくりと膨らんでいくのです。パンをスライスしてみてくださ い。たくさん空いている小さな穴が、気泡の跡です。パンの種類によ り、気泡の数や大きさが違います。あまりこねない水分の多いハ-ド 系のパンだと、気泡は大きく数は少なめ。小さな気泡が多いのは菓 子パンや食パンなどで、こねる回数が多く、きめが細かいです。発酵 中のガスで十分大きくなった気泡は、オ-プンに入れて焼くと温度が 上がりさらに内圧を高め、上へ上へとパン生地をふんわり膨らませま す。暖めた熱気球が空高く上昇するように、パンも復任でいくのです。 うんと膨らますには、ガスを旺盛に出す活発な酵母と、ガスを逃さない 薄くて丈夫なグルテン膜を持つ生地が必要になります。
パンはなぜ膨らむのでしょう?それは酵母の持 つ不思議な力によるものなのです。パン生地の 中で、酵母は粉に含まれる糖分をエサに、炭酸 ガスとアルコ-ルを発生させながら増殖していき ます。この炭酸ガスは行き場を求め、生地をこねる時に取り込まれた 無数の空気の穴、つまり「気泡」に、中身の空気を押し出す形でな がれこんでいきます。こうして気泡の内部のガス圧が高まり、パン 生地はゆっくりと膨らんでいくのです。パンをスライスしてみてくださ い。たくさん空いている小さな穴が、気泡の跡です。パンの種類によ り、気泡の数や大きさが違います。あまりこねない水分の多いハ-ド 系のパンだと、気泡は大きく数は少なめ。小さな気泡が多いのは菓 子パンや食パンなどで、こねる回数が多く、きめが細かいです。発酵 中のガスで十分大きくなった気泡は、オ-プンに入れて焼くと温度が 上がりさらに内圧を高め、上へ上へとパン生地をふんわり膨らませま す。暖めた熱気球が空高く上昇するように、パンも復任でいくのです。 うんと膨らますには、ガスを旺盛に出す活発な酵母と、ガスを逃さない 薄くて丈夫なグルテン膜を持つ生地が必要になります。