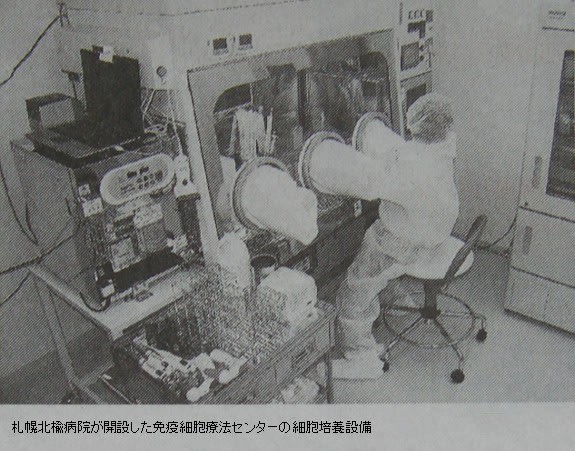ファ-ストフ-ド犯人説に重要度大?
欧米人の体質は、陽性タイプが圧倒的に多いといわれています。 その上、特に重要な特徴は膵臓で精製されるインシュリンの量が、 日本人に比べ非常に多いとのことです。そのため、食した糖分を ブドウ糖に還元し体内に吸収する機能が大きいため、日本人に比 べて想像を絶する体形の人たちを、メデアを通じまた訪日者等で知 ることとなります。根本的異質の人たちがファ-ストフ-ドを習慣的 にこよなく愛し日常的に食している。同国の人の中で、肥満の最悪 玉に一番に挙げています。その言い分は、何か習慣化するような 成分を、混入しているのではないかとの説です。わが国でも肥満対 策には、如何に腹八分目で摂取量を抑えることが大事かといいます。 イタリアが発祥地といわれています、スロ-フ-ズの考え方も、ゆっ くり食事を楽しみ、量よりも質を重んじる考え方と理解します。そこで 言われることに、出来うる限り日頃の食事量を減らし尚且つ満腹感 を感じ取るか、如何にして摂取量を減らすかという努力です。一つは、 ゆっくりと噛む回数を増やして飲み込むことが量の抑制につながると の提言です。ところが米国人の好む、ファ-ストフ-ドは余りにもソフ トに出来ていて、噛むことよりも飲み込むという形容が当たっている 食品です。またよく好んで食すポップコ-ンなどは、食べ始めたら全 部食すまで途中で止められません。とに角、歯応えのない軟らかい 食事を取り続ける限り腹八分目は望むべきもないと言うことです。 ケ-キをより固めのビスケットにする。また時間の掛かりそうな魚料 理(煮魚や焼き魚等)を多く取り入れるなど内容を変革するなどの努 力は必要ではないでしょうか。日本を訪れて、日本食、特に玄米食な どを好む人たちがいらっしゃいますが、皆さんスマ-トなスタイルを維 持しています。このように自然と食事に時間の掛かる食事内容の食 品への移行を考慮する、そのくらいの努力は健康体を確保する上で の、最小限の妥協だと認識すべきと思われますが・・・?。