
「和同開珎」の「日本最古の貨幣」としての名誉を奪おうとしている「冨本銭(ふほんせん)」とは、いったい何か。
「冨本銭)は、江戸時代から、その存在は知られていた。ところが、1999年、奈良国立文化財研究所は、奈良県明日香村の万葉文化館の建設に当たって飛鳥池遺跡から出土した33枚の冨本銭を分析研究した結果、「日本最古の流通貨幣である可能性が極めて高い」と発表した。
それまでは近畿地方を中心に5枚しか見つかっておらず、奈良時代に作られた「おまじない銭(厭勝銭)」ではないかとみられていた。「厭勝銭」とは、「富本」のような吉祥の文句を鋳出して、縁起物や護符にするもので、中国では漢代から、日本でも室町―江戸時代にあったという。
この33枚は不良品として破棄されたものと判断された。出土した土層が、「和同開珎」が造られた708年より前であること、追加発掘で鋳型や坩堝なども見つかり、出土した金属量から大量に鋳造された形跡が確認されたことから、「和同開珎」より古い銅貨と判定された。
もう一つ関連証拠があった。日本書紀の683年のくだりに「今より以降、銅銭を用いよ。銀銭を使うことなかれ」とあり、その後にも「鋳銭司」という記述があるのに、該当する銅銭がなく、大きな謎とされてきた。
「冨本銭」は、大きさ、形も「和同開珎」や唐の貨幣とそっくり、中央の正方形の孔の上下に「富 本」と縦に書かれている銅銭だ。孔の左右には、7つずつのボツボツ(点)が亀甲型についている。これは、「陰陽と木火土金水」の七星を表すという。
「日本最古の貨幣」の登場である。発表されると、マスコミも大々的に報道、「教科書が書き換えられる」と騒ぎ立てた。
問題は大量鋳造が確認されても、どの程度実際に流通したかである。「冨本銭」はその後、出土のニュースがほとんど伝えられず、全国的に流通したのかどうかは今後の発見に待つしかない。
それにひきかえ、「和同開珎」は全国500か所以上から出土、正倉院文書を初め、多くの文献に流通の記録があるとのこと。今のところ、「和同開珎」は、確実に広範囲に貨幣として流通した「日本最古の流通貨幣」であることは間違いないようだ。
ところで、貨幣がない場合の売買はどのように行われたのか。原始人同様の物々交換である。「和同開珎」も民衆の間で大量に全国的に流通したのではなさそうで、物々交換と併用されたようだ。
1300年前の話なので、「和同開珎」にも謎が多い。採掘された和銅の総量と、いつごろまで採掘されたのか。それを大和までどうして運んだのか。陸路か海路か。海路ならそのルートは。運ばれた銅はどこで鋳造されたのか。発見、採掘に当たったのは、帰化人なのか、日本人なのか――。現地を回りながら、さまざまな疑問が湧いてくる。
和同献上に続いて、749年には陸奥国から黄金が献上され、大仏建立を進める聖武天皇を喜ばせた。石見銀山を訪ねた際も思ったことだが、金、銀、銅・・・日本もかつては豊かな鉱物資源国だったのだなー。

















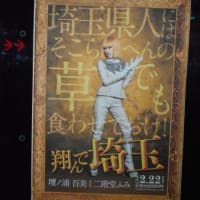


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます