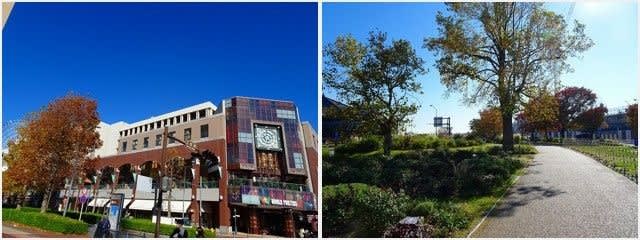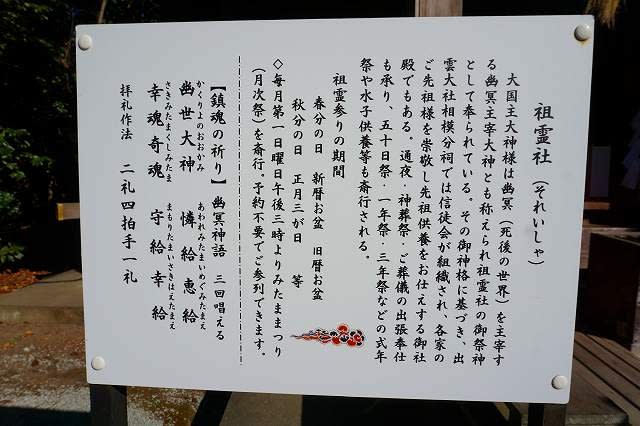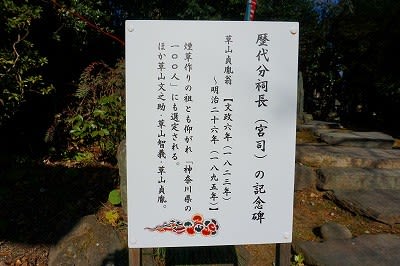最近、息子は昆虫の写真を撮ることに興味を持っており、
週末には近くの公園や、埼玉県の狭山丘陵や蝶の里公園などにも
足を延ばしているようです。
5月25日(日)には、多摩動物園の昆虫館に行くとの電話があり、
もし良かったらと誘ってもらったので、一緒に行ってきました。

曇りでしたが前日の土曜日が雨だったせいか、
多くの家族連れやカップルで賑わっていました。
昆虫園には2箇所の建物とオブジェがあります。
1箇所は昆虫標本などが多数展示してある昆虫園本館。
もう1箇所は大温室で蝶を放し飼いしている昆虫生態館です。
昆虫園本館は最後に時間があったら寄ることにし
まずは昆虫生態館に入りました。

大きなバッタのオブジェがお出迎え
中国人らしき観光客や、小さな子供が乗って記念撮影をしていました。

多摩動物公園のHPより、建物の上から撮った
画像をお借りしましたが、
チョウのいる昆虫生態感の建物は蝶の形、
昆虫の標本などが沢山展示されていた昆虫園本館は
トンボの形をしていたのですね。
下から見ている時は気が付きませんでした。

昆虫生態園に入ります。
中は日本最大級の放チョウ温室になっており、
沢山(約15種類だとか)のチョウが優雅に飛び交っていました。


オオゴマダラ黄金のさなぎ

オオゴマダラ
オオゴマダラはタテハチョウ科の蝶で、日本の蝶としては
最大種の1つだそうです。昔、沖縄旅行をしたとき、
蝶々園で見たことを思い出しましたが、沖縄県の県蝶だったようです。
白地に黒い斑(まだら)模様でゆっくり優雅に飛ぶのが特徴で、
黄金のさなぎもとても綺麗でした。

アオタテハモドキ

アオタテハモドキ
アオタテハモドキは前タテハチョウ亜科のタテハモドキ属の
翅長2 – 3cm前後の小さな蝶で、アフリカ・東南アジア、
日本では沖縄、八重島列島などの南西諸島に生息しているそうです
後翅の青い模様と眼状紋が特徴的で、翅色の変異が多い種類だとのこと。

沖縄の花「デイゴ」
マメ科デイゴ属の落葉高木
原産地は東アフリカ、インド、太平洋諸島

白や薄紫のアゲラタムに集う蝶たち


リュウキュウアサギマダラ
リュウキュウアサギマダラはタテハチョウ科に属する
チョウの一種でアサギマダラ属のアサギマダラとは別属だとのこと。
アサギマダラより一回り小さく、前翅と後翅で地色が同じで、
翅の模様もリュウキュウアサギマダラのほうが細かいそうです。。
日本では鹿児島県の奄美大島以南の地域に分布しており、
移動性はなく、奄美大島より北では迷蝶となっているそうです。
(迷蝶:台風などの風で飛ばされてやってきた蝶)

ブーゲンビリア
オシロイバナ科ブーゲンビリア属の低木
原産は南アメリカ

ベニモンアゲハ
ベニモンアゲハはアゲハチョウ科に属するチョウの一種
和名通り後翅に鮮やかな赤の斑点が並ぶ。
もともと日本には分布しておらず、南方からきた迷蝶として
八重山諸島で時々記録されていたが、1968年ごろから土着し始めたとのこと。

ツマベニチョウ
ツマベニチョウはシロチョウ科に分類されるチョウの一種。
シロチョウ科では世界最大級の種開張約9-10cm。
前翅先端の先端には三角形の黒い部分があり、
その中に大きな橙色の紋をもつ。
日本では宮崎県が北限で、鹿児島県や沖縄県に分布する。

蝶の名前がわからず調べたのですがよくわかりません。
疲れ果てたツマベニチョウを翅の裏側から撮ったものかもしれません。

シロオビアゲハ
シロオビアゲハはアゲハチョウ科に分類されるチョウの1種。
成虫は前翅長50mm前後、開張約7 - 8cmほどで、
他のアゲハチョウ類に比べると小型。
和名は後翅に白い斑点が列を成していて、翅を縦断する白い帯模様を
形成することに由来している。
本州では観察できないが、沖縄では普通に生息している。

ツマムラサキマダラ♂(オス)

ツマムラサキマダラ♂(画像はお借りしました)

ツマムラサキマダラ♀(メス)
ツマムラサキマダラはタテハチョウ科 マダラチョウ亜科に
分類されるチョウの1種で、前翅表の先が光の方向によって
鮮やかな紫色に輝くチョウです。
日本では八重山諸島・沖縄地方・奄美諸島で見られ、
多化性でほぼ一年中現れるそうです。

カバタテハ
カバタテハはタテハチョウ科に分類される蝶で、
以前は迷蝶として扱われていたそうですが、現在か石垣島、西表島、
波照間島、竹富島などで確認されているそうです。
暑い地域にしか生息していないので成虫は一年中活動しているとのことです。

ハイビスカス
ハイビスカスはアオイ科フヨウ属に分類される常緑低木
原産地はハワイ諸島、モーリシャス島などで、
沖縄では庭木として古くから植えられて親しまれてきました。
我が家でも冬は室内に取り込みますが、何年も育てています。

イシガケチョウ
イシガケチョウはタテハチョウ科に分類されるチョウの一種で、
和名通りの石崖・石垣模様を持ち、ひらひらと紙切れが舞うように飛ぶます。
温暖化により北上している蝶のひとつでもあり、
国内では年々分布域を広げているそうです。
確実に土着しているのは紀伊半島以南・四国・九州・南西諸島などで、
渓谷沿いの照葉樹林や疎林に多く、平野部ではほとんどいないとのことです。

スジグロモンシロチョウ
スジグロシロチョウはモンシロチョウと同じモンシロチョウ属する蝶で
知名度が低いためか、モンシロチョウと混同されることが多いようです。
日本全国広く分布しており、比較的暗い場所を好み、
市街地や都心部よりも、住宅地や山村、公園の樹木の中などに多く、
こうした場所ではモンシロチョウよりも多くみられるそうです。

アゲハ蝶
アゲハ蝶はアゲハチョウ科に分類され、黒と黄色のシマシマ模様が
特徴的な大型のチョウの仲間で、どこにでも見られる身近な蝶です。
成虫はほぼ全ての種類が花に飛来するが、幼虫はミカン科の植物を
食草とするので、我が家ではその一生をくまなく観察することができます。
初めて知ったのですが、アゲハ蝶はキリスト教では「魂の復活」を
司ると考えられ、仏教では「輪廻転生」の象徴とされているそうです。

ツダナナフシ
どこにツダナナフシが止まっているかわかりますか?
ツダナナフシはナナフシ目ナナフシ科ツダナナフシ属の昆虫で、
ニューギニア~台湾~石垣島や西表島の沖縄に生息しているそうです。
海岸に生息し、好物はアダンやタコノキの葉。
雄より雌の方が身体が大きく、身体には翅があり、
体表色は光沢のある緑色です。刺激されると首筋からハッカ臭のする
白い液体を噴射するそうですよ。

トノサマバッタ
トノサマバッタはバッタ目バッタ科トノサマバッタ属の昆虫。
ユーラシア大陸北部やアフリカ、日本に分布する。
体長は35-65mmの大型のバッタで、オスよりメスの方が大きい。
バッタというと緑色のイメージがあったので、
黒いバッタを見てちょっとびっくり
調べてみると、トノサマバッタは1匹だけでいると緑色になり(孤独相)、
仲間といると黒くなり(群生相)、見た目や生態が変化するそうです。
ここのバッタは集団で飼育されたため黒くなったようです。
【多摩動物公園】トノサマバッタの不思議
この後、動物園も歩いてきました。
その写真はおいおいにアップして行こうと思います。










































































































 ]
]