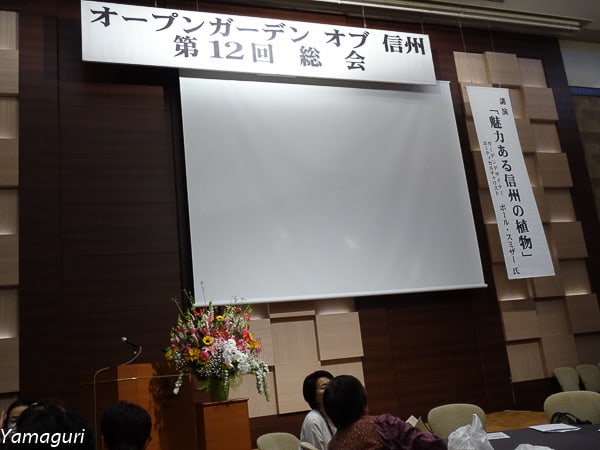昨夜から降り続いていた雨が上がった。朝食をゆっくり食べる。それにしても、花屋は何とも風情のある温泉宿だ。


花屋を後にして、長野に向かう。折角だから、「おぎはら植物園上田店」を覗いてみた。

欲しくなってくる宿根草が、あるある。時間をかけてゆっくり見たいところだが、午後1時からの総会に間に合わなくなるので、目についた花苗を買って、すぐに店を出た。
JR長野駅は、北陸新幹線の開業に合わせたのか、すっかりリニューアルしていた。
しかも今年は、7年に1度の善光寺の御開帳の年だ。その催しが明日から始まるとのことで、全国から700万人の観光客が押し寄せるらしい。

さて、オープンガーデンオブ信州の「第12回総会」は、長野駅隣の「ホテルメトロポリタン長野」で13時より開催された。

会場には、昨年、清里のアダージョの森を訪れていただいた模様が、パネルにして展示されていた。

総会では2014年度の事業報告、2015年度の事業計画とも承認された。今年は埼玉県深谷市のオープンガーデンを訪ねるとのことだ。
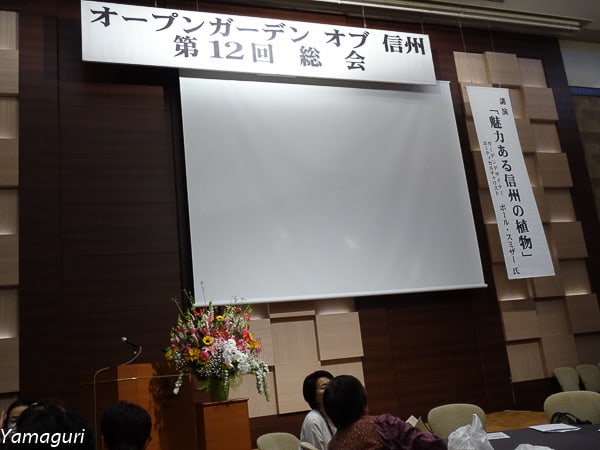
総会の後「ガーデンチャリティイ」があり、花苗や手作りの作品などが格安の料金で出品されていて、それの収益金が義援金として被災地に寄付されることになっている。

15時からは、ポール・スミザー氏の講演があった。題して「信州の魅力ある植物」。ここからは、会員とは別に一般の市民の方も参加することになっていたが、
用意していた椅子が足りなくなるほどの盛況ぶりで、ポールさんの人気のほどが推し量られる。

「20年あまり前に日本に来てから、やっと合点がいった。長野県の高山の花畑に文字通り迷い込んだ私は、野生のヘメロカリス、クガイソ
ウ、シャクナゲ、シモツケソウ、ギボウシが生い茂るのを目の当たりにしたのだ。これらはいずれも、イングランドで勉強していた時には
肥料をやるべき植物として教えられていたものだ。しかし、山地の奥深く、人の手が一切入らないところで、これらの植物はみな、いたっ
て健康そうに見えた。外来種も、せんじ詰めればほかの誰かにとっては在来種なのだ。
それ以来、植物はそれが適応している場所に植えることが、よく育つか否かを決める最も重要な要因だとわかってきた。そのうえで、多年
草を株分けして新芽の生育を促したり、樹木であれば的確な剪定をして若返りを図ったりすることが、植物の活力を維持するために必要に
なる。
腐葉土や樹皮堆肥で根覆いをすれば、植物の水分を保ち、雑草の生育を抑え、バクテリアやミミズを活発にする土壌を育てることができる
。」(The Midori Press より)
ポール・スミザーの話は、実に面白く、退屈させない。庭造りは難しく考えるのではなく、できる限り簡単に、「適当に」やればいいという 。
あくまでも自然の力に任せるというやり方だ。バラの話は全くなかった。要は信州の自然になじむ庭造りだ。
彼のナチュラルな庭作りの考え方に大いに考えさせられた。