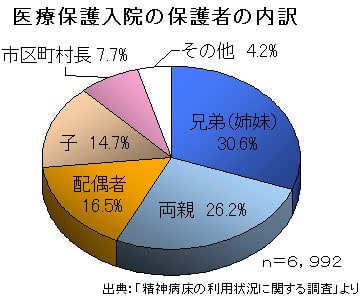「税と社会保障の一体改革」素案の要旨は以下の通り。
<社会保障改革>
【子ども・子育て】
・地域の実情に応じた保育の量的拡充、幼保一体化の機能強化などを行う子ども・子育て新システムを創設。
・恒久財源を得て早期に本格実施。それまでの間は13年度をめどに子ども・子育て会議(仮称)設置や国の基本指針策定など可能なものから段階実施。12年通常国会に法案提出。
【医療・介護】
・高齢化が一段と進む25年にどこに住んでも適切な医療・介護が受けられる社会を実現。
・できる限り住み慣れた地域で在宅生活の継続を目指す地域包括ケアシステムの構築に取り組む。24時間対応の訪問サービスを充実。
・短時間労働者への被用者保険の適用を厚生年金の適用拡大にあわせ拡大。12年通常国会への法案提出を検討。
・高額療養費負担の年間上限導入などを財源確保の上で目指す。年収300万円以下程度の人に特に配慮する。
・高齢者医療の支援金を各被用者保険者の総報酬に応じた負担とする措置を検討。12年通常国会に後期高齢者医療制度廃止に向けた見直し法案提出。
・70歳以上75歳未満の患者負担見直しを世代間の公平を図る観点から検討。
・所得水準の高い国民健康保険組合への国庫補助を見直す。12年通常国会への法案提出を検討。
・65歳以上の介護保険料の低所得者軽減策を強化。12年通常国会への法案提出を検討。
・介護納付金の総報酬割の導入を検討。12年通常国会への法案提出を検討。
・医療・介護・保育などの自己負担合計額に上限を設ける「総合合算制度」を創設。15年度以降の導入検討。
【年金】
1新年金制度の創設
・「所得比例年金」と「最低保障年金」を組み合わせた一つの公的年金制度に全員が加入する新年金制度の創設実現に取り組む。
・所得比例年金(社会保険方式)は職種を問わず全員が同じ制度に加入し所得が同じなら同じ保険料、同じ給付。保険料は15%程度(老齢年金にかかる部分)。納付した保険料を記録上積み上げ、仮想の利回りを付し、合計額を年金支給開始時の平均余命などで割り毎年の年金額を算出。
・最低保障年金(税財源)は満額で7万円(現在価値)。生涯平均年収ベース(=保険料納付額)で一定の収入レベルを超えた点より徐々に減額、ある収入レベルで給付額はゼロ。全受給者が所得比例年金と最低保障年金の合算で概ね7万円以上を受給できる制度に。
・13年の国会に法案を提出。
2現行制度の改善
・新年金制度の創設には一定の時間を要することなどから、新年金制度の方向性に沿い現行制度の改善を図る。
・消費税引き上げ後に消費税財源による国庫負担2分の1を恒久化。12年度の基礎年金国庫負担割合は歳出予算と「年金交付国債」(仮称)により2分の1を確保。必要な法案を12年通常国会に提出。
・13年度から消費税引き上げまでの取り扱いは引き続き検討。
・低所得者の老齢基礎年金や障害・遺族基礎年金に加算を実施。
・無年金者が納付した保険料に応じた年金を受給できるようにし、受給資格年数を現在の25年から10年に短縮。消費税引き上げ年度から実施。12年通常国会への法案提出を検討。
・高所得者の老齢基礎年金を調整する制度を創設。12年通常国会への法案提出を検討。
・マイナスの物価スライドを行わなかったことなどで2.5%本来より高い水準の年金額で支給している措置を12年度から3年間で解消、12年度は10月から実施。12年通常国会に法案提出。
・産休期間中の保険料負担を免除、将来の年金給付には反映させる。12年通常国会への法案提出を検討。
・厚生年金適用事業所の短時間労働者に厚生年金の適用を拡大。12年通常国会への法案提出を検討。第3号被保険者制度、配偶者控除の見直しとともに総合的な検討を行う。
・共済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向を基本に被用者年金を一元化。公務員、私学教職員の保険料率や給付内容を民間サラリーマンと同一化する。12年通常国会への法案提出を検討。
・第3号被保険者制度は新しい年金制度の方向性(2分2乗)を踏まえ検討。
・マクロ経済スライドの適用について物価スライド特例分の解消状況も踏まえ検討。
・60代前半にかかる在職老齢年金制度について調整限度額を引き上げる見直しを検討。
・厚生年金の標準報酬の上限見直しを検討。
・支給開始年齢のあり方について中長期的課題として検討。
【その他】
・無収入の高齢者世帯が発生しないよう継続雇用制度の基準に関する法制度を整備。
・生活保護基準、各種福祉手当は物価スライドなどの措置で消費税引き上げによる影響分を手当額に反映。
・生活困窮者対策と生活保護制度の見直しに総合的に取り組むための生活支援戦略を12年秋をめどに策定。
・日本発の革新的な医薬品・医療機器の創出などの拠点となる臨床研究中核病院(仮称)を創設。
<税制改革>
【基本的方向性】
・今回の税制抜本改革の最大の柱は社会保障財源を確保するための消費税率引き上げ。幅広い国民が負担する消費税は高齢化社会における社会保障の安定財源としてふさわしい。
【消費税】
・14年4月に8%、15年10月に10%に引き上げる。
・食料品などに軽減税率を適用した場合、高額所得者ほど負担軽減額が大きくなること、課税ベースが大きく侵食されること、事業者の負担が増すことなどを踏まえ今回の改革では単一税率を維持。
・消費税収(国分)は全額社会保障4経費(年金、医療、介護、少子化対策)に充てることを明確にし社会保障目的税化。地方の消費税増収分も社会保障財源化する。
・事業者免税点制度、簡易課税制度は中小事業者の事務負担への配慮から制度を維持。(個々の取引の消費税額などを示す)インボイス(荷送り状)制度は導入しない。
・値札などの「総額表示」の義務付けは、維持を基本とする。
・引き上げ分の消費税収の地方分は消費税率換算で14年4月から0.92%分、15年10月から1.54%分とする。
・住宅取得については一時の税負担の増加による影響を平準化、緩和する観点から必要な措置について財源も含め総合的に検討する。
・社会保険診療は非課税。医療機関などが行う高額投資にかかる消費税負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し、区分して手当てを行うことを検討。これにより医療機関などの仕入れにかかる消費税については診療報酬など医療保険制度で手当てする。
【逆進性対策】
・所得の少ない家計ほど食料品向けを含めた消費支出の割合が高いため消費税負担率も高くなるという逆進性の問題も踏まえ、15年度以降の番号制度の本格稼働・定着後の実施を念頭に総合合算制度や給付付き税額控除など、再配分にかんする総合的な施策を導入。
・総合的な施策の実現までの間の暫定的、臨時的措置として、簡素な給付措置を実施。
【景気弾力条項】
・法案成立後、引き上げにあたっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応できる仕組みを設ける。
・消費税率引き上げ実施前に「経済状況の好転」について、名目・実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況などを総合的に勘案した上で、引き上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする規定を法案に盛り込む。
【消費税以外の消費課税】
・酒税は類似する酒類間の税負担の公平性も踏まえ、消費税率の引き上げにあわせて見直しを行う方向で検討。
・地球温暖化対策税は12年度税制改正で引き続き実現を図る。
・自動車取得税および自動車重量税については、簡素化、負担の軽減、グリーン化の観点から見直しを行う。
【個人所得税】
・15年分の所得税から、課税所得5000万円超について45%の税率を設ける。特に高い所得階層に一定の負担増を求めることにより累進性を高める。
【金融所得課税】
・上場株式配当・譲渡所得にかかる10%軽減税率を14年1月から20%の本則税率とする。
【相続税】
・相続税基礎控除のうち定額控除を現行の5000万円から3000万円に、法定相続人比例控除を現行の1人当たり1000万円から600万円に引き下げる。
・最高税率を現行の50%(3億円超)から55%(6億円超)へ引き上げ、2億円超にかかる税率も引き上げる。
・一体改革の中で実現を図る。
【年金税制】
・年金受給者は給与所得者に比べ課税最低限が高いなど税制上優遇されている状況であり、世代間の公平性の確保も必要。年金収入に応じて控除額が増加していく現行の公的年金等控除の仕組みを見直すなど種々の方策を検討する必要がある。
【地方税制】
・財源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築。地方法人特別税および地方法人特別譲与税は、一体改革にあわせて抜本的に見直す。
【改革スケジュール】
・本素案に沿った各税目の改正内容・時期を盛り込んだ法案を11年度中に提出する。
・50年以降、高齢化のピークを迎えることを考慮すれば今後も改革を進める必要がある。今回の改革に引き続き、少子高齢化、財政、経済の状況などを踏まえつつ次の改革を実施することとし、今後5年をめどに所要の法律上の措置を講じることを今回の改革法案の附則に明記する。
【政治・行政改革】
・議員定数削減や公務員総人件費削減など自ら身を切る改革を実施した上で、税制抜本改革による消費税引き上げを実施すべき。
・衆議院議員定数を80削減する法案などを早期に国会提出。
・独立行政法人改革、公益法人改革、特別会計改革、国有資産見直しなどに向け行政構造改革実行法案(仮称)を早期に国会提出。閣議決定ベースで可能な改革は直ちに実行。
・給与臨時特例法案、国家公務員制度関連法案の早期成立を図る。
毎日新聞 2012年1月6日 21時33分