毎日肌寒い日が続きます。暑さ対策でトイレに置いてあった、タワーファンをグルニエにしまおうとしたら、スペースがどうしても確保できず、置いてあった先住者のグラシックギターを楽器部屋に移管することに。
ずっとケースにしまいっ放しだったので、恐る恐る開けてみたところ、あまりに可哀想な風情だったので、メンテナンスをしてあげることにしました。おそらく30年ぶりぐらいかも、もしかしたら、大学卒業以来かもしれません。
サビサビだったフレットを磨いてあげます。うちには何でも専用の道具がそろっています。

ビカビカになりましたが、よく見ると指版に細かいヒビが。経年変化と乾燥によるものと思われます。指版そのものも汚れていますね。

黒檀(エボニー)の指版ですが、ローズウッド用のレモンオイルで保湿と汚れ落としをしました。WEB情報では、レモンオイルで問題ないようです。おかげで真っ黒さを取り戻しました。

糸巻きの心棒にひびが入っていたので、瞬間接着剤を流し込んでおきます。
全とっかえという方策も考えたのですが、間隔が39mmという特殊な部材で、下手すると20,000円ぐらいしそうなので、なんとか当面これで持たせたいと思います。

ボディトップにラッカー塗装の特徴のウェザークラックを生じていますが、これは、味ということで、専用ワックスとポリッシュで磨きと保護をしておきました。
ということで、あとは、明日配送されるであろう「セット弦」待ちです。

弦が届くまで音を出せませんので、 それまで、いままで、探求したこともなかったこのギターの蘊蓄を探ってみます。
製作者は、「中村 篤」氏。製作年代は1960年代(後半?)と思われます。

ラベルが染みでほとんど判別ができなくなっていますが、オークションに出品されている同氏のギターに同一のラベルが貼ってあったので、この写真を参考にします。

スペイン語で記載されています。
ATUSHI NAKAMURA (中村 篤)
LUTHIER(弦楽器職人)
Construction Artistics de guitarra y viollina(ギターとバイオリンの芸術的な製作)
どうも、バイオリンやマンドリン等、他の楽器も作られていたようです(昔、部活のマンドリンを買いに行ったときに、一緒のアトリエに中村 篤さんのギターが置いてありました。そういうところと取引があったようです)。
Modelo(モデル) La caja-A.Torres (ボディは A.Torres)
La cabeza-M.Ramirez(ヘッドは M.Ramirez)
Año(年)nún(番号) Tokio Japan (シリアル番号は他の個体にも入っていないようです。東京に工房があったということのようです。)
※アントニオ・デ・トーレス(Antonio de Torres, 1817年6月13日 - 1892年11月19日)は、スペイン・アルメリア出身のギター製作家。現在製作されているクラシック・ギターの原型となるモダンギターを製作した人。
トーレスのギターは、当時の19世紀ギターと比べ、弦長を長く、ボディーサイズは大きく(体積増)、表板は薄く、扇形力木やトンネルなどの力木の変更がなされている。トーレスの製作方法や設計を模倣した伝統的なギターを製作する製作家も多い。
※マヌエル・ラミレス(Manuel Ramirez 1866-1916) スペイン・マドリッドのフランシスコ・ゴンザレス(1830-1880)の元で伝統的なマドリッド派のギター製作を学んだ後、トーレスの優秀さを認めいち早くトーレススタイルを取り入れたギター製作を確立。マドリッドを代表する製作家。
つまり、胴体(ボディ)はアントニオ・トーレス型に、ヘッドの部分はマヌエル・ラミレス型をモデルとしている、との意味でしょうか? たしかに、ヘッドの形状は真ん中の山が尖って、麓に切れ込みのあるラミレス型にある形です。

Jose Ramirez ホセ ラミレス C650
中村 篤 氏 の 名前は、WEB を検索しても、オークションの商品として散見するぐらいで、その経歴と業績はほとんど見当たりません。
ただ、松阪市民ギター音楽協会 の WEB の 中出 阪蔵氏の紹介の中に、中出氏のお弟子さんとして、中村 篤 氏 の名前があがっています。
以下は、中出 阪蔵氏の紹介の引用(概略)です。
中出阪蔵(ナカデサカゾウ)は明治39年(1906)4月1日、射和郡下蛸路(現在の松阪市下蛸路町)に生まれました。小学校を卒業後、すぐに松阪の材木問屋に奉公に出されましたが、半年位した大正8年(1919)念願の上京を果たし、ヴァイオリン製作家の宮本金八に弟子入り、以来宮本金八の下でヴァイオリンやマンドリン、スチールギター、更にはギタローネといった特殊楽器を製作していました。転機となったのは昭和4年(1929)アンドレス・セゴビアの初来日の際、特別にセゴビア使用のギターのコピーを許されたことで(実際に採寸したのは宮本金八)、これをきっかけに宮本金八の指示によりギター製作を開始することになりました。
(中略)
ギター製作家としてその名が知られるにつれ、中出阪蔵の門をたたく者も増え、最盛期には15人もの弟子を抱えていたこともありました。中出門下生は30人を超え、黒澤常三郎・田崎守男・中村 篤・中山 昇・今井博水らが独立、稲葉征司・井田英夫ら現在も活躍する製作家がいます。
(中略)
生涯ギター職人であり続けた阪蔵氏は、同年87歳で亡くなるまでに数多くのギターを世に送り出しました。それらはギター製作技術の向上のみならず、楽器を手にしたギタリストも育て上げ、日本のギター界に多大な影響を与えました。
ということで、数は、ある程度でているが、一般には知名度の少ない製作者さんのようです。
さて、本体は、量産品ではない手工品ギターだけあって、使用材に贅沢なものが使われています。
トップは色はあめ色に近くなってきていますが、スプルース(マツ科トウヒ属の常緑針葉樹)と思われます。


ジャーマンスプルース見本
サイド&バックは、あにはからんだ(や)、ハカランダ(ブラジリアン・ローズウッド)に間違いありません。ワシントン条約で、商業目的の輸出入は禁止され、新規の輸入は全く行われていない、今となっては貴重な材。


特にバックのハカランダには流れるような柾目材が使用されています。
ネックはマホガニー、指板はどこまでも黒い黒檀(エボニー)、ブリッジとヘッドの付き板には柾目ハカランダが使用されており、いまだったら、ちょっとやそっとでは、手に入らない材料を惜しみなく使っています。
肝心の音色ですが、全体的に柔らかい音がしますが、その中に独特の音色が含まれており、違う個体を弾いた時にも、「ああ、中村 篤 さんの音だ」とすぐに分かる音がしました。
30年ぐらい寝かせて、どのような音になっているのか楽しみです。
もっと価値を認識して、大事にしてあげればよかった。
to be continued

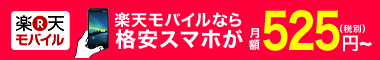




























 Line 6 FBV EXPRESS MKII
Line 6 FBV EXPRESS MKII




















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16dc6e10.8413a7cc.16dc6e11.9db2781e/?me_id=1303873&item_id=10005732&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frockonline%2Fcabinet%2Fproduct%2F05128721%2F60112_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)





 ニルス・シュナイダー さんのWEB より
ニルス・シュナイダー さんのWEB より








![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/12355484.9cd42a4e.12355485.0c2c77b8/?me_id=1230373&item_id=10190069&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshimamuragakki%2Fcabinet%2Fmt00979%2Fmt0097949.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
 Popumusicの創設者であるBruceZhang
Popumusicの創設者であるBruceZhang


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10117075&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem92000%2F91779.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0e59a13e.45f36395.0e59a13f.54ff69f6/?me_id=1206032&item_id=12787724&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F1456%2F4562314015430.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/108847df.7fe85978.108847e0.f657de4c/?me_id=1210933&item_id=11687735&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc281%2F140674.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/12ed66f2.33f1a9f7.12ed66f3.beb07e00/?me_id=1211264&item_id=10003432&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Farabasta%2Fcabinet%2F00213001%2Fblackd.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/198bf714.39b7d18c.198bf715.d95d0718/?me_id=1207956&item_id=10018710&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmusicfarm%2Fcabinet%2Fsyouhin01%2F03107501%2Fimg59306392.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10166329&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fset17500%2Fs17141.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10018694&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem23000%2Frt_22592_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11f49a82.475a31fd.11f49a83.6e32a4ee/?me_id=1200868&item_id=10097267&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchuya-online%2Fcabinet%2Fitem57000%2F56888.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
















