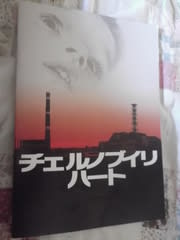今日も曇天。時折雪。
今朝もブルの置き土産。ざっと30センチくらいに積み上げられた氷の塊。
その上に、まるで粉砂糖のようにまぶされた粉雪が、うまく氷を隠してくれていました。
結局、このお土産の片付けから一日の作業が開始するのでございます。
ひどいときは、これで疲れ切り、もう何も出来ない状態になることもあります。
もっと若いといいけれど・・・。
年々年取り、次第に体力もなくなり、老人になったら、やはりここに住むことは至難の業となりそう。
さて、そんな冬の楽しみの一つは、暖かい部屋の中で、好きなビデオやDVDを観、傍らではコトコトとお鍋のいい香り・・・がしている事。
きのう、たまたまテレビを見ていたら、「白菜」のおいしい所はどこなのか放送されていました。

白菜の半分。

もっとも甘いのは、引っこ抜いた真ん中の部分。芯とつながっているので、そこが最も甘くなるそう。実際生で食べたら、ホントに「甘ーーい」
で、そこを早めにとって食べちゃった方が、あとあと、芯から他に栄養がまわるため、
外側も甘くなっていくんだそうよ。
「白菜」買ったら、今度からは、真ん中から食べて下さいね。
さて、その「白菜」を刻み、ほかの根菜や葉物野菜を刻み、キノコ類、しょうがやローリエ、塩こしょう、最後にハム(ベーコンでも良い)と水を加えたら、後はストーブにドーンとのせて、コトコト煮込むだけ。
(本当はコンソメをいれますが、入れなくてもハムと野菜から十分に出汁はとれます。)


我が家のストーブは便利。煮ることができます。経済的。
できあがった頃に、お好みでパスタを入れてもいいです。

私の好きなDVDの一つは、以前も書いた「アボンリーへの道」。
これは、「赤毛のアン」から派生した海外ドラマ。
だから、赤毛のアンに登場した人々も出て来ます。
主人公は、両親を亡くしたセーラという少女。
おばの家に引き取られて生活する、どこか赤毛のアンとも似た境遇。

主人公のおば「へティ」は準主役。職業は教師そして作家。


右の少女がセーラ。真ん中はおばのオリビア。左がおばのへティ。
この海外ドラマは、カナダで製作され、舞台はもちろんプリンスエドワード島。

「赤毛のアン」のリンドさんも、そのままの名前で出演。
リンドさんだけでなく、アンの育ての親のマリラ、アンの夫のギルバートさえも登場。
このドラマには、カントリー調の家、家具、洋服、雑貨がたくさん出てくるので、カントリーファンには楽しめます。

これが、ローズコテージ。そう、私が「ここあコテージ」と名付けた由来がここにありました。夏にはバラがいっぱい咲きます。

教会。長老派の教会という設定です。

幼児洗礼の場面。長老派の教会は幼児洗礼は認めていたっけ?

人々の足は馬車。こののち自動車も登場してきます。20世紀初頭のお話です。

家の中。

学校。

納屋。ここには牛や馬がいます。庭には鶏がいて、人々は乳と卵と肉を、これらから頂いています。
また、ジャガイモを中心に作付けし、海ではロブスターも獲れます。

街の雑貨店。

缶詰、洋服生地、洋服や帽子、新聞、野菜、くだもの、なんでも売られています。
電話はここで初めて付けられました。

島で唯一のホテル「ホワイトサンドホテル」。
ここには主にアメリカ人や、お金持ちが避暑に訪れます。
島の人々の雇用がここでもまかなわれます。
赤毛アンの映画でも出ています。
私の英語の勉強にもなっています。
しばし現実から抜け出たい時は、このDVDをよく観ています。
ここあでした。
今朝もブルの置き土産。ざっと30センチくらいに積み上げられた氷の塊。
その上に、まるで粉砂糖のようにまぶされた粉雪が、うまく氷を隠してくれていました。
結局、このお土産の片付けから一日の作業が開始するのでございます。
ひどいときは、これで疲れ切り、もう何も出来ない状態になることもあります。
もっと若いといいけれど・・・。
年々年取り、次第に体力もなくなり、老人になったら、やはりここに住むことは至難の業となりそう。
さて、そんな冬の楽しみの一つは、暖かい部屋の中で、好きなビデオやDVDを観、傍らではコトコトとお鍋のいい香り・・・がしている事。
きのう、たまたまテレビを見ていたら、「白菜」のおいしい所はどこなのか放送されていました。

白菜の半分。

もっとも甘いのは、引っこ抜いた真ん中の部分。芯とつながっているので、そこが最も甘くなるそう。実際生で食べたら、ホントに「甘ーーい」
で、そこを早めにとって食べちゃった方が、あとあと、芯から他に栄養がまわるため、
外側も甘くなっていくんだそうよ。
「白菜」買ったら、今度からは、真ん中から食べて下さいね。
さて、その「白菜」を刻み、ほかの根菜や葉物野菜を刻み、キノコ類、しょうがやローリエ、塩こしょう、最後にハム(ベーコンでも良い)と水を加えたら、後はストーブにドーンとのせて、コトコト煮込むだけ。
(本当はコンソメをいれますが、入れなくてもハムと野菜から十分に出汁はとれます。)


我が家のストーブは便利。煮ることができます。経済的。
できあがった頃に、お好みでパスタを入れてもいいです。

私の好きなDVDの一つは、以前も書いた「アボンリーへの道」。
これは、「赤毛のアン」から派生した海外ドラマ。
だから、赤毛のアンに登場した人々も出て来ます。
主人公は、両親を亡くしたセーラという少女。
おばの家に引き取られて生活する、どこか赤毛のアンとも似た境遇。

主人公のおば「へティ」は準主役。職業は教師そして作家。


右の少女がセーラ。真ん中はおばのオリビア。左がおばのへティ。
この海外ドラマは、カナダで製作され、舞台はもちろんプリンスエドワード島。

「赤毛のアン」のリンドさんも、そのままの名前で出演。
リンドさんだけでなく、アンの育ての親のマリラ、アンの夫のギルバートさえも登場。
このドラマには、カントリー調の家、家具、洋服、雑貨がたくさん出てくるので、カントリーファンには楽しめます。

これが、ローズコテージ。そう、私が「ここあコテージ」と名付けた由来がここにありました。夏にはバラがいっぱい咲きます。

教会。長老派の教会という設定です。

幼児洗礼の場面。長老派の教会は幼児洗礼は認めていたっけ?

人々の足は馬車。こののち自動車も登場してきます。20世紀初頭のお話です。

家の中。

学校。

納屋。ここには牛や馬がいます。庭には鶏がいて、人々は乳と卵と肉を、これらから頂いています。
また、ジャガイモを中心に作付けし、海ではロブスターも獲れます。

街の雑貨店。

缶詰、洋服生地、洋服や帽子、新聞、野菜、くだもの、なんでも売られています。
電話はここで初めて付けられました。

島で唯一のホテル「ホワイトサンドホテル」。
ここには主にアメリカ人や、お金持ちが避暑に訪れます。
島の人々の雇用がここでもまかなわれます。
赤毛アンの映画でも出ています。
私の英語の勉強にもなっています。
しばし現実から抜け出たい時は、このDVDをよく観ています。
ここあでした。