歪んだ検察・新聞こそ悪質 (上杉 隆ジャーナリスト)より
◇小沢一郎を無意味に巨人化する風潮◇
この四半世紀、永田町は結局、小沢一郎という一人の政治家を中心に回っている、そういっても過言ではない。
たしかに一時期、小沢に取って代わる名優の小泉純一郎という主役がステージに上がったこともあった。だが、それも所詮、5年間だけの話だ。
小沢が自民党幹事長として権力の絶頂にあった時代はもう20年も前の話である。1991年、竹下後継を決める「小沢面談」は、自民党のみならず、国家権力がこの一人の政治家に集中していることを印象付けた。
そうしたかたちでの権力行使が可能だったのは、なにも小沢一人の力によるものばかりではない。「小沢史観」とも呼ぶべき思考停止の権力報道が、記者クラブメディアを中心に拡散し、日本中に広まった結果でもある。実像以上にその存在を膨らませ、良きも悪きも、永田町で起こる事柄はすべて小沢一郎に起因する、という単純化した物の見方が横行したのは確かだ。
だが、時代は変わった。政治を取り巻く環境は大きく変わり、小沢が権勢を振るったころの永田町の状況を知っている者の多くは、権力を失ったか、引退したか、あるいは鬼籍に入っている。
田中角栄、金丸信、竹下登、安倍晋太郎、宮澤喜一、渡辺美智雄などの派閥の領袖クラスはいずれも鬼籍に入った。ブッシュ米大統領、サッチャー英首相、ゴルバチョフ・ソ連書記長など往時の世界のリーダーたちも一線から退いている。キューバのフィデル・カストロ議長、リビアのカダフィ大佐などの独裁者もかつての権力を維持していない。こうしてみると、小沢一郎だけが四半世紀のあいだ、政治権力の頂点にいることは奇跡的ですらある。
政治のプレイヤーが代わったように、そのシステムと風土も大きく変更された。政治資金規正法などの法律は何度も改正され、より厳格化された。インターネットなどの発達により、政治家の姿を国民に伝えるメディア環境も劇的に変化した。そうしたなか、はたして小沢一郎だけが不変でいられるのだろうか。
「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない」
小沢が好んで引用するイタリア映画『山猫』の台詞。まさしく自らのめざす「保守」でありつづけるために、小沢は変化しつづけてきたのである。
だが、そうした変化に付いてこられない勢力が日本には依然として存在する。古い考えをもった政治家たちと、検察庁を筆頭とする霞が関官僚の一部、そして記者クラブメディアである。とくに、検察と記者クラブメディアによるコンプレックス(複合体)は、「小沢一郎」という得体の知れない政治家の虚像を勝手につくり、それに勝手に怯え、自らの恐怖心を隠すために、戦略性の乏しい攻撃を仕掛けていったのだ。小沢一郎に対するこの種の見方は、永田町に横行している。
ところが、時代は変わり、政治も変わったのだ。小沢に対するその種の一面的な見方が通用しないことは、昨今の検察捜査や発表報道、そして政権交代で暴露されはじめている。
無意味に小沢一郎を巨人化する風潮は、永田町で実際に起きている現実を覆い隠してしまっている。国民が本来知りたい情報は、無意味に巨人化された政治家のストーリーではない。
所詮、政治は権力闘争である。検察と小沢という政治権力同士の戦いの構図を、記者クラブメディアの参戦という不可欠の要素を入れながら、検証してみよう。
田中角栄の秘蔵っ子として政界の中央に躍り出た小沢一郎。彼の検察との長い闘争はその時代に遡る。政治の恩師である田中がロッキード事件で逮捕・収監、その後に起訴されて刑事被告人の立場になっても、小沢は一貫して田中に寄り添いつづけた。一度も欠かすことなく、傍聴のために裁判所に通い詰めてもいる。
小沢のその行為を、恩師への義理立てだけだと見るのは早計にすぎる。学生時代、司法の道をめざした小沢は、政治とカネをめぐる政界の象徴的な事件をつぶさに追うことで、自らの法知識を補っていくことになった。それが、親戚関係にある金丸信の逮捕によって、小沢が、検察との対決の前面に出る1つのきっかけになったことは想像に難くない。
当時、政治資金規正法での捜査が近づいていた金丸の対検察戦略は小沢に一任されていた。小沢は、政治的なダメージは融和策で回避できると判断し、金丸を自民党から離党させ、上申書を提出、検察の判断を待った。しかし、それでも検察の動きはやまず、さらに金丸の議員辞職でもって譲歩の姿勢を見せたのだ。
ところが、検察は金丸を逮捕し、上申書と罰金20万円の支払いを求めた。この経験から小沢は、検察は絶対に話の通じない相手だと判断することになったのだ。今回、任意での事情聴取に小沢がなかなか応じなかった根底には、こうした過去の検察との「戦闘」の記憶があるのだろう。
さらに昨年3月からの長い「戦闘」も、小沢の姿勢をさらに硬化させる要素になった。
3月3日、政治資金規正法違反容疑で大久保隆規公設秘書が逮捕された。じつは当日の朝、東京地検から突然の呼び出しを受けた大久保は、小沢に電話してこう語っている。
「地検から電話がありまして、話を聞きたいということなんですが。行ってきますが、いったい、何でしょうね」
それに対して小沢は「うん、何だろうな」と返して、戻ったら報告してくれ、と伝えて電話を切っている。
だが、その日、大久保が東京地検から戻ることはなかった。なぜなら、そのまま身柄を取られたからだ。
小沢はその翌日の3月4日からマスコミの前に姿を現した。新聞・テレビなどの報道では、小沢は「雲隠れ」していると盛んに報じられているが、小沢はこの日以来、一貫して週1回の記者会見に姿を現し、あらゆるジャーナリストたちの質問に答えている。さらに珍しいことだが、ぶら下がりでの会見も数回開いている。
同じ西松建設から献金を受けた自民党の国会議員は9人いる。民主党にも一人いる。だが、小沢以外の誰一人、記者会見を開いて説明を行なった者はいない。それと比べれば、マスコミに対して最も説明を果たしている、もしくは、果たそうとしているのは小沢といえる。
記者クラブメディアは、このことをいっさい報じていない。そこには小沢と記者クラブメディアの長年の「闘争」があるからだ。これはのちに記す。
さらに小沢事務所には、大久保の逮捕に至るまで、赤坂の個人事務所や岩手水沢の地元事務所に捜査が入り、すべての関係文書を押収されている。その結果、小沢事務所の秘書の言葉を借りれば、次のような心境になった。
「大久保さんの逮捕で、法の裁きも受けた。小沢先生自身も、銀行や口座名まで検察側に示し、捜査に協力してきた。反発などしていない。協力しているところは協力しているのだ」
さらにその後、政権交代が成った。今度は与党として、検察に対して反撃できる状況が整った。検察は完全な司法機関ではない。独立性は担保されているものの、政府に組み込まれた行政機関である。よって、政府・与党として民主党政権は、いかなる方法でも反撃のできるチャンスはあるのだ。ところが、小沢は人事その他でいっさい報復に向かわなかった。それまでの検察からの攻撃を水に流したのである。
ところが、小沢の「譲歩」に対して、検察のほうが容赦しなかった。昨年末、小沢元秘書の石川知裕衆議院議員の事情聴取を繰り返し、強制捜査の末、国会開幕直前に逮捕したのである。さらにその際、大久保、池田(光智)という小沢の現職秘書も逮捕している。次に検察の狙うターゲットがもちろん小沢本人であるということは想像に難くない。つまり、小沢サイドからしてみれば、せっかく「休戦」の意思を示したのに、それを無視して、執拗に挑戦してきたのは検察側のほうだ――ということになるのである。
いまや、小沢事務所は宗教的な色彩を帯びている。しかも、教祖のみならず、信徒までもが迫害されている「教団」の雰囲気だ。それは理屈と常識だけでは説明がつかない。これまでの小沢とその秘書たち、彼らの意識の流れを取材で追うことによって初めて気づく感情的な権力の「闘争」そのものなのである。
秘書たちは「殉教」すら辞さない覚悟でいる。小沢への忠誠心というよりも、小沢事務所や小沢後援会への忠誠心かもしれない。また、地元には、検察という国家権力によって小沢一郎総理の夢が潰えたのだ、と信じて疑わない熱狂的な「信者」たちが控えている。
これこそが、小沢事件の底流に流れる小沢サイドの強硬姿勢の答えである。
◇記者クラブのタブーに触れた幹事長◇
じつは、ここにもう一つの要素が絡まっていく。先述した記者クラブメディアの存在だ。
日本にしか存在しない記者クラブ制度は、世界のジャーナリズムの「恥」といっても過言ではない。同業者であるジャーナリストの公権力へのアクセス権を同業者が封じるという、世界でも類をみない奇妙なシステムが長年存続し、世界中から批判の対象になっている。
〈土地代4億円「小沢氏が不記載了承」石川容疑者供述〉(『読売新聞』2010年1月20日夕刊)
一面トップにこのような見出しが躍れば、誰もが信じるだろう。だが、こうした記事は海外のジャーナリズムではルール違反のものだ。ニューヨーク・タイムズ東京支局長のマーティン・ファクラーはこう語っている。
「私は、記者クラブのことを『一世紀続く、カルテルに似た最も強力な利益集団の1つ』と書きました。(中略)そのことを実感したのが、西松建設事件を巡る報道です。記者クラブによるほとんどの報道が検察のリーク情報に乗るだけで、検察の立場とは明確に一線を画し、(中略)独自の取材、分析を行う記事はなかったように思います」(『SAPIO』1月4日号、筆者インタビュー記事より)
たしかに、小沢一郎も公権力ではあるが、検察もまた公権力である。双方の言い分を公平に扱って、対立する意見を取材し、読者や視聴者に両論を提示、各々の判断に委ねることこそ、ジャーナリズムに要請されている役割である。それは、公正な記者会見の舞台でのみ達成される。
だが、日本では、すべての取材現場において、記者クラブが公権力と一体化し、手を結んで国民の知る権利を阻害している。
結局、『読売新聞』は翌日の朝刊でこの記事を修正している。だが、いまだに公権力であるはずの検察からの情報だとは認めず、「関係者」報道を続けている。
世界に通用する公平な記者会見を求めつづけている政治家が、じつは日本にもいる。それが小沢一郎だ。昨年12月の記者会見で筆者は小沢に聞いた。
「平野官房長官などが約束を反故にするなか、小沢幹事長が一貫して約束を守り、フリー、雑誌、海外、ネットメディアの記者に会見を開放しつづけていることに感謝します。そこで質問ですが、幹事長はいつから会見を開放しているのでしょうか。そしてなぜそうした考えに至ったのでしょうか?」
「(自由党、新進党はもちろん)自民党の幹事長時代からすべての記者さんに公平にしなくてはならないという意識で、(会見のオープン化を)指示しました。時期については自民党に聞いてもらわなくてはなりませんが、まさか、私が自民党に行くわけにもいかないので(笑)」
小沢が記者会見を開き、日本独特の懇談やぶら下がり会見を廃止しようと試みたのは、たしかに自民党幹事長時代のことだった。一部の新聞・テレビの記者しか参加できないクローズドな懇談ではなく、海外特派員、フリーランス、雑誌の記者が入れるように定例記者会見の設置を、自民党の記者クラブに提案したのだ。
ところが、それは記者クラブメディアからみれば、既得権に触れるタブーであった。健全な記者会見の開催を呼び掛けた小沢に対して、翌日の新聞・テレビはすべて同じ記事を書いて逆に批判したのだ。
〈小沢幹事長、懇談会見の中止を通告。「記者会見はサービス」とも〉
小沢が、こうした「官報複合体」の虎の尾を踏んだため、その後20年以上にわたって、小沢史観ともいうべき小沢に批判的な報道があふれることになった。そう考えるのは穿ちすぎだろうか。
「小沢はなんとしても捕るべきだ。多少の犠牲を払ってでも、小沢をつぶすことこそ日本のためになる」
これは、検察幹部との懇談で、ある新聞記者が検事に語った言葉だ。情報源は「関係者」としておく。はたして、これで民主主義国家といえるだろうか。やはり「官報複合体」こそ、政治を歪め、国を滅ぼすものではないか。
◇ネットメディアが政治を動かす時代へ◇
しかしいま、記者会見における新しいメディアがその状況を打破しようとしている。
ツイッターやユーチューブなどの登場は過去15年間、筆者が永田町で体験し、眺めてきたどの事象よりも衝撃的なものだ。この新しいメディアは、記者クラブ制度を根底から崩壊させ、施政者と国民の関係をフラット化し、既存の社会システムの大転換をもたらしはじめている。
米国のオバマ大統領陣営の戦略を見ても分かるとおり、これら新しいネットメディアは既存メディアを飛び越え、未加工の情報を直接、国民に伝える役割を果たしている。そこに古いメディアの介在する余地はない。政治力などではなく、メディア環境が政治を動かしている。
記者クラブメディアには冷たい小沢一郎だが、じつは彼ほどネットメディアに理解のある政治家は稀である。ニコニコ動画の黎明期、その番組に最初に登場した大物政治家は誰であろう小沢一郎である。記者会見の席上、情報を加工して伝える新聞やテレビなどのオールドメディアに対する態度と180度打って変わり、やさしく語り掛けるのは、決まってフリーランスやネットの記者たちに対してだ。
日本の政治の向かう方向は明確である。直接、国民に語り掛ける術を知った政治家と、そうでない政治家に峻別されるだろう。いまそれは、記者クラブなどのオールドメディアと、ネットなどのニューメディアの代理戦争の様相すら呈している。
日本の政治システムの未来図のヒントは海外にある。世界中で、アンシャンレジーム(旧体制)はいかなる分野においても滅びゆこうとしている。日本も例外ではいられない。もはや属人的な要素で動く政治は終焉を迎えようとしている。変わることのできる政治家、そうでない政治家、それが新しい日本政治の分水嶺になるだろう。
そうした意味で、小沢一郎ははたして『山猫』の一節のように変わることができるだろうか。それが彼と民主党の運命を決するのかもしれない。(文中敬称略)
◇小沢一郎を無意味に巨人化する風潮◇
この四半世紀、永田町は結局、小沢一郎という一人の政治家を中心に回っている、そういっても過言ではない。
たしかに一時期、小沢に取って代わる名優の小泉純一郎という主役がステージに上がったこともあった。だが、それも所詮、5年間だけの話だ。
小沢が自民党幹事長として権力の絶頂にあった時代はもう20年も前の話である。1991年、竹下後継を決める「小沢面談」は、自民党のみならず、国家権力がこの一人の政治家に集中していることを印象付けた。
そうしたかたちでの権力行使が可能だったのは、なにも小沢一人の力によるものばかりではない。「小沢史観」とも呼ぶべき思考停止の権力報道が、記者クラブメディアを中心に拡散し、日本中に広まった結果でもある。実像以上にその存在を膨らませ、良きも悪きも、永田町で起こる事柄はすべて小沢一郎に起因する、という単純化した物の見方が横行したのは確かだ。
だが、時代は変わった。政治を取り巻く環境は大きく変わり、小沢が権勢を振るったころの永田町の状況を知っている者の多くは、権力を失ったか、引退したか、あるいは鬼籍に入っている。
田中角栄、金丸信、竹下登、安倍晋太郎、宮澤喜一、渡辺美智雄などの派閥の領袖クラスはいずれも鬼籍に入った。ブッシュ米大統領、サッチャー英首相、ゴルバチョフ・ソ連書記長など往時の世界のリーダーたちも一線から退いている。キューバのフィデル・カストロ議長、リビアのカダフィ大佐などの独裁者もかつての権力を維持していない。こうしてみると、小沢一郎だけが四半世紀のあいだ、政治権力の頂点にいることは奇跡的ですらある。
政治のプレイヤーが代わったように、そのシステムと風土も大きく変更された。政治資金規正法などの法律は何度も改正され、より厳格化された。インターネットなどの発達により、政治家の姿を国民に伝えるメディア環境も劇的に変化した。そうしたなか、はたして小沢一郎だけが不変でいられるのだろうか。
「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない」
小沢が好んで引用するイタリア映画『山猫』の台詞。まさしく自らのめざす「保守」でありつづけるために、小沢は変化しつづけてきたのである。
だが、そうした変化に付いてこられない勢力が日本には依然として存在する。古い考えをもった政治家たちと、検察庁を筆頭とする霞が関官僚の一部、そして記者クラブメディアである。とくに、検察と記者クラブメディアによるコンプレックス(複合体)は、「小沢一郎」という得体の知れない政治家の虚像を勝手につくり、それに勝手に怯え、自らの恐怖心を隠すために、戦略性の乏しい攻撃を仕掛けていったのだ。小沢一郎に対するこの種の見方は、永田町に横行している。
ところが、時代は変わり、政治も変わったのだ。小沢に対するその種の一面的な見方が通用しないことは、昨今の検察捜査や発表報道、そして政権交代で暴露されはじめている。
無意味に小沢一郎を巨人化する風潮は、永田町で実際に起きている現実を覆い隠してしまっている。国民が本来知りたい情報は、無意味に巨人化された政治家のストーリーではない。
所詮、政治は権力闘争である。検察と小沢という政治権力同士の戦いの構図を、記者クラブメディアの参戦という不可欠の要素を入れながら、検証してみよう。
田中角栄の秘蔵っ子として政界の中央に躍り出た小沢一郎。彼の検察との長い闘争はその時代に遡る。政治の恩師である田中がロッキード事件で逮捕・収監、その後に起訴されて刑事被告人の立場になっても、小沢は一貫して田中に寄り添いつづけた。一度も欠かすことなく、傍聴のために裁判所に通い詰めてもいる。
小沢のその行為を、恩師への義理立てだけだと見るのは早計にすぎる。学生時代、司法の道をめざした小沢は、政治とカネをめぐる政界の象徴的な事件をつぶさに追うことで、自らの法知識を補っていくことになった。それが、親戚関係にある金丸信の逮捕によって、小沢が、検察との対決の前面に出る1つのきっかけになったことは想像に難くない。
当時、政治資金規正法での捜査が近づいていた金丸の対検察戦略は小沢に一任されていた。小沢は、政治的なダメージは融和策で回避できると判断し、金丸を自民党から離党させ、上申書を提出、検察の判断を待った。しかし、それでも検察の動きはやまず、さらに金丸の議員辞職でもって譲歩の姿勢を見せたのだ。
ところが、検察は金丸を逮捕し、上申書と罰金20万円の支払いを求めた。この経験から小沢は、検察は絶対に話の通じない相手だと判断することになったのだ。今回、任意での事情聴取に小沢がなかなか応じなかった根底には、こうした過去の検察との「戦闘」の記憶があるのだろう。
さらに昨年3月からの長い「戦闘」も、小沢の姿勢をさらに硬化させる要素になった。
3月3日、政治資金規正法違反容疑で大久保隆規公設秘書が逮捕された。じつは当日の朝、東京地検から突然の呼び出しを受けた大久保は、小沢に電話してこう語っている。
「地検から電話がありまして、話を聞きたいということなんですが。行ってきますが、いったい、何でしょうね」
それに対して小沢は「うん、何だろうな」と返して、戻ったら報告してくれ、と伝えて電話を切っている。
だが、その日、大久保が東京地検から戻ることはなかった。なぜなら、そのまま身柄を取られたからだ。
小沢はその翌日の3月4日からマスコミの前に姿を現した。新聞・テレビなどの報道では、小沢は「雲隠れ」していると盛んに報じられているが、小沢はこの日以来、一貫して週1回の記者会見に姿を現し、あらゆるジャーナリストたちの質問に答えている。さらに珍しいことだが、ぶら下がりでの会見も数回開いている。
同じ西松建設から献金を受けた自民党の国会議員は9人いる。民主党にも一人いる。だが、小沢以外の誰一人、記者会見を開いて説明を行なった者はいない。それと比べれば、マスコミに対して最も説明を果たしている、もしくは、果たそうとしているのは小沢といえる。
記者クラブメディアは、このことをいっさい報じていない。そこには小沢と記者クラブメディアの長年の「闘争」があるからだ。これはのちに記す。
さらに小沢事務所には、大久保の逮捕に至るまで、赤坂の個人事務所や岩手水沢の地元事務所に捜査が入り、すべての関係文書を押収されている。その結果、小沢事務所の秘書の言葉を借りれば、次のような心境になった。
「大久保さんの逮捕で、法の裁きも受けた。小沢先生自身も、銀行や口座名まで検察側に示し、捜査に協力してきた。反発などしていない。協力しているところは協力しているのだ」
さらにその後、政権交代が成った。今度は与党として、検察に対して反撃できる状況が整った。検察は完全な司法機関ではない。独立性は担保されているものの、政府に組み込まれた行政機関である。よって、政府・与党として民主党政権は、いかなる方法でも反撃のできるチャンスはあるのだ。ところが、小沢は人事その他でいっさい報復に向かわなかった。それまでの検察からの攻撃を水に流したのである。
ところが、小沢の「譲歩」に対して、検察のほうが容赦しなかった。昨年末、小沢元秘書の石川知裕衆議院議員の事情聴取を繰り返し、強制捜査の末、国会開幕直前に逮捕したのである。さらにその際、大久保、池田(光智)という小沢の現職秘書も逮捕している。次に検察の狙うターゲットがもちろん小沢本人であるということは想像に難くない。つまり、小沢サイドからしてみれば、せっかく「休戦」の意思を示したのに、それを無視して、執拗に挑戦してきたのは検察側のほうだ――ということになるのである。
いまや、小沢事務所は宗教的な色彩を帯びている。しかも、教祖のみならず、信徒までもが迫害されている「教団」の雰囲気だ。それは理屈と常識だけでは説明がつかない。これまでの小沢とその秘書たち、彼らの意識の流れを取材で追うことによって初めて気づく感情的な権力の「闘争」そのものなのである。
秘書たちは「殉教」すら辞さない覚悟でいる。小沢への忠誠心というよりも、小沢事務所や小沢後援会への忠誠心かもしれない。また、地元には、検察という国家権力によって小沢一郎総理の夢が潰えたのだ、と信じて疑わない熱狂的な「信者」たちが控えている。
これこそが、小沢事件の底流に流れる小沢サイドの強硬姿勢の答えである。
◇記者クラブのタブーに触れた幹事長◇
じつは、ここにもう一つの要素が絡まっていく。先述した記者クラブメディアの存在だ。
日本にしか存在しない記者クラブ制度は、世界のジャーナリズムの「恥」といっても過言ではない。同業者であるジャーナリストの公権力へのアクセス権を同業者が封じるという、世界でも類をみない奇妙なシステムが長年存続し、世界中から批判の対象になっている。
〈土地代4億円「小沢氏が不記載了承」石川容疑者供述〉(『読売新聞』2010年1月20日夕刊)
一面トップにこのような見出しが躍れば、誰もが信じるだろう。だが、こうした記事は海外のジャーナリズムではルール違反のものだ。ニューヨーク・タイムズ東京支局長のマーティン・ファクラーはこう語っている。
「私は、記者クラブのことを『一世紀続く、カルテルに似た最も強力な利益集団の1つ』と書きました。(中略)そのことを実感したのが、西松建設事件を巡る報道です。記者クラブによるほとんどの報道が検察のリーク情報に乗るだけで、検察の立場とは明確に一線を画し、(中略)独自の取材、分析を行う記事はなかったように思います」(『SAPIO』1月4日号、筆者インタビュー記事より)
たしかに、小沢一郎も公権力ではあるが、検察もまた公権力である。双方の言い分を公平に扱って、対立する意見を取材し、読者や視聴者に両論を提示、各々の判断に委ねることこそ、ジャーナリズムに要請されている役割である。それは、公正な記者会見の舞台でのみ達成される。
だが、日本では、すべての取材現場において、記者クラブが公権力と一体化し、手を結んで国民の知る権利を阻害している。
結局、『読売新聞』は翌日の朝刊でこの記事を修正している。だが、いまだに公権力であるはずの検察からの情報だとは認めず、「関係者」報道を続けている。
世界に通用する公平な記者会見を求めつづけている政治家が、じつは日本にもいる。それが小沢一郎だ。昨年12月の記者会見で筆者は小沢に聞いた。
「平野官房長官などが約束を反故にするなか、小沢幹事長が一貫して約束を守り、フリー、雑誌、海外、ネットメディアの記者に会見を開放しつづけていることに感謝します。そこで質問ですが、幹事長はいつから会見を開放しているのでしょうか。そしてなぜそうした考えに至ったのでしょうか?」
「(自由党、新進党はもちろん)自民党の幹事長時代からすべての記者さんに公平にしなくてはならないという意識で、(会見のオープン化を)指示しました。時期については自民党に聞いてもらわなくてはなりませんが、まさか、私が自民党に行くわけにもいかないので(笑)」
小沢が記者会見を開き、日本独特の懇談やぶら下がり会見を廃止しようと試みたのは、たしかに自民党幹事長時代のことだった。一部の新聞・テレビの記者しか参加できないクローズドな懇談ではなく、海外特派員、フリーランス、雑誌の記者が入れるように定例記者会見の設置を、自民党の記者クラブに提案したのだ。
ところが、それは記者クラブメディアからみれば、既得権に触れるタブーであった。健全な記者会見の開催を呼び掛けた小沢に対して、翌日の新聞・テレビはすべて同じ記事を書いて逆に批判したのだ。
〈小沢幹事長、懇談会見の中止を通告。「記者会見はサービス」とも〉
小沢が、こうした「官報複合体」の虎の尾を踏んだため、その後20年以上にわたって、小沢史観ともいうべき小沢に批判的な報道があふれることになった。そう考えるのは穿ちすぎだろうか。
「小沢はなんとしても捕るべきだ。多少の犠牲を払ってでも、小沢をつぶすことこそ日本のためになる」
これは、検察幹部との懇談で、ある新聞記者が検事に語った言葉だ。情報源は「関係者」としておく。はたして、これで民主主義国家といえるだろうか。やはり「官報複合体」こそ、政治を歪め、国を滅ぼすものではないか。
◇ネットメディアが政治を動かす時代へ◇
しかしいま、記者会見における新しいメディアがその状況を打破しようとしている。
ツイッターやユーチューブなどの登場は過去15年間、筆者が永田町で体験し、眺めてきたどの事象よりも衝撃的なものだ。この新しいメディアは、記者クラブ制度を根底から崩壊させ、施政者と国民の関係をフラット化し、既存の社会システムの大転換をもたらしはじめている。
米国のオバマ大統領陣営の戦略を見ても分かるとおり、これら新しいネットメディアは既存メディアを飛び越え、未加工の情報を直接、国民に伝える役割を果たしている。そこに古いメディアの介在する余地はない。政治力などではなく、メディア環境が政治を動かしている。
記者クラブメディアには冷たい小沢一郎だが、じつは彼ほどネットメディアに理解のある政治家は稀である。ニコニコ動画の黎明期、その番組に最初に登場した大物政治家は誰であろう小沢一郎である。記者会見の席上、情報を加工して伝える新聞やテレビなどのオールドメディアに対する態度と180度打って変わり、やさしく語り掛けるのは、決まってフリーランスやネットの記者たちに対してだ。
日本の政治の向かう方向は明確である。直接、国民に語り掛ける術を知った政治家と、そうでない政治家に峻別されるだろう。いまそれは、記者クラブなどのオールドメディアと、ネットなどのニューメディアの代理戦争の様相すら呈している。
日本の政治システムの未来図のヒントは海外にある。世界中で、アンシャンレジーム(旧体制)はいかなる分野においても滅びゆこうとしている。日本も例外ではいられない。もはや属人的な要素で動く政治は終焉を迎えようとしている。変わることのできる政治家、そうでない政治家、それが新しい日本政治の分水嶺になるだろう。
そうした意味で、小沢一郎ははたして『山猫』の一節のように変わることができるだろうか。それが彼と民主党の運命を決するのかもしれない。(文中敬称略)











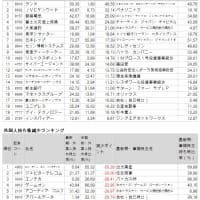





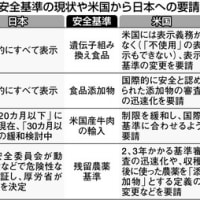
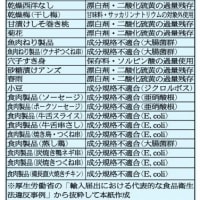

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます