
7月22日の日蝕(日食)観測の拠点となったトカラ列島の悪石島を調べてみると、とても興味深い文化があることを知りました。
トカラ列島については日本書紀にも記載があり、また平家の一門が喜界島に流されたり、広く落人伝説が残っているところでもあるようです。
悪という名前がついたのは、南西諸島に落ち伸びた平家の落人が、追っ手が来ないように名付けたという説もあるようです。
また、非常に南方系の仮面と衣装をまとった人物が広場で踊る「ボゼ」というお祭りがあることも知りました。
このお祭りをあつかった2008年8月16日付産経新聞の記事を一部紹介します。
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080816/sty0808161929004-n1.htm
***

仮面神ボゼが大暴れ トカラで奇祭
2008.8.16
写真・・ 赤土のついた棒で観光客や子供たちを追いかけるボゼ=16日午後、鹿児島県十島村の悪石島(古厩正樹撮影)
トカラ列島(鹿児島県十島村)の悪石島(あくせきじま)で16日、古くから伝わる奇祭、ボゼ祭りが行われた。
ボゼ祭りは、毎年旧暦の7月16日に行われるお盆の行事。ヤシ科の植物「ビロウ」の葉で身を包み、赤土と墨で塗られた面を着けた仮面神ボゼが現れ、島民や観光客を追いかけ始めると、辺りは歓声と悲鳴に包まれた。
ボゼが持つ棒に塗られた赤土を付けられると、悪魔ばらいのご利益があり、女性は子宝に恵まれるとされている。
***
記事の写真を見て、あまりのプリミティブさ、力強さに思わずはっとしてしまいました。
秋田の“なまはげ”に似てはいますが、顔のつくりが独特です。
日本でこのような仮面衣装は珍しいと思われ、悪石島がこのような南方系の文化がきちんと継承されている島であると知り、驚きました。

wikipediaによると「ボゼ」はこのように説明されています。
***
ボゼは鹿児島トカラ列島の悪石島に伝わる来訪神行事で、鹿児島県の無形文化財。
ボゼは盆の終わりに現れるとされる仮面装束で、その出現理由には諸説あるが、盆行事の幕を引くことで、人々を死霊臭の漂う盆から新たな生の世界へ蘇らせる役目を持つと指摘する研究者もいる。
また、盆時期には先祖の霊とともに悪霊も現世にやって来るので、その悪霊を追い払うものとする説もある。
盆の最終日翌日にあたる旧暦7月16日に、若者が赤土と墨で塗られた異形の面を被り、ビロウの葉の腰蓑を巻き、手首や足にシュロの皮をあててボゼに扮し、手にはボゼマラという長い棒を持つ。
午後に島内の聖地とされるテラ(墓地に隣接する広場)を出発した3体のボゼは、島の古老の呼び出しと太鼓の音に導かれ、島民が盆踊りに集まっている公民館の前の広場を訪れる。
主に女子供を追い回し、子供達は異様な姿に悲鳴をあげて逃げ惑い、辺りは笑い声と叫び声につつまれ騒然となる。
あまりの恐怖に泣き出す子供すらいることもある。
ボゼはボゼマラを持ったまま人々に迫り、その先端についた赤い泥水を擦りつける。
こうすることで悪霊祓いの利益があり、女性は子宝に恵まれるという。
こうした騒ぎが10~15分続いた後、太鼓の音が六調のリズムに変わると、ボゼが広場の中央に集まり踊り始める。
そして再度の太鼓の合図で再びボゼたちは子供たちを追い回しながら、その場を走り去る。
ボゼがテラへと戻って来た後、顔を覆っていた面はそこで跡形もなく壊される。
一方で残された公民館では、悪霊を祓われた人々が安堵と笑いに満ち、酒や料理を楽しみながら夜が更けてゆく。
稲垣尚友が著した『十島村誌』によれば、ボゼはヒチゲーと呼ばれる冬の節替りの夜に登場する仮面を被った神で、トカラの各島に現れたとされており、その名残が悪石島にのみ残ったとされる。
現在は悪石島の伝統行事として旧暦7月16日のお盆最終日翌日に登場する。
また、島の盆踊りは鹿児島県指定の無形民俗文化財。
創作におけるボゼ
水木しげる『ゲゲゲの鬼太郎』
「鬼太郎国盗り物語」(角川文庫『鬼太郎国盗り物語』などに収録)に登場。本作では沖縄県の妖怪神とされる。
***
写真 上・中はボゼ(産経新聞社より)
写真 下は、なまはげ
 wiki「まれびと」より
wiki「まれびと」より まれびと、マレビト(稀人・客人)は、時を定めて他界から来訪する霊的もしくは神的存在を指す折口学の用語。
折口信夫の思想体系を考える上でもっとも重要な鍵概念の一つであり、日本人の信仰・他界観念を探るための手がかりとして民俗学上重視される。
沖縄におけるフィールド・ワークが、まれびと概念の発想の契機となったらしい。
来訪神のまれびとは神を迎える祭などの際に、立てられた柱状の物体(髯籠・山車など)の依り代に降臨するとされた。
その来たる所は海の彼方(沖縄のニライカナイに当たる)、後に山岳信仰も影響し山の上・天から来る(天孫降臨)ものと移り変わったという。
 wiki「トカラ列島・歴史」 より
wiki「トカラ列島・歴史」 より 地名の由来については諸説あるものの、奄美諸島から沖縄諸島にかけてで「沖の海原」を指す「トハラ」から転訛したという説が有力。
『日本書紀』には「吐火羅国」とある。
699年(文武天皇3年)7月19日に、多褹、夜久、菴美、度感の人が物を貢いだことが、『続日本紀』に記されている(それぞれ種子島、屋久島、奄美大島、トカラにあたる)。
同書によればこれが度感(徳之島との説もある)が日本と通じた始まりであった。
 wiki「鬼界ヶ島」より
wiki「鬼界ヶ島」より 鬼界ヶ島(きかいがしま)とは、1177年の鹿ケ谷の陰謀により、俊寛、平康頼、藤原成経が流罪にされた島。薩摩国に属す。
『平家物語』によると島の様子は次の通りである。
舟はめったに通わず、人も希である。住民は色黒で、話す言葉も理解できず、男は烏帽子をかぶらず、女は髪をさげない。農夫はおらず穀物の類はなく、衣料品もない。
島の中には高い山があり、常時火が燃えおり、硫黄がたくさんあるのでこの島を硫黄島ともいう。
翌1178年に康頼、成経は赦免され京に帰るが、俊寛のみは赦されず、ひとり島に残され悲嘆のうちに死んだ。
鬼界ヶ島の現在の場所ははっきりしないが、薩南諸島の以下の島のいずれかと考えられている。
硫黄島 - 1995年5月に建てられた俊寛の銅像がある。火山の硫黄によって海が黄色に染まっていることから「黄海ヶ島」と名付けられたとの説がある。
•
喜界島 - 俊寛の墓と銅像がある。墓を調査した人類学者の鈴木尚によると、出土した骨は面長の貴族型の頭骨で、島外の相当身分の高い人物であると推測された。
•
伊王島 - 俊寛の墓がある。
 wiki「平家の落人伝説より・鹿児島地方」より
wiki「平家の落人伝説より・鹿児島地方」より •鹿児島県鹿児島郡三島村
平経正、平業盛らのほか、30あまりの史跡があるとされる。
鹿児島県大島郡(奄美諸島)
平家一門の平資盛が、壇ノ浦の戦いから落ち延びて約3年間喜界島に潜伏し、弟の平有盛、いとこの平行盛と合流し、ともに奄美大島に来訪したという。2005年に平家来島800年記念祭が行われた。
喜界町志戸桶(喜界島)、奄美諸島に到着した平家が最初に築いたと言われる七城跡がある。
喜界町早町、源氏警戒のため築いた城跡がある、平家森と呼ばれている。
奄美市名瀬浦上(奄美大島)、有盛を祀った平有盛神社がある、有盛が築いた浦上城跡と言われている。
瀬戸内町諸鈍(加計呂麻島)、資盛を祀った大屯(おおちょん)神社がある。
龍郷町戸口(奄美大島)、行盛が築いた戸口城跡がある。現地には行盛を祀った平行盛神社もあるが、城跡とは離れている。
龍郷町今井崎(奄美大島)、行盛により今井権田大夫が源氏警戒のため配された、今井権現が建っている。
奄美市笠利町蒲生崎(奄美大島)、有盛により蒲生佐衛門が源氏警戒のため配された。
沖縄県宮古島狩俣 落武者の物という古刀など遺品が伝わる。また平良という地名は平家の姓に由来するものという。












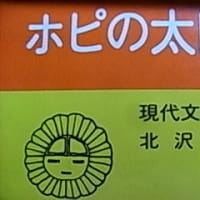

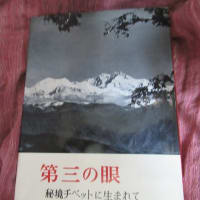







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます