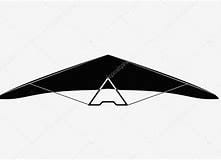前回では、ハンググライダーのコントロールバーがいかにスゴイ発明だったかをご紹介いたしました。
コントロールバーの役目は…。
・機体を持ち上げ、姿勢を維持できるとにより、テイクオフを可能とする。
・ワイヤー等を張ることにより、翼の強度を上げる
・着陸時にフレアーの動作を可能とさせ、足だけで降りることが出来る。
・機体の操縦を可能とさせる。
と、いくつもの役割を兼ねていることをご説明いたしました。
実は、もう一つ重要な仕事もコントロールバーはしているので、今回はそれをご説明いたします!
まず、飛行機はもちろん、自動車などの乗り物には、必ず操舵感覚というものがあります。
これはどのようなものかというと…。
舵を切る量や速度に合わせて、操舵の際に舵に重みが生じることです。
分かりやすく言えば、車でハンドルを切ると、その切れ角や速度に応じて、手に重みを感じることが
出来ます。
これが操舵感覚、飛行機などの飛びものでは、「舵感」などと言ったりします。
これって、非常に大事なことなんです!
皆さん、ちょっと想像してみてください。
仮に、ハンドルを切ってもまったく重みを感じない車があったとしましょう。
いくらハンドルを切ってみても、手応えなくスカスカな状態です。
そんな車でカーブを曲がると…。
視界からしか情報が認識できない状態になり、カーブに合わせようとしても、切りすぎたり戻したり…。
ふらふらと安定しない曲がり方になってしまうんです!
実際の車ではそのようなことにならないように、その構造や調整により、ハンドルを切ると上手く重みが生じるようになっています。
飛行機などでは、この舵感がもっと重要になり、舵の形状やその構造などの工夫、更に、ジェット機など高速で飛ぶ飛行機の場合、コンピュ
ータによる制御までして、それを実現させているのです。
で…。
本題のハンググライダーの場合なのですが…。
実は、「ピッチ」の操縦については、コントロールバーがあるおかげで、理想的な舵感が実現できているのです!
このように書くと、ちょっと難しく感じるかもしれませんが、バープレッシャーというと、「あ
~!」と思う上級者の方は多いと思います。
そう。ここで御説明している「舵感」って、つまりはハンググライダーでいうバープレッシャーのことなんです。
このバープレッシャー。なぜそのような感覚が生まれるのかというと…。
ハンググライダーをはじめ、航空機には自立安定性というものが持たされています。
これは、正常な飛行状態に、飛行機が勝手に戻ろうとするもののことです。
ハンググライダーはこの作用のおかげで、たとえコントロールバーを握らなくても、一定の速度で飛ぼうとしてくれるのですが…。
仮に、いま速度を上げるために、コントロールバーを引いたとしましょう。
そうすると…。
ハンググライダーは自立安定性があるため、元の速度に戻りたがります。それに対し、人はコントロールバーを引くわけですから、
その反力で人は持ち上がってしまうのです。
この人が持ち上がった体重分が、バープレッシャー、つまり、舵感として感じられるわけです。

この感覚は、空を飛ぶものにとって、非常に大事なものです。
このバープレシャーは、初級機などの機体では重くなる設定となっていますが、競技機などでは、必要最小限の軽さに収められています。
競技機など、高性能を狙う機体では、不必要なピッチ安定はその性能を奪ってしまう要素でしかないからです。
つまり、それだけハンググライダーの競技機は、ピッチの安定に余裕がないわけですが…。
熟練したパイロットであれば、このバープレッシャを正確に感じ取り、ぎりぎりのラインでその安全性をキープすることが出来ます。
更には、その他にも最小沈下速度や最良滑空速度、更には失速速度なども、やはり、バープレッシャーが生じるおかげで、パイロットはその感覚だけで
かなり正確にグライダーの翼の気流の状態がどのようになっているのかを判断することが出来るのです。
このような、操縦するものにとってハンググライダー乗りこなしやすくなったことも、コントロールバーがあったおかげであり、飛行機でいうところ
の「舵感」、つまり、「バープレッシャー」を作り出すことが出来たからだと言えます。
ちなみに…。
某、琵琶湖で開催されている自作飛行機の競技会などでも、体重移動と電気的なサーボの制御での操縦が主で、一部(最近ワイヤーリンケージを使
って舵感が感じられる機体が増えてきている。)を除いて「舵感」が感じられない構造になっているため、機体の飛行状況は視界からのみ得られる情報
だけで飛ばせていますが、これが、何とかパイロットが「舵感」が感じられる構造を考案すれば、面白い機体が出来るのではないか?と、私は思ってい
ます。
コントロールバーの役目は…。
・機体を持ち上げ、姿勢を維持できるとにより、テイクオフを可能とする。
・ワイヤー等を張ることにより、翼の強度を上げる
・着陸時にフレアーの動作を可能とさせ、足だけで降りることが出来る。
・機体の操縦を可能とさせる。
と、いくつもの役割を兼ねていることをご説明いたしました。
実は、もう一つ重要な仕事もコントロールバーはしているので、今回はそれをご説明いたします!
まず、飛行機はもちろん、自動車などの乗り物には、必ず操舵感覚というものがあります。
これはどのようなものかというと…。
舵を切る量や速度に合わせて、操舵の際に舵に重みが生じることです。
分かりやすく言えば、車でハンドルを切ると、その切れ角や速度に応じて、手に重みを感じることが
出来ます。
これが操舵感覚、飛行機などの飛びものでは、「舵感」などと言ったりします。
これって、非常に大事なことなんです!
皆さん、ちょっと想像してみてください。
仮に、ハンドルを切ってもまったく重みを感じない車があったとしましょう。
いくらハンドルを切ってみても、手応えなくスカスカな状態です。
そんな車でカーブを曲がると…。
視界からしか情報が認識できない状態になり、カーブに合わせようとしても、切りすぎたり戻したり…。
ふらふらと安定しない曲がり方になってしまうんです!
実際の車ではそのようなことにならないように、その構造や調整により、ハンドルを切ると上手く重みが生じるようになっています。
飛行機などでは、この舵感がもっと重要になり、舵の形状やその構造などの工夫、更に、ジェット機など高速で飛ぶ飛行機の場合、コンピュ
ータによる制御までして、それを実現させているのです。
で…。
本題のハンググライダーの場合なのですが…。
実は、「ピッチ」の操縦については、コントロールバーがあるおかげで、理想的な舵感が実現できているのです!
このように書くと、ちょっと難しく感じるかもしれませんが、バープレッシャーというと、「あ
~!」と思う上級者の方は多いと思います。
そう。ここで御説明している「舵感」って、つまりはハンググライダーでいうバープレッシャーのことなんです。
このバープレッシャー。なぜそのような感覚が生まれるのかというと…。
ハンググライダーをはじめ、航空機には自立安定性というものが持たされています。
これは、正常な飛行状態に、飛行機が勝手に戻ろうとするもののことです。
ハンググライダーはこの作用のおかげで、たとえコントロールバーを握らなくても、一定の速度で飛ぼうとしてくれるのですが…。
仮に、いま速度を上げるために、コントロールバーを引いたとしましょう。
そうすると…。
ハンググライダーは自立安定性があるため、元の速度に戻りたがります。それに対し、人はコントロールバーを引くわけですから、
その反力で人は持ち上がってしまうのです。
この人が持ち上がった体重分が、バープレッシャー、つまり、舵感として感じられるわけです。

この感覚は、空を飛ぶものにとって、非常に大事なものです。
このバープレシャーは、初級機などの機体では重くなる設定となっていますが、競技機などでは、必要最小限の軽さに収められています。
競技機など、高性能を狙う機体では、不必要なピッチ安定はその性能を奪ってしまう要素でしかないからです。
つまり、それだけハンググライダーの競技機は、ピッチの安定に余裕がないわけですが…。
熟練したパイロットであれば、このバープレッシャを正確に感じ取り、ぎりぎりのラインでその安全性をキープすることが出来ます。
更には、その他にも最小沈下速度や最良滑空速度、更には失速速度なども、やはり、バープレッシャーが生じるおかげで、パイロットはその感覚だけで
かなり正確にグライダーの翼の気流の状態がどのようになっているのかを判断することが出来るのです。
このような、操縦するものにとってハンググライダー乗りこなしやすくなったことも、コントロールバーがあったおかげであり、飛行機でいうところ
の「舵感」、つまり、「バープレッシャー」を作り出すことが出来たからだと言えます。
ちなみに…。
某、琵琶湖で開催されている自作飛行機の競技会などでも、体重移動と電気的なサーボの制御での操縦が主で、一部(最近ワイヤーリンケージを使
って舵感が感じられる機体が増えてきている。)を除いて「舵感」が感じられない構造になっているため、機体の飛行状況は視界からのみ得られる情報
だけで飛ばせていますが、これが、何とかパイロットが「舵感」が感じられる構造を考案すれば、面白い機体が出来るのではないか?と、私は思ってい
ます。