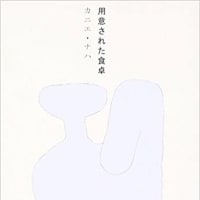『今ここに父を送る野道は細く、人には愛がある。
私は湧きかえる感情を畳んで頸を立てて歩き、喪服はさやさやと鳴った。
つゆ草が一トむら。名にちなむ花よ。』……「父」より
「父」と「こんなこと」は幸田文の父上である露伴にまつわる二篇の随筆です。
「こんなこと」は文の思春期から結婚、そして出産、離婚に至るまでの、
父(実母はすでにいない。)を中心とした、文とその弟との思い出話です。
「父」は娘の玉子を連れて離婚した文が、露伴のもとに帰った後のことであり、
露伴の看病から最期の看取り及び葬送についての思い出を書いたものです。
女性の生き方が多様化している現代において、それぞれの女性の生き方について
「間違っている」とも「正しい」とも言えない自分がいつもいます。
自らの生き方も含めて、女性の生き方の源流を辿ってみたくてこの本を開いたのかもしれません。
しかし「父」のなかで、介護に心を張りつめ身体を限界まで疲労困憊させている幸田文の姿は、現代でも同じことだと思えます。
どの時代でも介護の当事者よりも外野が煩いことも同じで、当事者の腹立たしさも同じでした。
介護の本質はこの理不尽さゆえに見失われることが多いのです。
女性の生き方の形態は変われども、こうした点では時代を超えても変わらないもののようでした。
けれども、露伴の葬送の時にすべてが昇華されます。文の七歳の春、母の葬送の折の父の言葉「しゃんとして歩けよ。」が彼女の記憶に蘇る。
そして最後はこのように結ばれています。
『親は遂に捐てず、子もまた捐てられなかったが死は相捐てた。四十四年の思い出は美醜愛憎、ともに燦として恩愛である。
これから生きる何年かのわが朝夕、寂しくとも父上よ、海山ともしくない。』と言い切ったのでした。
さて「こんなこと」に話題を移します。
すでに母不在の家族になって、娘の幸田文のすべての教育は父の露伴が務めることになります。
これについて書いている文はさぞ楽しかったであろうと思えます。読む方も非常に楽しいものでした。
女性が一番幸福な時間とは娘時代なのでしょうか?
認知症になった私の亡母がほとんどの記憶を失くした後に残った記憶は娘時代だったことをふと思い出しました。
(ここから少し脱線。)
その母から私へ、そして娘へと伝わった摩訶不思議な形容詞があって、赤ちゃんの髪の毛を「ぽやぽや」と言っていました。
しかし娘が高校時代に友人から「聞いたことがない。」と言われてショックを受けていました。
これは方言なのか?我が一族だけの共通認識だったのか?と初めて疑いを持ちました。
しかし、大いなる味方があらわれました。「こんなこと」のなかに「ぽやぽや」を発見!
『老いて残りすくない祖父の白髪にも、幼くぽやぽやと柔らかい孫の髪にも春日はひかっていた。』
祖父とは露伴、孫は青木玉さんです。
(路線回復。)
露伴の文への教育は家事家計全般、着物のこと、様々な人間関係など。
どこか無理難題であったり、妙に箍がはずれていたり、皮肉まじりであったりしますが、文の意地っ張りと見事に調和していました。
この調和のなかに深い愛情が立ち昇ってきます。こうして人間はいずれ親のいない(自分が親になる)人生の到来を受け止めて生きてゆけるのでしょう。
さて、ここで私は「女性の生き方」について何を学んだのだろうか?
まず「女性」という枠をはずしてみることでした。
露伴の文への深い(乱暴とも言える。)愛は、文が強く生きてゆく心を育てました。
露伴は文を才色兼備のおとなしい女性ではなく、逞しい農婦のように育てたのです。
女性の生き方ではなく、人間の生き方と愛し方を。
大き過ぎる父の存在と、その愛に向き合った幸田文の健かな背筋を感じました。
《追記》
この記事は清水哲男さん発行の《Weekly ZouX 309号(12月16日付)》に掲載されたものです。
(平成23年・第76刷・新潮文庫)