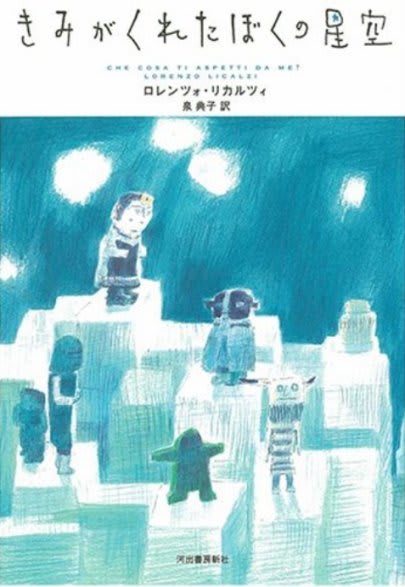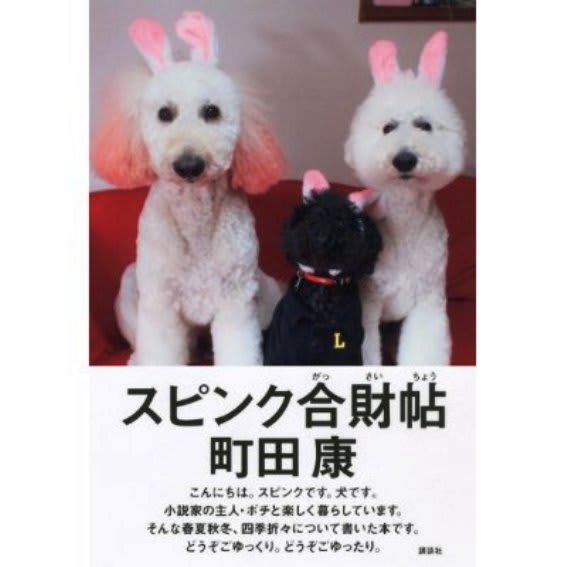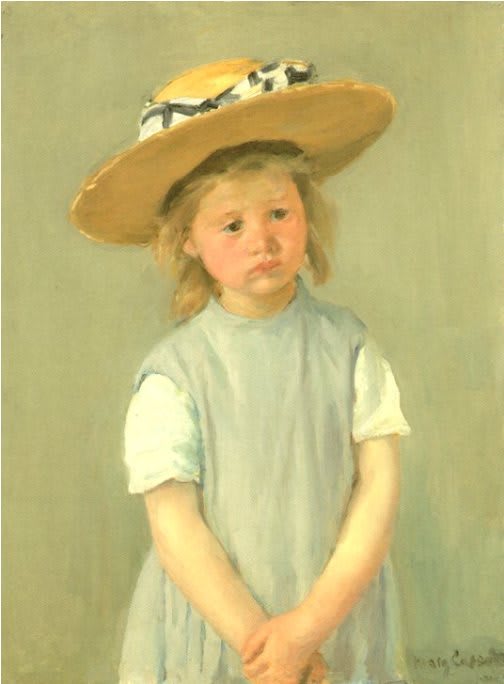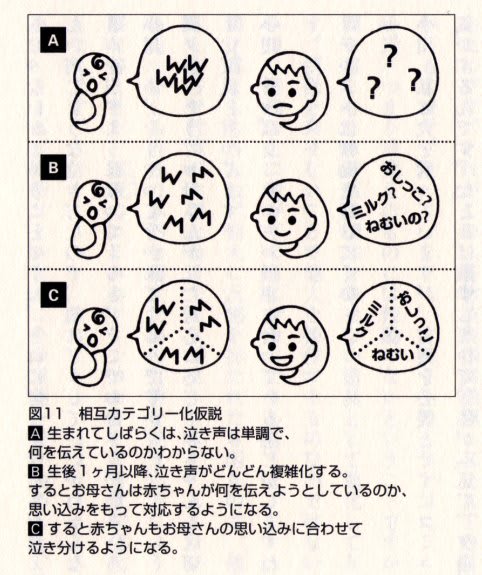読了後、一番はじめにぼんやりと感じとったことなのですが、一人の学者が育ってゆくこと、あるいは育てられてゆくためには、
わずかな人数でいいのだが他者の大きな愛がいる。
また一筋の思想が頑なでもなく偏りもなく育ってゆくためには、人間の根源から涌き出るような深い愛の力がいるのだということでした。
網野善彦の言葉を借りれば「彼はたいへんしゃれた、うまいいい方のできる人で、なかなか本質的な表現で私がぼんやり考えていることをいってくれます。」
というような中沢新一の美しい文体とともに、そのような深い感銘を受けました。
まず、哲学者であり宗教学者の中沢新一を育てた親族を記してみよう。すべて山梨県出身者でることにも注目して下さい。
父親の中沢厚は在野の民族学者、コミュニストである。叔父の中沢護人も「鉄の歴史家」と言われた在野の研究者です。
そして中沢新一が五歳の時に、父中沢厚の妹の真知子叔母の婚約者として登場するのが、この本のタイトルとなっている歴史学者「網野善彦」です。
この四人の真摯で豊かな対話の積み重ねが、さらに思考のおおきな流れをつくっていったようです。
この網野善彦は若き日の中沢新一にこのように語っています。
『貧しい甲州は、ヤクザとアナーキストと商人しか生まない土地だと言われてきたけれども、
そのおかげで、ほかのところでは消えてしまった原始、未開の精神性のおもかげが、
生き残ることができたともいえるなあ。貧しいということは、偉大なことでもあるのさ。』
この一冊に貫かれているものはこの網野の言葉に集約されているようです。
中沢厚の著書に『つぶて・一九八一年・法政大学出版局刊』がある。「飛礫(つぶて)あるいは(ひれき)」の歴史の再発見がテーマとなった著書である。
この論考の発端となった厚の意外な視点についての、新一の記述部分は心が躍り出すほどに面白かった!
一九六八年一月、佐世保港にアメリカの原子空母「エンタープライズ」が給油のため入港する。
それを阻止しようとした「反代々木系」の学生たちはヘルメット、角棒、旗竿を持って機動隊に激突、
そして彼等のとった行動は「投石」であった。機動隊はおおいにたじろいだ。
このテレビ報道を食い入るように観ていた父親が最初に語ったことは、
父親の少年期の、笛吹川の対岸の万力村や正徳寺村の子供たちと、こちら側の加納岩村の子供たちとの「投石合戦」だったのだ。
「投石」という人類の根源的な衝動の働きかけを厚はそこに感じとったのである。原初の人間から引き継がれている行為は、
消えることなく現代の人間たちに内在されていたということだろうか?中沢厚のこの研究はそこから出発したらしい。
この中沢厚の「つぶて」は網野善彦の著書『蒙古襲来』に引き継がれる。
この著書の章のタイトルは「飛礫、博奕(ばくえき)、道祖神」から始まった。
難しいことはわからないが、わたしが感覚的に理解できたことは「アジール」的な精神世界の存在が、歴史の根底にはいつもしっかりとあって、
その上で人間の侵略戦争、反権力闘争は続いてきたのだろうということでした。
これ以後、網野善彦と中沢新一の仕事は弛むことなく続くのですが、以上書いたことは、
この一冊から極私的にわたしの心の琴線に触れた部分だけです、と責任放棄しておきます。
(2004年・集英社新書)