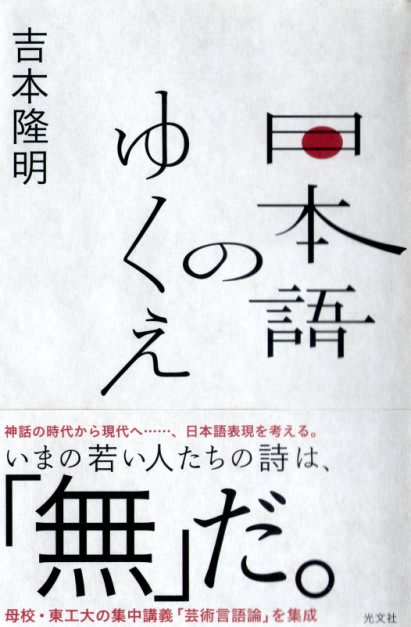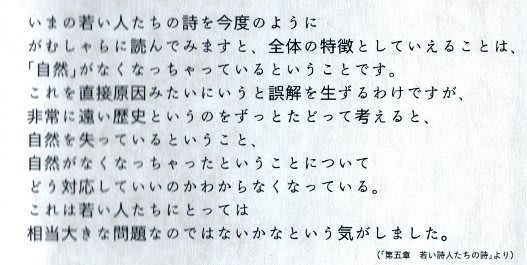これは「取り替え子・チェンジリング・2000年」と「憂い顔の童子・2002年」との3部作となっています。すべて講談社刊。
3部とも主人公の老作家「長江古義人」をはじめとして、その家族、友人たちとの物語です。
そしてこれらはすべて「いのち」の根源を辿る道のりであり、死者への語りかけでもあり、
古義人は何度も少年期に戻り、そこに置き去りにされたままでいるもう一人の分身の「童子」とのはるかな対話を続けながら、
さらに老境に入った小説家としての「総括」あるいは「覚悟」かもしれません。
それを建築家の「繁」と「おかしな2人組・スウード・カップル」として締めくくろうとしたのだろうか?
さようなら、私の本よ! 死すべき者の眼のように、
想像した眼もいつか閉じられねばならない。
恋を拒まれた男は立ち上がることになろう。
――しかし彼の創り手は歩き去っている。
この詩は、老年になって、暴力事件の被害者となり、深手を負って入院した「古義人」が、
集中治療室から集団快復病棟に移された夜に見た夢のなかで、
若いナバコフの小説(ドイツ語)の結びとなっていた詩のような一節を「古義人」が邦訳したものだった。
それが、この小説のタイトルとなっています。
この物語の第1部の扉は、このエリオットの詩から開かれた。
もう老人の知恵などは
聞きたくない、むしろ老人の愚行が聞きたい
不安と狂気に対する老人の恐怖心が
――T・S・エリオット(西脇順三郎訳)
上記の3冊の小説のなかで、老作家は次々に大切な友人を亡くしています。映画監督、音楽家、編集者などなど・・・・・・。
そして残された友人の建築家の「繁」を中心として、その周囲の若い人間たちとのドラマが「さようなら、私の本よ!」だった。
「繁」はアメリカの大学で教鞭をとっていたが、長い空白ののちに帰国して「古義人」とともに、深く関わる時間を共有することになります。
エリオットの詩に「ゲロンチョン」という作品があります。
ギリシャ語で、geron(old man)とtion(little)を組み合わせた言葉で、「小さな老人」の意味ですが、
一般的な意味では、精神が萎縮しつつある人間と社会を象徴しているようです。
主人公の老作家の軽井沢の別荘は、この「小さな老人=ゲロンチョン」という名前が付けられています。
かつて設計と建築に関わったのは「繁」であり、案は「古義人」だった。
――ぼくの父親がいったのは、ぼくの代りに死んでくれるほかの子供ということだが、
きみのお母さんがいわれたのは、ぼくがきみの代りに死ぬ、ということだね。(古義人)
――それでも、事の始まりは、われわれお互いの母親が、それぞれの子供をね、
相手のために死ぬ人間へ育てようと、そういう密約だったのじゃないか?(繁)
少年期に不思議な出会いをした二人の少年の、再び老齢にはいってから交わされたこの会話は一体なんだろう?
これは、第2部の扉にかかれた詩です。
死んだ人たちの伝達は生きている
人たちの言語を越えて火をもって
表明されるのだ。
――T・S・エリオット(西脇順三郎訳)
第3部の扉では・・・・・・
老人は探検家になるべきだ。
現世の場所は問題ではない
われわれは静かに静かに動き始めなければならない。
――T・S・エリオット(西脇順三郎訳)
三島由紀夫の自決、「古義人」のかつての自殺未遂、
「古義人」と「繁」を中心として会話があり、そこに集まった若い人たちの考え方あるいは1人の老作家の見方など、
錯綜する対話のなかで、「古義人」は、1つの時代を終えて、
あらたな老作家として、どう書いて生きてゆくのか?を模索するのでした。
(2005年・講談社刊)