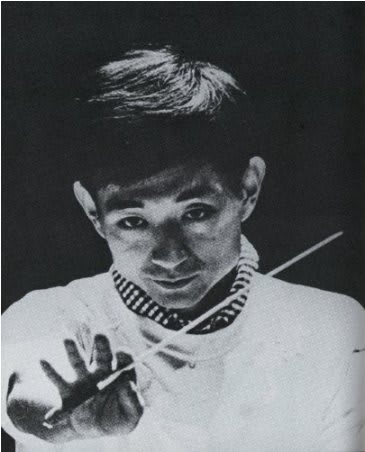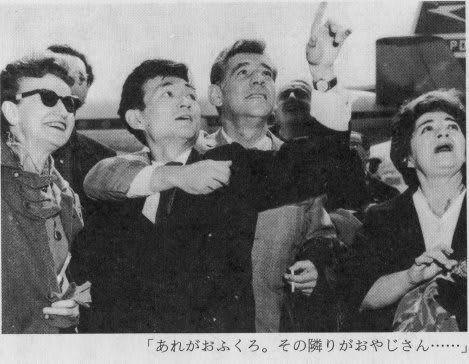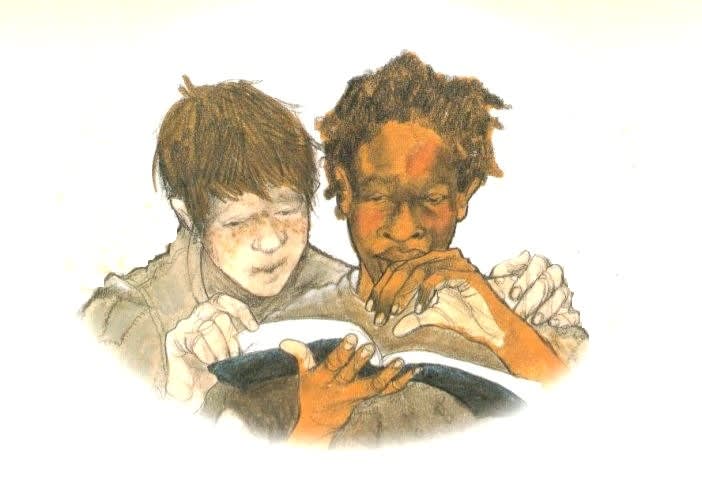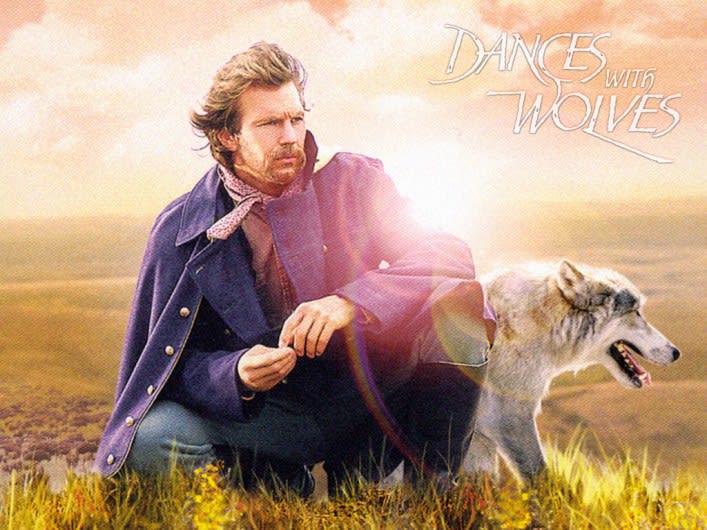この本は、須賀敦子が選んだ、19世紀から20世紀を生きた5人の詩人についてのエッセーであり、それぞれの代表的な作品の紹介ともなっています。
彼女の細やかな、そして真摯な眼差しが感じられる心地よい文章です。しかしながら読み手のわたくしはそこに紹介されている詩の原文にあたることはできない。
「完璧な韻律」と言われても、わたくしは須賀敦子によって日本語に翻訳された詩を読むしか手立てがない。これがもどかしい。
ウンベルト・サバ(1883年~1957年)
「もし今日、トリエステに着いて、もう一度サバに会えるとしたら・・・・・・なにげなく選んだ道を、サバと歩くことができたなら・・・・・・」と、
1958年(サバの亡くなった翌年。)に言ったのはジャコモ・デベネデッティだが、その同じ思いを抱いて須賀敦子は「サバ」について書きはじめる。
この思いが彼女のエッセー「トリエステの坂道」にも繋がっているのだろう。
「サバ」はヘブライ語で「パン」を意味する。母親はユダヤ人だったが、彼女は「サバ」誕生の前に、「美しくて軽薄な」白人の夫に捨てられ、
幼い「サバ」はこの町のゲットーで育つ。父親のイタリア名はすすんで捨てて、「サバ」というペンネームとする。
彼の詩作の源泉は「トリエステ」と妻の「リーナ」、時代に遅れた詩人と見られる傾向もあり、ユダヤ人であることの孤独などから、孤高の詩人でもあったが、
須賀敦子は彼の貧しさのなかで育った誠実なやさしさ、韻律の美しさに注目した。
ジョゼッペ・ウンガレッティ(1888年~1970年)
「ウンガレッティ」はエジプトのアレキサンドリア生まれ。両親はルッカ(トスカーナ)出身。2歳で両親を亡くし、24歳でアレキサンドリアからパリに出る。
「アフリカ人」の彼が、フランス文化とイタリア文化の坩堝に巻き込まれることになる。
「ウンガレッティ」の詩作は彷徨し、姿勢が整わないままに、ヨーロッパは第一次大戦の舞台と変わる。
この「死の時代」のなかで皮肉にも彼の詩は生命に肉迫するものとなる。そうして新しいイタリア詩の誕生を迎える。
季節をめぐるように「ウンガレッティ」の詩作は充足の秋へと向かう頃に兄を失い、九歳の息子を失う。
「死は生きることで贖われる。」と、28歳の「ウンガレッティ」は戦場でうたったが、秋の終わりには「挽歌」とともに、詩人の冬の季節が来てしまった。
エウジェニオ・モンターレ(1896年~1981年)
オペラ歌手を目差したこともあった彼は、彼の詩の重要な特徴となった音楽的ともいえる韻律として詩のなかに活かされている。
さらにフランス語、スペイン語、英語などを独学で学び、外国文学を原語で親しんでいる。
音楽評論、外国の詩のイタリア語訳など、彼の活動の範囲は広く、それが詩人「モンターレ」の豊かな土壌ともなっている。
1938年に、ファシスト政党党員になることを拒否。翌1939年に出版された第二詩集「機会」は、
前線に送られた若きインテリ兵士の限られた荷物のなかには、しばしばこの詩集があったという伝説をもつ詩集となっています。
彼は「サルヴァトーレ・クワジーモド」とともに「ノーベル文学賞」受賞者でもあるが、
「サルヴァトーレ・クワジーモド」の受賞は否定論者が多かったのに対して、
「モンターレ」の受賞は否定論者はなく賞賛されている。
また、人生の大半を精神病院で過ごした「ディーノ・カンパーナ」の死後の評価はさまざまに拡散するばかりであったが、
その彼に確固たる評価を与えたのも「モンターレ」だった。
ディーノ・カンパーナ(1885年~1932年)
「ディーノ・カンパーナ」は精神分裂病者で、生涯の大半を放浪と病院で過ごしていることによって、彼の二十世紀詩人としての存在そのものが特異なものとなっています。
この難しい詩人に向き合い、須賀敦子は粘り強く彼の作品と生涯を書いていらっしゃいました。
「ディーノ・カンパーナ」がこの地上に残した詩集は「オルフェウスの歌」(自費出版である。)一冊だけであったが、
彼の残したものの特異ともいえる大きな存在感は、のちのち文学評論家を迷わせるものとなる。
死後「オルフェウスの歌」は再評価され、復刻されます。
さらに「初稿」「未完詩集」、「評伝」「注釈」など、続々と出版されます。須賀敦子は最後にこのように記しています。
『彼は狂気に守られて、純粋詩の世界だけを追求することができた、数少ない幸福な詩人であったとさえいえるのではないか。
その意味からも、彼は、やはり《見者》の群に属する、光彩を放つ存在だったと、私は考えたい。そして《見者》はいつも不幸である。』
サルヴァトーレ・クワジーモド(1901年~1968年)
さて。須賀敦子も苦しみつつ書いているようで、この詩人の評価は難しい。
「ノーベル文学賞」受賞者ではあるが、この受賞そのものが不評であったという詩人です。
シチリア島のラグーサという小さな町で、駅長の子として生まれる。
文学仲間に出会うのはパレルモの中学時代。その出発点からスムーズに一九三〇年詩壇に登場してゆくことになる。
幸運ともいえる道筋だったように思えます。しかし須賀敦子の「クワジーモド」への言及には厳しい言葉が並ぶ。何故か?
「クワジーモド」は詩壇で、それ相当の評価をほぼ持続的に維持していたが、いつでも「疑惑」がついてまわった。
それは彼の作品の言葉の美しさとは裏腹に見えてくる、ものごとの本質性に対する徹底した無関心による非情さだった。
彼にも戦争は無縁ではなかった。しかし戦前の若い時代のみ、彼の詩は熱く息づいていたが、
戦後の「クワジーモド」は「水子の儚さにも似た世界にしかもとめられない。」ような「夢の職人」だったという厳しい言及となっていました。
* * * * *
以上5人のイタリア詩人について読んできましたが、読了後に驚かされたのは、このタイプの異なる詩人たちの生涯についてよりも、
須賀敦子が詩人をみつめる時のやさしさと同時にある「厳しさ」の方でした。それは「権威」に阿ることのない視線の確かさだったように思います。
(1998年・青土社刊)