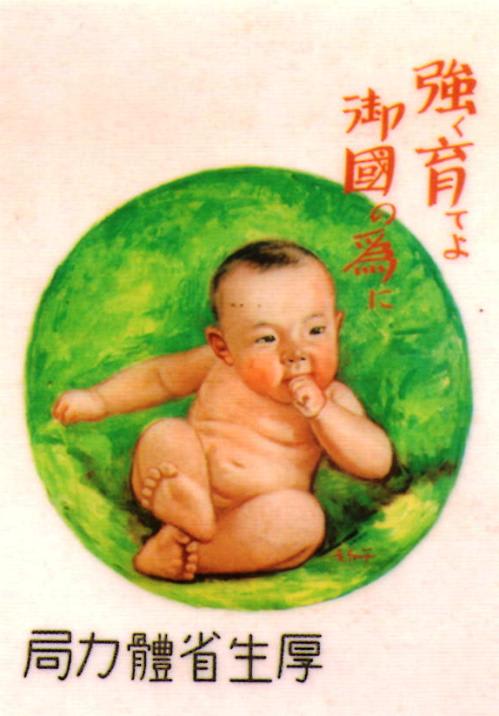著者:スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ
訳者:松本妙子
この本は、1991年ソヴィエト連邦(社会主義)の解体から、ロシア連邦(資本主義)へと移行した時代を生きた人々(決して特別な人々ではなく、市井の人々)の声を取材した一冊である。なんと606ページ。スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの熱意と永い歳月を要した困難な取材に、気の遠くなるような思いに迫られました。そして、多くの人々が国の激しい変動に翻弄されたことが、よくわかります。
「セカンドハンド」とは「思想も言葉もすべてが他人のおさがり、だれかのお古のような」そうした状況を言っているようだ。お仕着せの時代をさしているのだろうか。
歴史とは恐らく権力者と国家の動きを捉えているだけで、それに翻弄された市井の人々の真実の声は、なかなか聴こえてはきませんが、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの言葉に尽くせないほどの膨大な取材によって、私はそれを聴くことができました。それは単なる取材ではなく、語り手にすべてをゆだねて、質問はしない。そして語られた言葉たちは、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチによって、文学の域まで到達したと思う。
弾圧と犠牲のうえに、強大な軍事国家を築いたとしても、口を封じられた市井の人々が語りださなければ、真の歴史は見えてこないと著者は教えて下さいました。
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの著書は……
「戦争は女の顔をしていない」
「ボタン穴から観た戦争――白ロシアの子供たちの証言」
「アフガン帰還兵の証言――封印された真実」
「チェルノブイリの祈り――未来の物語」
以上4作と、「セカンドハンドの時代」を加えて、「ユートピアの声」シリーズとなっています。これらの困難極める仕事によって、2015年、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチはノーベル文学賞を受賞されています。お国では、大きなニュースにはしていないようですが……。
以下、引用。 映画監督 イリーナ・ワシーリエヴナの話。
『ルーシ(ロシアの古名)では、太古の昔から懲役囚が愛されてきました。(中略)酔っぱらった男が、わたしたちのヒロインがどこに住んでいるのか教えてくれた。百姓家から彼女が出てきた。わたしはすぐに気に入った。青い青い目。均整のとれた豊かな身体つき。美人と言っていい。ロシア美人です。このような女性は、貧しい百姓小屋でもモスクワの豪華な部屋でも輝くのです。彼女は殺人犯の妻で、わたしたちはまだ彼に会ったことがありませんが、終身刑を課せられ、結核をわずらっている。彼女は、わたしたちがここにやってきた目的を聞くと、「わたしの連続ドラマね」とわらった。わたしは歩きながら、彼女を撮ることをどう切りだそうかと考えていたのです。カメラをこわがったらどうしようかと。彼女はいうのです。「わたしっておバカで、会う人ごとに自分の話をしちゃうんです。泣く人もいるし、ののしる人もいるわ。よろしかったら、あなたにもお話します。」話してくれる。』
心に残った……。
(2016年9月29日 第一刷 岩波書店刊)