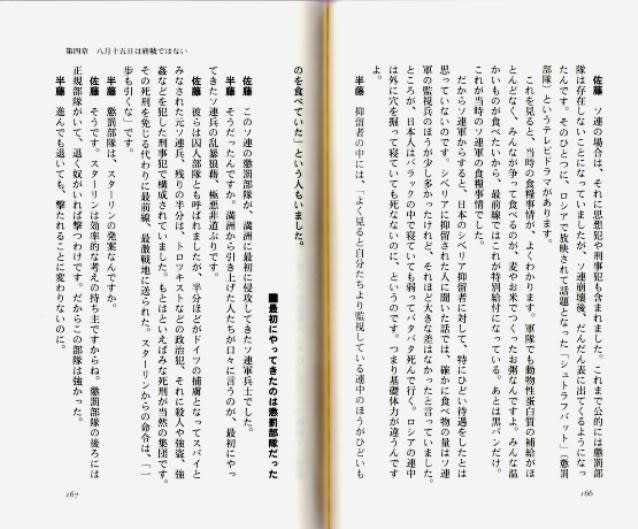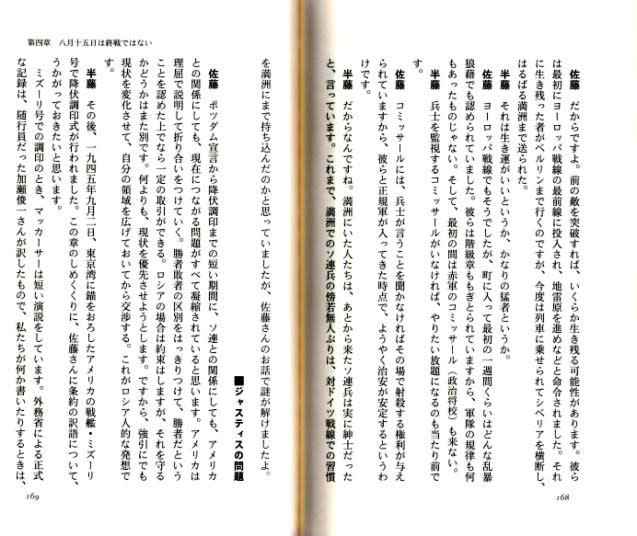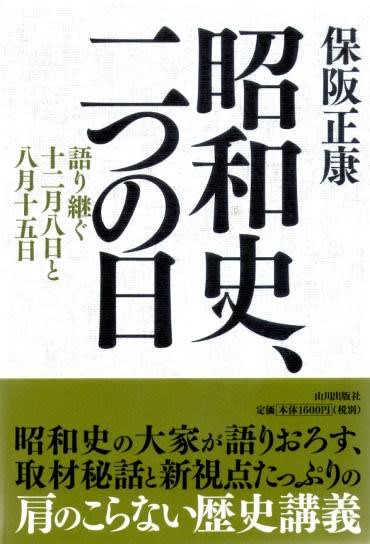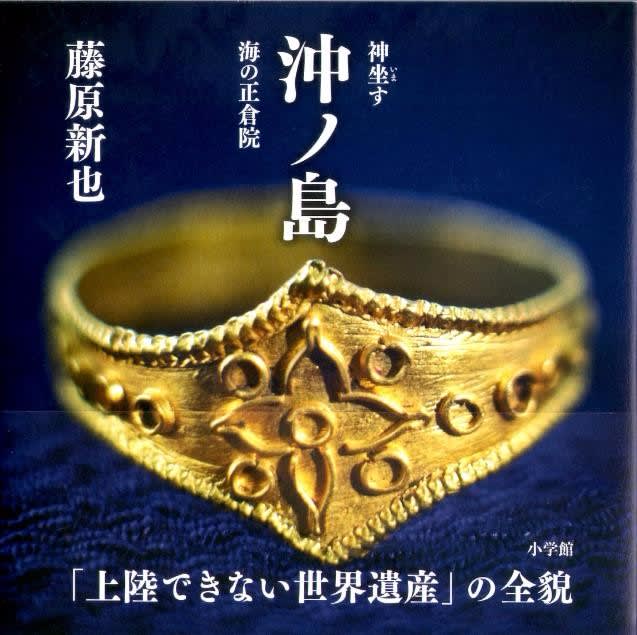1992年 文藝春秋 発行
イタリアの詩人たちを読んでから、大分時間は経過している。
1960年、イタリアのミラノの教会の片隅で、自由な共同体を夢みて発足した書店(リーダーはダヴィデ・マリア・トゥロルド神父。)に
集う人々との交流を記したエッセー集である。
その名は「コルシア・ディ・セルヴィ書店」。約20年間続いた。
その書店の援助者となる方々、その書店に集う(あるいは働く)仲間たちとの交流を記した一冊です。
須賀敦子の、その人々への記憶力と観察力が並ではないのです。
書店の仲間たちには、その時代が及ぼしたそれぞれの人生があって、括ることは出来ない。
それぞれみんな孤独だったのではないだろうか?
その仲間の1人であった「ジョゼッペ・ペッピーノ・リッカ」と須賀敦子は結婚する。しかし1967年に彼は死去する。
どの時代にあっても、書籍と書店の厳しさを思う。
しかしここから次の時代が導かれるのではないか?そう信じたい。
「あとがき」は「ダヴィデ」にむけて書かれています。最後にこう書かれています。
以下引用。
『コルシア・ディ・セルヴィ書店をめぐって、私たちは、ともするとそれを自分たちが求めている世界そのものであるかのように、あれこれと理想を思い描いた。
そのことについては、書店をはじめたダヴィデも、彼をとりまいていた仲間たちも、ほぼおなじだったと思う。
それぞれの心のなかにある書店が微妙に違っているのを、若い私たちは無視して、いちずに前進しようとした。
その相違が、人間のだれもが、究極においては生きなければならない孤独と隣あわせで、
人それぞれが自分自身の孤独を確立しないかぎり、人生は始まらないということを、すくなくとも私は、ながいこと理解できないでいた。
若い日に思い描いたコルシア・ディ・セルヴィ書店を徐々に失うことによって、
私たちは少しづつ、孤独が、かつて私たちを恐れさせたような荒野でないことを知ったように思う。』
久しぶりに本を読んだ。
日常の雑事に振り回されながら、どうにかその隙間で読みました。