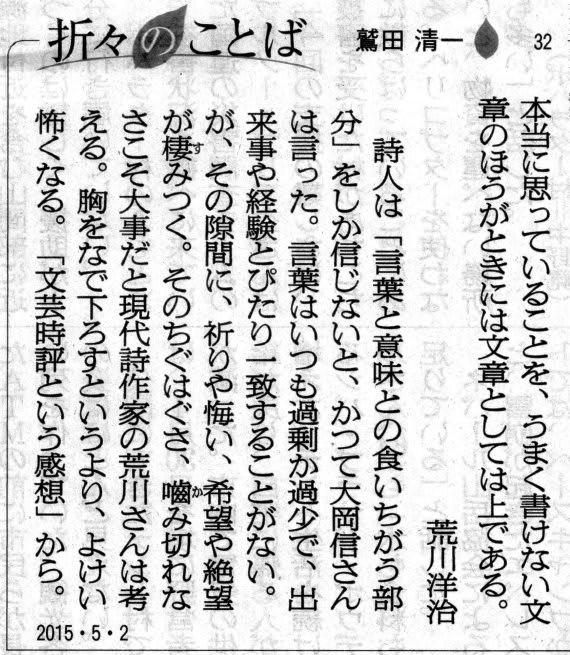「音の歳時記」 那珂太郎
一月 しいん
石のいのりに似て 野も丘も木木もしいんとしづまる
白い未知の頁 しいんーとは無音の幻聴 それは森閑の
森か 深沈の深か それとも新のこころ 震の気配か
やがて純白のやははだの奥から 地の鼓動がきこえてくる
二月 ぴしり
突然氷の巨大な鏡がひび割れる ぴしり、と きさらぎ
の明けがた 何ものかの投げたれきのつけた傷? 凍湖の
皮膚にはしる鎌いたち? ぴしりーそれはきびしいカ行音
の寒気のなか やがてくる季節の前ぶれの音
三月 たふたふ
雪解の水をあつめて 渓川は滔々と音たてて流れはじめ
る くだるにつれ川股に若草が萌え土筆が立ち 滔々た
る水はたふたふと和らぎ 光はみなぎりあふれる 野に
とどくころ流れはいっそう緩やかに たぷたぷ たぷ
たぷ みぎはの草を浸すだらう
四月 ひらひら
かろやかにひらひら 白いノオトとフレアアがめくれ
る ひらひら 野こえ丘こえ蝶のまぼろしが飛ぶ ひら
ひら空の花びら桃いろのなみだが舞ひちる ひらひら
ひらひら 緩慢な風 はるの羽音
五月 さわさわ
新緑の木立にさわさわと風がわたり 青麦の穂波もさわ
さわと鳴る 木木の繁りがまし麦穂も金に熟れれば ざわ
ざわとざわめくけれど さつきなかばはなほさわさわ
と清む 爽やか、は秋の季語だけれど 麦秋といふ名の
五月もまた 爽やか
六月 しとしと
しとしとしとしとしとしとしとしと 武蔵野のえごのき
の花も 筑紫の無患子の花も 小笠原のびいでびいでの
花も 象潟の合歓の花も うなだれて絹濃のなが雨に聴き
いる しとどに光の露をしたたらせて
七月 ぎよぎよ
樹樹はざわめき緋牡丹は燃え蝉は鳴きしきる さつと白
雨が一過したあと 夕霧が遠い山影をぼかすころ ぎよ
ぎよぎよ 蛙のこゑが宙宇を圧しはじめる 月がのぼる
とそれは ぎやわろっぎやわろっぎやわろろろろりっ
と 心平式の大合唱となる
八月 かなかなかな
ひとつの世紀がゆつくりと暮れてゆく 渦まく積乱雲の
ひかり 光がかなでる銀いろの楽器にも似て かなかな
かなかなと ひぐらしのこゑはかぼそく葉月の大気に
錐を揉みこむ 冷えゆく木立のかげをふるはせて
九月 りりりりり
りりりりり......りり、りりり......りりり、りり......り、
りりりり...... あれは草むらにすだく虫のこゑか それと
も鳴りやまぬ耳鳴りなのか ながつき ながい夜 無明
長夜のゆめのすすきをてらす月
十月 かさこそ
あの世までもつづく紺青のそら 北の高地の山葵色の林
を しぐれがさっさつと掠めてゆくにつれ 幾千の扇子
が舞ひ 梢が明るみはじめる 地上にかさこそとかすかな
気配 栗鼠の走るあし音か 地霊のつぶやきか
十一月 さくさく
しもつきの朝の霜だたみ 乾反葉敷く山道を行けばさり
さり 波うちみだれる白髪野を行けばさくさく 無数の
氷の針は音立ててくづれる 澄んだ空気に清んだサ行
音 あをい林檎を噛む歯音にも似て
十二月 しんしん
しんしん しはすの空から小止みなく 白模様のすだれ
がおりてくる しんしん茅葺の内部に灯りをともし 見
えないものを人は見凝める しんしんしんしん それは
時の逝く音 しんしんしんしん かうして幾千年が過ぎてゆく
* * *
「しんしんしんしん かうして幾千年が過ぎてゆく」のですね。
今日はとても寒い。風が強い。
もっと寒い地方では、この厳しい冬を何度繰り返してきたのだろうか?
そして幾千年が過ぎて、時が逝く(行く、ではなくて)音は「しんしん」となる。
炭つぐや骨拾ふ手のしぐさにて 那珂太郎
ここまで追いつめておいて、「一月」は
「やがて純白のやははだの奥から 地の鼓動がきこえてくる」となる。
この詩と俳句が、どの時期に書かれたものかはわからないが、
私の思いのなかでは、奇妙に繋がっている。