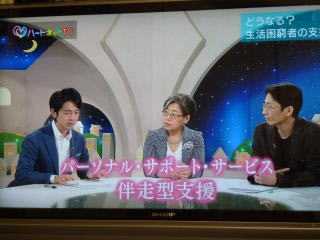4月21日(日)金沢都ホテル地下2Fセミナーホールで社民党若者アクションプログラム2013が開催されました。
テーマは「若者と雇用」 格差社会を許すな!
雨宮処凛さんは、若者の「生きづらさ」についての著作を発表したり、不安定さを強いられる人々「プレカリアート」問題に取り組み、精力的に発信。「『生きさせろ』難民化する若者たち」は、日本ジャーナリスト会議賞受賞。反貧困ネットワーク副代表、週刊金曜日編集委員など。
雨宮さんから、若者の生きづらさのリアルな事例が報告され、それらは、働きづらさー貧困問題ー生活保護問題へとリンクしていることを知らされました。
若者の不安定雇用は「自己責任」にされがちであるが、これは、会社の切り捨て政策である。
なぜ若者はこんな目にあってもっと怒らないのかと言われるが、競争社会の中で自己肯定感が奪われて自分はダメな人間だと思ってしまっている。
人に助けを求められるためには、自己肯定感や社会・他人への信頼関係必要。
フロアからは、若者、女性、そして、福島から避難された方から、バカンス法を制定しワークシェアし、ゆったり生きられる社会にしてはどうか、若者ももっと一次産業に従事してはどうかなどの提案がありました。
雨宮さんからは、東京の杉並の「デモ割」の報告。脱原発などの5000人ものデモの参加者に商店街の割引券(デモ割)を支給する。その割引券でデモ終了後に参加者が居酒屋で楽しく一杯やる。商店街が活性化し、地域でデモが支援される相乗効果を生み、町おこしにつながっている。
福島党首からは、状況は厳しいが、楽しいこともやらなくてはいけない。自然エネで地域に雇用を生み出すことが可能。(香川県、小田原市、飯田市、世田谷区)など、最後は元気の出る報告を聞き、あっという間に時間が来てしまいました。
久しぶりに(?)有意義で楽しい会でした。私が25年くらい前に小1・2を担任した若者が今朝のフェイスブックを見て、友達2人誘って駆け付けてくれて最前列に陣取り、発言してくれたこともうれしかったです。
私は、お二人を小松空港へ出迎え、会場へ向かう途中のタクシーの中で講演と対談の打ち合わせをし、司会に臨みました。福島党首は打ち合わせの内容以外にもずっとおしゃべり続け、まあなんとエネルギュッシュなことか!と驚きました。
テーマは「若者と雇用」 格差社会を許すな!
雨宮処凛さんは、若者の「生きづらさ」についての著作を発表したり、不安定さを強いられる人々「プレカリアート」問題に取り組み、精力的に発信。「『生きさせろ』難民化する若者たち」は、日本ジャーナリスト会議賞受賞。反貧困ネットワーク副代表、週刊金曜日編集委員など。
雨宮さんから、若者の生きづらさのリアルな事例が報告され、それらは、働きづらさー貧困問題ー生活保護問題へとリンクしていることを知らされました。
若者の不安定雇用は「自己責任」にされがちであるが、これは、会社の切り捨て政策である。
なぜ若者はこんな目にあってもっと怒らないのかと言われるが、競争社会の中で自己肯定感が奪われて自分はダメな人間だと思ってしまっている。
人に助けを求められるためには、自己肯定感や社会・他人への信頼関係必要。
フロアからは、若者、女性、そして、福島から避難された方から、バカンス法を制定しワークシェアし、ゆったり生きられる社会にしてはどうか、若者ももっと一次産業に従事してはどうかなどの提案がありました。
雨宮さんからは、東京の杉並の「デモ割」の報告。脱原発などの5000人ものデモの参加者に商店街の割引券(デモ割)を支給する。その割引券でデモ終了後に参加者が居酒屋で楽しく一杯やる。商店街が活性化し、地域でデモが支援される相乗効果を生み、町おこしにつながっている。
福島党首からは、状況は厳しいが、楽しいこともやらなくてはいけない。自然エネで地域に雇用を生み出すことが可能。(香川県、小田原市、飯田市、世田谷区)など、最後は元気の出る報告を聞き、あっという間に時間が来てしまいました。
久しぶりに(?)有意義で楽しい会でした。私が25年くらい前に小1・2を担任した若者が今朝のフェイスブックを見て、友達2人誘って駆け付けてくれて最前列に陣取り、発言してくれたこともうれしかったです。
私は、お二人を小松空港へ出迎え、会場へ向かう途中のタクシーの中で講演と対談の打ち合わせをし、司会に臨みました。福島党首は打ち合わせの内容以外にもずっとおしゃべり続け、まあなんとエネルギュッシュなことか!と驚きました。