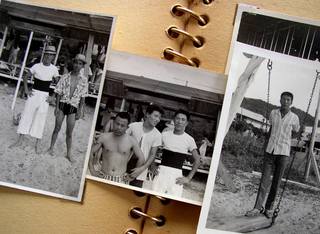丑年にあやかって、“牛に引かれて善光寺参り…”ではないが、“孫に引かれておのぼりさん”の東京タワー見学まで後2週間。 今となっては、言い出しっぺの孫よりも、じいちゃんが一番その気になって、あれもこれも…とスケジュールを欲張っている。
そんな折り、思いも掛けぬ嬉しいプレゼントを頂いた。
「……ささやかですが、気持ちです……」メッセージに添えて東京タワー展望券「OBSERVATION TICKET」3名分が送られてきた。もちろん丁重なお手紙に、タワーパンフ・周辺地図なども。
感動に胸が熱くなった。 内容や理由は、6歳には理解しがたいだろうから今は言わない。が、もう少し大きくなったらちゃんと話して、人と人とのつながりの大切さ・有り難さ・嬉しさ…全てを含めて、人生のいい教材として話して聞かせたい。
思い起こせば、14年前に初めての出会いがあった。
会社の命令で本社勤務を命じられ、単身赴任。住まいは、有楽町から45分くらいのベッドタウン。会社が準備した借り上げマンション。その管理をされていたご夫妻である。 そこで7ヶ月間お世話になった。
その後世田谷区の単身赴任寮に引っ越したから、実質のお付き合いは、14年前のわずか7ヶ月である。
それはそれは気の置けない素晴らしいご夫婦で、おっかなびっくりのお上りさんをものの見事に都会生活に馴染ませて頂いた。それだけで終生忘れ得ぬ出会いとなった。その後ももちろん音信は途絶えず、定年退職2ヶ月後には退職の挨拶に訪問した。
一昨年、錦帯橋・宮島を旅行されるチャンスに恵まれ、ホンの少し案内して差し上げた。
長い生涯の中でのたったの7ヶ月間のお付き合いが、今このような形で感動させて頂けるとは、人生って素晴らしいなー……と、つくづく思う。
こんな感動で始まる14年ぶりの東京見物、やっぱり、孫に引かれて…などではない。
じいちゃんに引かれて、孫が後からついてくる旅になりそうだ。 楽しんでくるぞー……。
( 写真: 送られてきた展望券・パンフなどなど )
そんな折り、思いも掛けぬ嬉しいプレゼントを頂いた。
「……ささやかですが、気持ちです……」メッセージに添えて東京タワー展望券「OBSERVATION TICKET」3名分が送られてきた。もちろん丁重なお手紙に、タワーパンフ・周辺地図なども。
感動に胸が熱くなった。 内容や理由は、6歳には理解しがたいだろうから今は言わない。が、もう少し大きくなったらちゃんと話して、人と人とのつながりの大切さ・有り難さ・嬉しさ…全てを含めて、人生のいい教材として話して聞かせたい。
思い起こせば、14年前に初めての出会いがあった。
会社の命令で本社勤務を命じられ、単身赴任。住まいは、有楽町から45分くらいのベッドタウン。会社が準備した借り上げマンション。その管理をされていたご夫妻である。 そこで7ヶ月間お世話になった。
その後世田谷区の単身赴任寮に引っ越したから、実質のお付き合いは、14年前のわずか7ヶ月である。
それはそれは気の置けない素晴らしいご夫婦で、おっかなびっくりのお上りさんをものの見事に都会生活に馴染ませて頂いた。それだけで終生忘れ得ぬ出会いとなった。その後ももちろん音信は途絶えず、定年退職2ヶ月後には退職の挨拶に訪問した。
一昨年、錦帯橋・宮島を旅行されるチャンスに恵まれ、ホンの少し案内して差し上げた。
長い生涯の中でのたったの7ヶ月間のお付き合いが、今このような形で感動させて頂けるとは、人生って素晴らしいなー……と、つくづく思う。
こんな感動で始まる14年ぶりの東京見物、やっぱり、孫に引かれて…などではない。
じいちゃんに引かれて、孫が後からついてくる旅になりそうだ。 楽しんでくるぞー……。
( 写真: 送られてきた展望券・パンフなどなど )