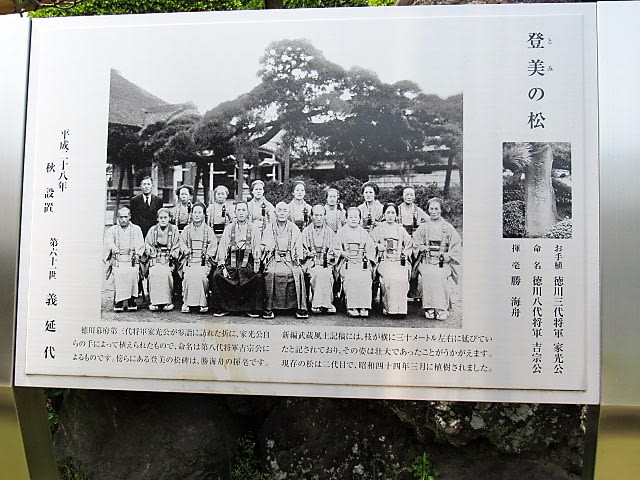釣鐘(つりがね)について想うこと
7月3日のことでした。
釣鐘の下で物思いにふけっていた。
難しい漢字を読み解いていたら、金属回収令なる文字を発見
当時に思いを浸した。

① 鐘楼建設に当たり寄付された人の名前(S41年竣工)

② 釣鐘と第2次世界大戦と金属供出

③ 諸行無常・・・・。
釣鐘の下に立ちて、しばし考えを巡らした。
① 鐘楼建設に当たり寄付された人の名前
多額を寄付された方は50万円、一般的に5千円が多かった。
昭和41年↓建設とありますから、当時の物価を調べてみた(対比)
中華そば 64円(559円):8.73倍
マヨネーズ(500g) 44円(292円):6.64倍
コーヒー(喫茶店) 76.5円(445円):5.8倍
豆腐(100g) 7.17円(33円):4.6倍
タクシーの初乗りが100円の料金でした、現在は760円。。
② 第2次世界大戦と釣鐘
太平洋戦争時の金属供出により梵鐘が無くなってしまったため、戦後再鋳造された梵鐘。梵鐘にその旨が記録されている。 兵器の製造に必要な金属資源の不足を補う目的で公布された金属類回収令(昭和16年9月1日施行)により、官民所有の金属類は、装身具、鍋・釜から門扉、銅像、梵鐘などあらゆるものが根こそぎ回収された。
日本刀までその範ちゅうに入ったことを、子どもながら憶えています。
③ 諸行無常・・・・、について調べ、意味を知った。
≪仏法の大網である『三法印』の一つ≫
「諸行無常
是生滅法
生滅滅已
寂滅爲樂」
説いていることは、
この世の中のあらゆるものは変化・生滅してとどまらないこと。この世のすべてがはかないこと。全てのものが変化するものであることを知れば、安楽の境地に至ることが出来ると述べています。
読み方は
・ 諸行無常 (しょぎょうむじょう)
・ 是生滅法 (ぜしょうめっぽう)
・ 生滅滅已(しょうめつめっち)
・ 寂滅為楽(じゃくめついらく) と読むそうです。
ウィキペディアから出典
 と名づけたといいます。
と名づけたといいます。