「つながり」に寄せられた文章を読ませていただいた。あまりないことだが、何度もくり返し読むということをした。それは心がこもった文章のありがたさゆえだった。
読んで感じたことがいくつかあった。「つながり」とともに、最終講義の感想を含めてそれを書き留めておきたい。
「つながり」で圧倒的に多かったのは、私と野山を歩いたときに、私が動植物の解説をしたことでおもしろかったとか、それ以降自然の見方が違ったとかいう声だった。自分では伊沢整君が書いているように、独り言のようにしゃべっていたのだと思うし、覚えていないようなこともある。たぶん「ああ、きれいだ」というような感嘆詞と同列に、「この花の白さは、同じ白といってもちょっと透明感があるんだ」とか「ハナイカダというのは葉っぱの上に花を咲かせるのがおもしろいけど、名前も詩みたいだよね」といった類いの言葉が人によっては印象に残っているようだ。そういう説明もしたが、なぜこの植物がここに生えているかを説明するのに地形の話をしたり、降水量の話をしたり、これは何と言う蝶の食草だなどという話もしたに違いない。
この野外での解説が印象に残っているということそのものが私の持ち味だったのだということを確認できたような気がする。とくに神宮さんの文章はそのことを実によく伝えていてうれしかった。その点、よいのだかよくないのだかわからないが、講義がおもしろかったというのは、里山の話(神宮さん)や動物園のゾウの話(多田青加さん)くらいのものだった。
これに次いで多かったと思われるのは、誰にでも気さくに話しかけるとか、立場や出身などに関係なく親しくなるという類いのことだった。それは岩手県五葉山の調査のことを書いてくれた今栄君や金華山の調査のことを書いてくれた岡田さんなどに見ることができる。このことについて、私は自分をそのように意識したことはない。自分自身がマッカラーさんやガイストさんに会いにいって親しく話をしてもらったが、それで感激したということもあまりなかった。科学するということについてそれは当然のことだと思っていたから、「大先生」のそうした行いを特別ありがたいと思う必要はないと思ったし、自分が後輩や若い人と出会ったときも同じ仲間だと思っているので、自然にそうしてきたにすぎない。ありがたいことに、多くの人がそれをよろこんでくれているが、私に言わせれば、「大学の先生は威厳があって自分などに話をしてくれない」と思っている若い人が多いことのほうに違和感がある。無知ゆえにいきなりぶつかって、その結果否定されたら、そのときに「ああ大学の先生ってこういうものか」(実際にはそういうことは滅多にないはずだが)とがっかりすればよいのであって、初めからそのように思い込むのはよくないのではないか。少なくとも私はぶつかって、裏切られたことはなかった。
その意味で私は子供じみたほど単純にものごとに熱中する。それは単純だからなのだと思うが、純粋だととった人も多かった(瀧口君、海老原君、大津さん、藤本さん、嶋本さん、笹尾さん、安本さん)。
そういう私のいわば「直球」はセミナーなどでの直言になって表れる。これは私にとっては当然のことで、いっしょに自然から事実や真理を引き出そうとするのに遠慮は無用である。先生や先輩がまちがっていることもあれば、後輩が正しいこともある。当然のことである。ただそういう直言に不慣れな人はそれを毒舌と感じ、当然当惑し、ショックを受ける(辻君、内山さん、原さん)。ただ私の知る限り、しばらく時間が経てば、あるいは私の性格がわかれば、その真意が理解されたように思う。
多くの人が私を穏やかで優しいと書いているが(岡田さん、瀧口君、安本さん)、それはそうでもない。私は数は少ないが学生をきびしく叱ったことがある。それは「研究など適当にやっても大した違いはないんじゃないですか」という意味の発言をした学生と、自分を卑下して、他大学の先生に質問することをしなかった学生に対してであった。そのときはかなり強く叱ったのでよく覚えている。
一方、私が人の話をよく聞くということを書いた人もいる(樋口先生、岡田さん、瀧口君、安本さん)。これはそうでもないと思う。もちろんよく聞くつもりだが、重要な内容を聞いたときに、それを考え始めて、相手は次の話を始めたのに、その話は聞いていないことがときどきある。
瀧口君などは私が科学に厳しいと書いてくれているが、残念ながらやや買いかぶられている。いいかげんとは思わないが、合理的な範囲で妥協はよくしてきた。
東北大や東大ではなかったことだが、麻布大学の学生の多くは、1、2年の講義を聴いて私を「きびしくて、怖い」と思っていたが、研究室に入ったら意外にやさしく、おもしろいところもあってほっとしたということを書いている(伊沢君、八木さん、神宮さん、)。
私がよく歌をうたうと書いたものも多かった(樋口先生、嶋本さん、多田青加さん、八木さん)。確かに子供の頃からの習慣で野山を歩いているときは楽しくて鼻歌をうたうクセがある。自分では歌っている意識がないのだが、ふだん大学では気難しげな表情をしているのか、「意外におちゃめ」と感じた学生が多いようだった。確かに私は音楽が好きで、とくに歌は大好きといってよい。ただ東北大学の頃は大学でギターを弾くということはなかった(一度だけ今栄君や後藤君とミニセッションをしたが)。藤田剛さんが書いているように、東大の学生実習のときに津田君のギターで歌って以来だと思う。その後は忘年会などでよくセッションをして楽しんだ。あるとき、パワーポイントに写真と歌詞を書いて歌ったらわりあいよかったので、送別会などでそうすることがあった(嶋本さん)。樋口先生にはそのことが印象に残っていたようだ。麻布大学ではあまり吹かなかったが、リコーダーも好きで、東大時代はときどきリコーダーの好きな人がいて合わせた。茂田井さんや内海さんがそのことを覚えてくれていた。
私には理屈っぽいところと、歌に代表される芸術を好むという両方の面があり、絵を描くことも好きだ。そのことを書いてくれた人もいる(黒沢さん)。詩も好きだし(中川さん)、ときに短歌を書く(内海さん)。
私は文章を書くことも好きなのだが、そのことを書いた人は少なかった(木場さん、西野先生、伊藤文代さん)。わずかに黒沢さんが私の文章の構造を、姜さんが文体などをほめてくれた。
それから、私は「連絡をもらったのに返事をしない状態」を放置することができない。そのこと自体が「返事をしないでいる」ということを意味し、相手に申し訳ない気がしてしまうからだ。なので、手紙でもメールでも、もらったものを読みながら返事を考える癖がある。学生の原稿の添削もしかりで、どんなに長いものでも、英語原稿でもたいていその日のうちに返事をし、3日も放置できない。そのことを書いた人もいる(霜田さん、植原さん)。そのことを望月さんは「音速で帰ってくる」とユニークに表現している。
こうして読み返せばまことにありがたい思いがする。ただ、文集の成り立ちとして、寄稿した人は当然、よい印象や思い出を書いているに違いない。私がしたに違いない忘れ物やミスでご迷惑をおかけしたことはこの文集には書きにくかったため埋もれているはずだ(辻君は書いてくれたが)。それは一人一人の胸に刻まれているはずで、まことに汗顔ものであり、ありがたい文章の背後にあるそうしたことも読み取らなければならないと自分に言い聞かせている。
2015.4.28 記
読んで感じたことがいくつかあった。「つながり」とともに、最終講義の感想を含めてそれを書き留めておきたい。
「つながり」で圧倒的に多かったのは、私と野山を歩いたときに、私が動植物の解説をしたことでおもしろかったとか、それ以降自然の見方が違ったとかいう声だった。自分では伊沢整君が書いているように、独り言のようにしゃべっていたのだと思うし、覚えていないようなこともある。たぶん「ああ、きれいだ」というような感嘆詞と同列に、「この花の白さは、同じ白といってもちょっと透明感があるんだ」とか「ハナイカダというのは葉っぱの上に花を咲かせるのがおもしろいけど、名前も詩みたいだよね」といった類いの言葉が人によっては印象に残っているようだ。そういう説明もしたが、なぜこの植物がここに生えているかを説明するのに地形の話をしたり、降水量の話をしたり、これは何と言う蝶の食草だなどという話もしたに違いない。
この野外での解説が印象に残っているということそのものが私の持ち味だったのだということを確認できたような気がする。とくに神宮さんの文章はそのことを実によく伝えていてうれしかった。その点、よいのだかよくないのだかわからないが、講義がおもしろかったというのは、里山の話(神宮さん)や動物園のゾウの話(多田青加さん)くらいのものだった。
これに次いで多かったと思われるのは、誰にでも気さくに話しかけるとか、立場や出身などに関係なく親しくなるという類いのことだった。それは岩手県五葉山の調査のことを書いてくれた今栄君や金華山の調査のことを書いてくれた岡田さんなどに見ることができる。このことについて、私は自分をそのように意識したことはない。自分自身がマッカラーさんやガイストさんに会いにいって親しく話をしてもらったが、それで感激したということもあまりなかった。科学するということについてそれは当然のことだと思っていたから、「大先生」のそうした行いを特別ありがたいと思う必要はないと思ったし、自分が後輩や若い人と出会ったときも同じ仲間だと思っているので、自然にそうしてきたにすぎない。ありがたいことに、多くの人がそれをよろこんでくれているが、私に言わせれば、「大学の先生は威厳があって自分などに話をしてくれない」と思っている若い人が多いことのほうに違和感がある。無知ゆえにいきなりぶつかって、その結果否定されたら、そのときに「ああ大学の先生ってこういうものか」(実際にはそういうことは滅多にないはずだが)とがっかりすればよいのであって、初めからそのように思い込むのはよくないのではないか。少なくとも私はぶつかって、裏切られたことはなかった。
その意味で私は子供じみたほど単純にものごとに熱中する。それは単純だからなのだと思うが、純粋だととった人も多かった(瀧口君、海老原君、大津さん、藤本さん、嶋本さん、笹尾さん、安本さん)。
そういう私のいわば「直球」はセミナーなどでの直言になって表れる。これは私にとっては当然のことで、いっしょに自然から事実や真理を引き出そうとするのに遠慮は無用である。先生や先輩がまちがっていることもあれば、後輩が正しいこともある。当然のことである。ただそういう直言に不慣れな人はそれを毒舌と感じ、当然当惑し、ショックを受ける(辻君、内山さん、原さん)。ただ私の知る限り、しばらく時間が経てば、あるいは私の性格がわかれば、その真意が理解されたように思う。
多くの人が私を穏やかで優しいと書いているが(岡田さん、瀧口君、安本さん)、それはそうでもない。私は数は少ないが学生をきびしく叱ったことがある。それは「研究など適当にやっても大した違いはないんじゃないですか」という意味の発言をした学生と、自分を卑下して、他大学の先生に質問することをしなかった学生に対してであった。そのときはかなり強く叱ったのでよく覚えている。
一方、私が人の話をよく聞くということを書いた人もいる(樋口先生、岡田さん、瀧口君、安本さん)。これはそうでもないと思う。もちろんよく聞くつもりだが、重要な内容を聞いたときに、それを考え始めて、相手は次の話を始めたのに、その話は聞いていないことがときどきある。
瀧口君などは私が科学に厳しいと書いてくれているが、残念ながらやや買いかぶられている。いいかげんとは思わないが、合理的な範囲で妥協はよくしてきた。
東北大や東大ではなかったことだが、麻布大学の学生の多くは、1、2年の講義を聴いて私を「きびしくて、怖い」と思っていたが、研究室に入ったら意外にやさしく、おもしろいところもあってほっとしたということを書いている(伊沢君、八木さん、神宮さん、)。
私がよく歌をうたうと書いたものも多かった(樋口先生、嶋本さん、多田青加さん、八木さん)。確かに子供の頃からの習慣で野山を歩いているときは楽しくて鼻歌をうたうクセがある。自分では歌っている意識がないのだが、ふだん大学では気難しげな表情をしているのか、「意外におちゃめ」と感じた学生が多いようだった。確かに私は音楽が好きで、とくに歌は大好きといってよい。ただ東北大学の頃は大学でギターを弾くということはなかった(一度だけ今栄君や後藤君とミニセッションをしたが)。藤田剛さんが書いているように、東大の学生実習のときに津田君のギターで歌って以来だと思う。その後は忘年会などでよくセッションをして楽しんだ。あるとき、パワーポイントに写真と歌詞を書いて歌ったらわりあいよかったので、送別会などでそうすることがあった(嶋本さん)。樋口先生にはそのことが印象に残っていたようだ。麻布大学ではあまり吹かなかったが、リコーダーも好きで、東大時代はときどきリコーダーの好きな人がいて合わせた。茂田井さんや内海さんがそのことを覚えてくれていた。
私には理屈っぽいところと、歌に代表される芸術を好むという両方の面があり、絵を描くことも好きだ。そのことを書いてくれた人もいる(黒沢さん)。詩も好きだし(中川さん)、ときに短歌を書く(内海さん)。
私は文章を書くことも好きなのだが、そのことを書いた人は少なかった(木場さん、西野先生、伊藤文代さん)。わずかに黒沢さんが私の文章の構造を、姜さんが文体などをほめてくれた。
それから、私は「連絡をもらったのに返事をしない状態」を放置することができない。そのこと自体が「返事をしないでいる」ということを意味し、相手に申し訳ない気がしてしまうからだ。なので、手紙でもメールでも、もらったものを読みながら返事を考える癖がある。学生の原稿の添削もしかりで、どんなに長いものでも、英語原稿でもたいていその日のうちに返事をし、3日も放置できない。そのことを書いた人もいる(霜田さん、植原さん)。そのことを望月さんは「音速で帰ってくる」とユニークに表現している。
こうして読み返せばまことにありがたい思いがする。ただ、文集の成り立ちとして、寄稿した人は当然、よい印象や思い出を書いているに違いない。私がしたに違いない忘れ物やミスでご迷惑をおかけしたことはこの文集には書きにくかったため埋もれているはずだ(辻君は書いてくれたが)。それは一人一人の胸に刻まれているはずで、まことに汗顔ものであり、ありがたい文章の背後にあるそうしたことも読み取らなければならないと自分に言い聞かせている。
2015.4.28 記










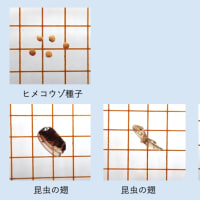

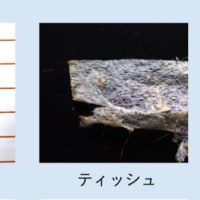






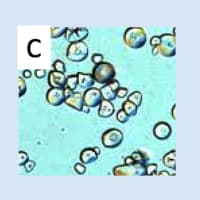






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます