藤田 剛
高槻先生が東大に在籍されていた時代には、いろいろなことでお世話になりました。そして、そのあいだに起こった、たくさんのことを思い出します。
その中でも、ぼくにとっての一番は、大学院生向けの野外実習を金華山島で行った際に、ご一緒してくださったことです。金華山での実習は、秋の中頃、10月か11月の秋にたしか3年間行い、その最初の年、高槻先生はすべての日程を一緒してくださいました。今でもこの5日間は、長く担当してきた実習の中でもとくにたくさんの思い出が詰まった実習のひとつです。
金華山は、房総でサルを追いかけていた学部生時代から、訪れてみたかった憧れのフィールドでした。シカやサルの個体数や分布のデータが長年にわたって記録されている。しかも、個体ごとの行動の観察も、個体群全体の動きを追跡することもでき、その動物の食べものになる植物の側の情報も同じようにしっかりと蓄積されている。個体レベルから群集まで動物と植物の関係を調べるのに、日本、いや世界でも最高のフィールドのひとつ、といった内容のうわさ話を何度も耳にしていたからです。
そして、そのフィールドを立ち上げた総元締め(?)の高槻先生と一緒に金華山に入れるのですから、これほど嬉しいことはない、と思ったことを今も覚えています。そして、張り切って、事前に一度下見をしたのですが、そのときに、実習のサポート役を担ってくれた当時修士2年の石黒真理子さん (当時は霜田さん) が、ちょうどぼくが金華山に着いた頃、調査中に頭に怪我をしてしまい、病院へ行くためすぐに本土へとんぼ返りすることになったことも、今となってはよい思い出です。ご存知のとおり、霜田さん無事でしたし、その翌日に金華山へもどったときは、嬉しさ倍増でした(霜田さんは、その人柄もあって、先生と並ぶ実習参加者の人気者になり、うやましかったことも思い出しました)。
さて、実習本番。実習の最初に、まる1日を使って金華山の山歩きをしました。先頭をきって歩く高槻先生の姿を頼もしく感じたのは確かですが、とくに、踏み固められた林道沿いに生えた小さな芽のようなイネ科の草本をみただけでいとも簡単に種名を教えてくださったことに、本当に驚きました。自分もいつか、こうなりたいと強く思ったのを覚えています。
参加者の中には、天野達也くん (現ケンブリッジ大) や天野麻里さん(当時は武田さん。現モーガンスタンレー)、西原昇悟くん(現保全生態学研究室) がいました。当時の学生たちは、実習期間中に実に豪快に飲んで騒いで、でも一生懸命に実習に参加してくれたと思っています。そんな学生たちのあいだに自然に入って楽しみ、無理をせずに、適当なところで抜けて休むというやり方も、先生から密かに学びました。そして、休むことを考えない学生たちは睡眠不足もあって、だんだんと弱って(?)いったのですが、そんな姿を余裕をもって見ることもできました (参加していた皆さん、もしこれを読んでいたらごめんなさい)。
実習は、グループに分かれて自分たちでテーマを見つけ、自分たちで方法を考えて調べそれをまとめて発表する、という流れでした。その山場である全グループの発表が終わったあと、ぼくはそれぞれの発表へのコメントを一通りしてから、どのグループも全体的によかったみたいな、ちょっと差し障りのないコメントをしました。しかし、高槻先生はちがっていました。「ぼくは、自分の好みをはっきり言うよ。このグループが面白かったなあ」とお気に入りのグループの着想と結果の面白さを説明されました。このとき、教育というか、自分の意見を人に伝えることとの、本質を教わった気がしました。これは、今もことある度に思い出す、大切なエピソードです。
そうそう、当時森圏管理に所属していた津田吉晃くんが、はるばる運んできたギターの腕も披露してくれました。そして、打ち上げで先生が、ファックスで送ってもらった楽譜を見ながら、ギターを弾きながら歌ってくださったこともよく覚えています。のちに研究室や専攻のイベントでは恒例になった高槻先生のギターと歌は、この津田くんのギターが始まりだったと記憶しています。そういう意味で、高槻先生の人生に少しだけ潤い(?)を加えるきっかけに関係できたことも、嬉しく思っています(勘違いでしたら、申し訳ありません。内緒にしておいてください…笑)。
その後の実習でも、辻大和くん(現京都大学)や黒江美紗子さん(現九州大学)、 吉原佑くん(現東北大学)たち、高槻先生門下の院生が頼り甲斐のあるサポートをしてくれました。これも、先生からいただいた間接的な恩恵でした。実習のことは、これくらいにしておきます。
最後に、先生のギターと歌で、一番うれしかったのは、樋口先生の最終講演のあとのパーティの時だったことをお伝えしたいと思います。たしか、山口由里子さんの本職の歌(これも凄かったですね)のあとに、本当にうれしそうにギターをかかえた高槻先生が登壇して、気の利いたお話で笑いをとってくださったとき、全体の場がすっと和んだことが印象的でした。そして高槻先生の歌に続いてみんなが歌いはじめた瞬間、高槻先生の人間力みたいなものを実感しました。そのときの、幸せな気持ちも、ぼくにとっては大切な思い出のひとつです。
金華山島を中心に進めて来られた高槻先生のフィールド研究の大きな業績とそれに取り組む先生の後ろ姿は、先生の元を巣立っていった多くの学生や院生たちにとって大きな目標になっていると、思っています。その先生が退官されるのは寂しくないと言えば嘘になりますが、それよりも、これから先生が何をされるのか、その期待の方がずっと大きいことも確かです。
高槻先生、退官おめでとうございます。
(東京大学大学院農学生命科学研究科)
金華山の実習にギターをもってきている学生をみて、「何を考えているんだ、この馬鹿たれ」と思って叱ってやろうと思っていました。しかしいっしょに山を歩くとなんとなく仲間意識が湧くもので、話を聞くと津田君は音楽の道と研究の道を迷ったほどの才能のもちぬしで、ギターを毎日さわらないと腕も耳も鈍るということでした。それで私も納得して、叱るのはやめましたが、最後の打ち上げのときにそのギターを独占していたのは私でした。その年の学生の忘年会に呼ばれて津田君のミニセッションをして大いに受けました。彼は私がどのコードで初めても耳で聞いてハイポジションで伴奏してくれました。私は歌には「マ」が一番大切だと思っていますが、私が少しテヌート気味に終わって次のフレーズに移るとき、心の中で「このマで初めてくれると理想的なんだけど」と思っても、たいがい微妙にずれるものですが、津田君は本当にぴったしでした。彼とのセッションは実に説明不要の「歌心」が伝わるものでした。「歌は音程ではない、心だぜ!」(高槻)。
高槻先生が東大に在籍されていた時代には、いろいろなことでお世話になりました。そして、そのあいだに起こった、たくさんのことを思い出します。
その中でも、ぼくにとっての一番は、大学院生向けの野外実習を金華山島で行った際に、ご一緒してくださったことです。金華山での実習は、秋の中頃、10月か11月の秋にたしか3年間行い、その最初の年、高槻先生はすべての日程を一緒してくださいました。今でもこの5日間は、長く担当してきた実習の中でもとくにたくさんの思い出が詰まった実習のひとつです。
金華山は、房総でサルを追いかけていた学部生時代から、訪れてみたかった憧れのフィールドでした。シカやサルの個体数や分布のデータが長年にわたって記録されている。しかも、個体ごとの行動の観察も、個体群全体の動きを追跡することもでき、その動物の食べものになる植物の側の情報も同じようにしっかりと蓄積されている。個体レベルから群集まで動物と植物の関係を調べるのに、日本、いや世界でも最高のフィールドのひとつ、といった内容のうわさ話を何度も耳にしていたからです。
そして、そのフィールドを立ち上げた総元締め(?)の高槻先生と一緒に金華山に入れるのですから、これほど嬉しいことはない、と思ったことを今も覚えています。そして、張り切って、事前に一度下見をしたのですが、そのときに、実習のサポート役を担ってくれた当時修士2年の石黒真理子さん (当時は霜田さん) が、ちょうどぼくが金華山に着いた頃、調査中に頭に怪我をしてしまい、病院へ行くためすぐに本土へとんぼ返りすることになったことも、今となってはよい思い出です。ご存知のとおり、霜田さん無事でしたし、その翌日に金華山へもどったときは、嬉しさ倍増でした(霜田さんは、その人柄もあって、先生と並ぶ実習参加者の人気者になり、うやましかったことも思い出しました)。
さて、実習本番。実習の最初に、まる1日を使って金華山の山歩きをしました。先頭をきって歩く高槻先生の姿を頼もしく感じたのは確かですが、とくに、踏み固められた林道沿いに生えた小さな芽のようなイネ科の草本をみただけでいとも簡単に種名を教えてくださったことに、本当に驚きました。自分もいつか、こうなりたいと強く思ったのを覚えています。
参加者の中には、天野達也くん (現ケンブリッジ大) や天野麻里さん(当時は武田さん。現モーガンスタンレー)、西原昇悟くん(現保全生態学研究室) がいました。当時の学生たちは、実習期間中に実に豪快に飲んで騒いで、でも一生懸命に実習に参加してくれたと思っています。そんな学生たちのあいだに自然に入って楽しみ、無理をせずに、適当なところで抜けて休むというやり方も、先生から密かに学びました。そして、休むことを考えない学生たちは睡眠不足もあって、だんだんと弱って(?)いったのですが、そんな姿を余裕をもって見ることもできました (参加していた皆さん、もしこれを読んでいたらごめんなさい)。
実習は、グループに分かれて自分たちでテーマを見つけ、自分たちで方法を考えて調べそれをまとめて発表する、という流れでした。その山場である全グループの発表が終わったあと、ぼくはそれぞれの発表へのコメントを一通りしてから、どのグループも全体的によかったみたいな、ちょっと差し障りのないコメントをしました。しかし、高槻先生はちがっていました。「ぼくは、自分の好みをはっきり言うよ。このグループが面白かったなあ」とお気に入りのグループの着想と結果の面白さを説明されました。このとき、教育というか、自分の意見を人に伝えることとの、本質を教わった気がしました。これは、今もことある度に思い出す、大切なエピソードです。
そうそう、当時森圏管理に所属していた津田吉晃くんが、はるばる運んできたギターの腕も披露してくれました。そして、打ち上げで先生が、ファックスで送ってもらった楽譜を見ながら、ギターを弾きながら歌ってくださったこともよく覚えています。のちに研究室や専攻のイベントでは恒例になった高槻先生のギターと歌は、この津田くんのギターが始まりだったと記憶しています。そういう意味で、高槻先生の人生に少しだけ潤い(?)を加えるきっかけに関係できたことも、嬉しく思っています(勘違いでしたら、申し訳ありません。内緒にしておいてください…笑)。
その後の実習でも、辻大和くん(現京都大学)や黒江美紗子さん(現九州大学)、 吉原佑くん(現東北大学)たち、高槻先生門下の院生が頼り甲斐のあるサポートをしてくれました。これも、先生からいただいた間接的な恩恵でした。実習のことは、これくらいにしておきます。
最後に、先生のギターと歌で、一番うれしかったのは、樋口先生の最終講演のあとのパーティの時だったことをお伝えしたいと思います。たしか、山口由里子さんの本職の歌(これも凄かったですね)のあとに、本当にうれしそうにギターをかかえた高槻先生が登壇して、気の利いたお話で笑いをとってくださったとき、全体の場がすっと和んだことが印象的でした。そして高槻先生の歌に続いてみんなが歌いはじめた瞬間、高槻先生の人間力みたいなものを実感しました。そのときの、幸せな気持ちも、ぼくにとっては大切な思い出のひとつです。
金華山島を中心に進めて来られた高槻先生のフィールド研究の大きな業績とそれに取り組む先生の後ろ姿は、先生の元を巣立っていった多くの学生や院生たちにとって大きな目標になっていると、思っています。その先生が退官されるのは寂しくないと言えば嘘になりますが、それよりも、これから先生が何をされるのか、その期待の方がずっと大きいことも確かです。
高槻先生、退官おめでとうございます。
(東京大学大学院農学生命科学研究科)
金華山の実習にギターをもってきている学生をみて、「何を考えているんだ、この馬鹿たれ」と思って叱ってやろうと思っていました。しかしいっしょに山を歩くとなんとなく仲間意識が湧くもので、話を聞くと津田君は音楽の道と研究の道を迷ったほどの才能のもちぬしで、ギターを毎日さわらないと腕も耳も鈍るということでした。それで私も納得して、叱るのはやめましたが、最後の打ち上げのときにそのギターを独占していたのは私でした。その年の学生の忘年会に呼ばれて津田君のミニセッションをして大いに受けました。彼は私がどのコードで初めても耳で聞いてハイポジションで伴奏してくれました。私は歌には「マ」が一番大切だと思っていますが、私が少しテヌート気味に終わって次のフレーズに移るとき、心の中で「このマで初めてくれると理想的なんだけど」と思っても、たいがい微妙にずれるものですが、津田君は本当にぴったしでした。彼とのセッションは実に説明不要の「歌心」が伝わるものでした。「歌は音程ではない、心だぜ!」(高槻)。














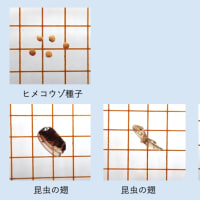

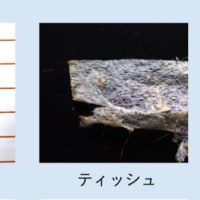









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます