2010年10月27日11時20分
『正月用のしめ縄作りを伝統産業にしている愛知県岡崎市大門地区の「大門しめ縄組合」の組合員たちが26日、地元の岡崎市立大門小学校www.tym.ed.jp/sc144 ) を訪ねて小学5年生128人に作り方を指導した。 藤江敏雄組合長(65)ら9人が手分けして、約15人ずつ8班に分かれた児童を受け持った。組合員たちは地元産のわらを使って、手順やこつをていねいに説明。子どもたちは悪戦苦闘しながら、自動車に飾る交通安全用の約30センチのしめ縄を仕上げていた。 江口夢実さん(11)は「最初は難しかったが、2本目にうまくできた時はすごくうれしかった」と話していた。 』
地元の伝統産業、地場産業のしめ縄作りを学べて良かったですね。農耕民族の日本に藁を生活に使って来ました。藁を編んで縄に今は出来る人も少なくなっているのではないでしょうか。環境にやさしく燃やしても有害ガス化でない人間に優しい藁を見直すべきです。「大門しめ縄組合」の組合員の皆さんに教えて貰い大門小学校の皆さんが失敗もしながら自動車に飾る交通安全用の約30センチのしめ縄を仕上げられて良かったですね。しめ縄作りから物を作る喜びの体験学習が出来ましたね。これからも。「大門しめ縄組合」の組合員の皆さん子供達に伝統産業を守り育てる為にしめ縄作りを今後とも指導して下さいね。
藁(わら)
[ 日本大百科全書(小学館) ]![]()
成熟した稲や麦の茎を乾かしたもので、稲藁、麦藁という。稲藁の成分はセルロース約36%、リグニン20%、ペントザン22%、粗タンパク質6%、灰分13%などである。これらは栽培作物としての稲、麦の副産物で、日本原産ではないが、古くから日本人の日常生活のなかでさまざまな形で利用されてきた。とくに稲藁は麦藁に比べて利用度が高く、各生活分野に使われており、日本の生活文化は稲藁の利用で特徴づけられるといっても過言ではない。日本での麦作の歴史は不明な点が多く、麦藁利用についての起源や歴史は解明されてない。一方稲藁は、縄文時代終末期に稲作が受容され、弥生(やよい)時代に定着・発展したのち、弥生終末期から古墳時代にかけて鉄製手鎌(てがま)が収穫具として使われ始め、刈り取りの条件が形成されることによって、多面的利用が可能となったと考えられる。すでにこれ以前から麻、シナ、コウゾなど自然繊維を加工・編織する技術が行われており、稲藁の利用はこうした技術を基盤に展開したといえよう。福井県鳥浜貝塚からは縄文時代前期の縄が出土しており、また日本の石器時代には縄文の施文体からわかるように目覚ましく縄が発達していたのである。
藁
稲藁の利用 利用法には、加工せずにそのまま用いる方法と、加工・編織する方法とがある。前者は燃料、飼料、牛馬舎や作物の根元への敷き藁、堆肥(たいひ)(積み肥)などへの利用であり、後者は藁細工、藁仕事での利用である。細かく刻んで土壁のツタ(
 (すさ))にするなどの利用法もある。稲藁は通常、米一石(約150キログラム)について120キログラム程度とれるといわれ、利用上ではこのうちの3割が藁細工に用いられた。藁細工による利用は世界の稲作地帯のなかでは日本がもっとも進んでいる。これは、稲藁はもろく風化しやすいが、軟質で加工しやすく、保温力に富み、稲作によって豊富に得られ、また日本型の品種は加工・編織に適すからである。農家での藁細工は原則として自家用の品をつくった。暮れまでに稲の収穫・収納を済ませ、正月の仕事始めから冬場の家内仕事としてこれを行ったのである。現在、各家庭では藁製品を日用品に使うことはほとんどないが、正月の仕事始めの儀礼にナイゾメなどといって縄を一房(いちぼう)なって年神様に供えたり、藁の打ち初(ぞ)めをすることが広く行われていた。藁細工が重要な仕事であったのがよくわかろう。
(すさ))にするなどの利用法もある。稲藁は通常、米一石(約150キログラム)について120キログラム程度とれるといわれ、利用上ではこのうちの3割が藁細工に用いられた。藁細工による利用は世界の稲作地帯のなかでは日本がもっとも進んでいる。これは、稲藁はもろく風化しやすいが、軟質で加工しやすく、保温力に富み、稲作によって豊富に得られ、また日本型の品種は加工・編織に適すからである。農家での藁細工は原則として自家用の品をつくった。暮れまでに稲の収穫・収納を済ませ、正月の仕事始めから冬場の家内仕事としてこれを行ったのである。現在、各家庭では藁製品を日用品に使うことはほとんどないが、正月の仕事始めの儀礼にナイゾメなどといって縄を一房(いちぼう)なって年神様に供えたり、藁の打ち初(ぞ)めをすることが広く行われていた。藁細工が重要な仕事であったのがよくわかろう。
冬の農閑期の藁細工では縄や草履(ぞうり)、草鞋(わらじ)、足半(あしなか)、背中当て、蓑(みの)、莚(むしろ)、俵、桟俵などがつくられた。おもに男の仕事で、近隣の若者がムロをつくり、集まって細工をしたり、藁打ちを共同で行う場合もあった。藁細工では、まず稲藁のスベ(下葉)をすぐりとり、先端のミゴを抜いて藁をこしらえ、さらに莚や俵など一部のものを除いては、藁打ち石の上で杵(きね)や槌(つち)で打ちこなして柔らかくして使うのが普通である。細工用の藁は早稲(わせ)種の水稲で乾田でつくったものがよいとされている。糯(もち)種の藁は粳(うるち)種より長く、しかも柔らかいので糯藁もよく使われた。日本の藁製品には先述のもののほかに、服飾品では編笠(あみがさ)、蓑帽子、藁手袋、脛巾(はばき)、踏俵、深沓(ふかぐつ)、藁沓、爪掛(つまがけ)、運搬具や容器では負縄(おいなわ)、縄袋、畚(もっこ)、扶畚(ふご)、叺(かます)、苞(つと)、生産用具では藁網、藁綱といった漁具、養蚕のマブシ、菰(こも)など、室内用具では藁ぶとん、敷莚、畳床、円座、えじこ、縄暖簾(のれん)、箒(ほうき)、台所用具では飯櫃(めしびつ)入れ、弁当入れ、釜敷(かましき)、鍋(なべ)つかみ、たわし、刷毛(はけ)、ベンケイなどがある。牛馬の沓も稲藁でつくり、さらに注連縄(しめなわ)、宝船、供物の容器である藁苞、ヤス、藁皿、七夕(たなばた)の藁馬、虫送りや道祖神の藁人形もある。これらのうち漁網・漁綱のようにじょうぶにつくらなければならないものや、細かい細工、外観を美しくつくるものにはミゴを選んで用いていた。
URLhttp://www18.ocn.ne.jp/~abc8181
プログランキングドツトネット http://blogranking.net/blogs/26928


















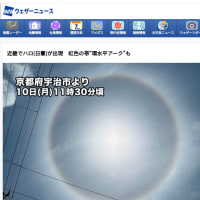
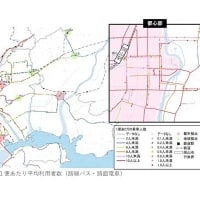
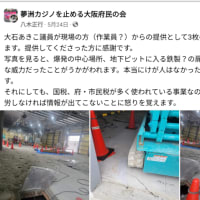
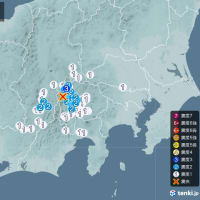







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます