15:02朝日新聞
『東京都大田区の区立中学校22校の進路指導担当教員計26人が、都内の私立高校から食事や酒、図書カードの提供を受けていたことが区教育委員会の調査でわかった。都教委は事実確認を進めると同時に、他の自治体でも同様のケースがないか調べている。
大田区教委によると、教員26人は昨年10月上旬、私立高の入試説明会に参加した際、会場で弁当や酒類の提供を受け、謝礼として配布資料に同封された2千円分の図書カードを受け取ったという。26人のうち4人は説明会後、飲食店での2次会にも参加したという。
都教委によると、生徒募集に関わる利害関係者からの供応は、懲戒処分の対象になる可能性がある。区教委の指摘を受けた教員らは昨年12月に私立高へ飲食代を支払い、図書カードを返したという。区教委は「疑念を招きかねない行為で、教員は提供されても断るべきだった。今後は指導を徹底する」としている。』
少子化による18歳人口減少による影響も有るでしょうが。教育界も付け届けが無いと駄目な世界で、どの地域も今更始まったことではなく、長年慣例化しているのが、現実ではありませんか。
『東京都大田区の区立中学校22校の進路指導担当教員計26人が、都内の私立高校から食事や酒、図書カードの提供を受けていたことが区教育委員会の調査でわかった。都教委は事実確認を進めると同時に、他の自治体でも同様のケースがないか調べている。
大田区教委によると、教員26人は昨年10月上旬、私立高の入試説明会に参加した際、会場で弁当や酒類の提供を受け、謝礼として配布資料に同封された2千円分の図書カードを受け取ったという。26人のうち4人は説明会後、飲食店での2次会にも参加したという。
都教委によると、生徒募集に関わる利害関係者からの供応は、懲戒処分の対象になる可能性がある。区教委の指摘を受けた教員らは昨年12月に私立高へ飲食代を支払い、図書カードを返したという。区教委は「疑念を招きかねない行為で、教員は提供されても断るべきだった。今後は指導を徹底する」としている。』
少子化による18歳人口減少による影響も有るでしょうが。教育界も付け届けが無いと駄目な世界で、どの地域も今更始まったことではなく、長年慣例化しているのが、現実ではありませんか。










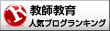



 JR各社(在来線)の人身事故の推移(写真:産経新聞)
JR各社(在来線)の人身事故の推移(写真:産経新聞) 



