1995年初恋を主題にした「Love Letter」と、2010年作の「スイート・リトルライズ」までに、15年の歳月が流れている。初恋を失った順子が、もし結婚して家庭を築くことができたら、スイート・リトルライズの新婚三年目に入った夫婦のようになる可能性はかなり大きいと思うと、面白い。まちがっても、かれらが「喜びも悲しみも幾歳月」(1965年作木下順二,佐田啓二・田中絹代主演)の灯台守夫婦のような人生はおくれない。これだけは確信をもって言いうる。また映画の主人公を演じた大森南朋(おおもり・なお)は、それだからこそ、この不倫映画の主人公として誰よりも適役として、存在感を発揮したのである。
大森南朋は、ぼくが日曜のゴールデンタイムに見入っているNHK大河ドラマ「龍馬伝」で武市半平太を演じてきた。先々週に切腹をさせられて死んだので、この後は登場しないのかもしれない。このドラマの前には2007年冬のNHK連続土曜テレビドラマ「はげたか」で、米国投資ファンド会社の日本支社長の辣腕ファンドマネージャー鷲津政彦を演じた。バブル崩壊で打撃を受けた日本企業を踏み殺すような取引条件で、つぎつぎに買収していく行為のため「はげたか」と呼ばれる。それを非難されると「お金を稼ぐことがいけない事でしょうか」と冷然と口にする。この返答の反論しようもない明快さ、どこかで質問者にざまーみろと感じさせるクールな鷲津の人間像に、ぞくぞくする快感を覚えたものであった。それはかれによる日本の現実批判でもあったからだ。かれは、かれなりの正義感が内面を押しとどめられていた。それを殺しながら、出てくる言葉でもあるからだ。しかし、しだいに、その正義感は、表面に現れてきて、最後には米国本社の命令を無視して大空電気の買収を強行、会社とそのその職人的技術者たちを救う。冷酷無常のファンドマネジャーに、しだいしだいに正義感、人間愛というのが、にじみ出てくることが快感であったのだ。それは、攘夷のテロを弟子たちに命令しながらも、ついに人間愛に屈して、藩主と妥協にいたる正義感のあり方とも同様であった。この疎外というよりもっと、もっと激しい内面の葛藤、その屈折をみごに表現する大森南朋の表現がきわめて説得力があった。その内面の奥の闇のような感じは、この映画の夫役でも十分に漂っていた。だが、なにゆえにかれは、葛藤する内面をかかえこんでいるのだろうか、きわめて分かりにくい。だから魅力もあるのだ。
この映画は、結婚して3年目の夫婦が、お互いに不倫してしまう。しかし俗に言われる「3年目の浮気」というようなそんな軽いものでないというモードで、えんえんと二人の生活が描かれる。あげくのはてに、夫も妻も浮気の相手と決別して、もとの日常に戻るまでの物語だ。それは、キャッチコピーによると、「人は守りたいものに嘘をつくの。あるいは守ろうとするものに。」という妻のことばで要約され、主題となる。一見意味深のコピー文言は、ありていに言えば「嘘も方便」という実もふたもない世間知に還元できるのであるが、そうとはならない、嘘も方便で納まるような世間知などではなく、とにかく内面の波立ちであるのだと言わんばかりだ。この心象を大森南朋は演じているし、監督もその内面表示に力点を置いている。しかし、なぜ嘘も方便という露骨な用語が似つかわしくなく「人は守りたいものに嘘をつくの」という思わせぶりなキャッチコピーが適切なのか。それはこの映画の基底にあるものが、まさに現実ではなくムードという虚構的現実の舞台であるからだ。
珍しく、この映画は昭和レトロの下町を舞台とせずに、中間所得者層が暮らしている住宅街で、瀟洒な白を基調としたマンション風住宅に囲まれ、二人の部屋のベランダからこの無国籍な住居群が風景となって眺められる。妻の趣味なのか、寝室はローソクの灯りをともし、朝起きると消すようになっている。ねじ巻きの柱時計とか、レトロな品物があちこちに置かれている。朝食には大きな白い皿にトーストやらバターやらがちょっぴり置かれたムード食である。コーヒーはサイフォン式で入られる。妻はテディベアの製作者で、これもレトロ作品だ。住宅はおそらく妻の好みによって、完璧なほどレトロ調カフェにされているのだ。夫はここから、IT関連会社に出勤していく。帰宅すると、自分の部屋に入り、液晶大型スクリーンのパソコンゲームとそのサラウンド大音響に包まれて時間を過ごす。夫と妻の連絡は、携帯電話が使用されている。ごく自然にまったく当たり前にである。
前回、ぼくはパソコンメールやインターネットがどの街にいようが、アメリカに暮らしていようが、距離感なく瞬時に連絡可能のショックを書いたが、隣室の夫とワシントンの知人との連絡がまったく同レベルであるとは、あらためて衝撃的な事実なのだと思えるのであった。隣室もアメリカ首都も距離感は消滅してしまうのだ。カフェと化してしまった夫婦の住居からは、生活のもつ実感ではなく、虚構というムード的生活が主体を動かしているのだ。しかし、夫も妻もそれに気づくことができない。なぜか。かれらは消費社会というブロイラー、もしくは飼育農場の主体的存在である牛や豚や鶏の生活を強いられているからである。その動物たちとおなじように運命を知りえないのである。飼育動物には餌が、人にはムードが与え、られつづけられる。
以下次回へつづく。
大森南朋は、ぼくが日曜のゴールデンタイムに見入っているNHK大河ドラマ「龍馬伝」で武市半平太を演じてきた。先々週に切腹をさせられて死んだので、この後は登場しないのかもしれない。このドラマの前には2007年冬のNHK連続土曜テレビドラマ「はげたか」で、米国投資ファンド会社の日本支社長の辣腕ファンドマネージャー鷲津政彦を演じた。バブル崩壊で打撃を受けた日本企業を踏み殺すような取引条件で、つぎつぎに買収していく行為のため「はげたか」と呼ばれる。それを非難されると「お金を稼ぐことがいけない事でしょうか」と冷然と口にする。この返答の反論しようもない明快さ、どこかで質問者にざまーみろと感じさせるクールな鷲津の人間像に、ぞくぞくする快感を覚えたものであった。それはかれによる日本の現実批判でもあったからだ。かれは、かれなりの正義感が内面を押しとどめられていた。それを殺しながら、出てくる言葉でもあるからだ。しかし、しだいに、その正義感は、表面に現れてきて、最後には米国本社の命令を無視して大空電気の買収を強行、会社とそのその職人的技術者たちを救う。冷酷無常のファンドマネジャーに、しだいしだいに正義感、人間愛というのが、にじみ出てくることが快感であったのだ。それは、攘夷のテロを弟子たちに命令しながらも、ついに人間愛に屈して、藩主と妥協にいたる正義感のあり方とも同様であった。この疎外というよりもっと、もっと激しい内面の葛藤、その屈折をみごに表現する大森南朋の表現がきわめて説得力があった。その内面の奥の闇のような感じは、この映画の夫役でも十分に漂っていた。だが、なにゆえにかれは、葛藤する内面をかかえこんでいるのだろうか、きわめて分かりにくい。だから魅力もあるのだ。
この映画は、結婚して3年目の夫婦が、お互いに不倫してしまう。しかし俗に言われる「3年目の浮気」というようなそんな軽いものでないというモードで、えんえんと二人の生活が描かれる。あげくのはてに、夫も妻も浮気の相手と決別して、もとの日常に戻るまでの物語だ。それは、キャッチコピーによると、「人は守りたいものに嘘をつくの。あるいは守ろうとするものに。」という妻のことばで要約され、主題となる。一見意味深のコピー文言は、ありていに言えば「嘘も方便」という実もふたもない世間知に還元できるのであるが、そうとはならない、嘘も方便で納まるような世間知などではなく、とにかく内面の波立ちであるのだと言わんばかりだ。この心象を大森南朋は演じているし、監督もその内面表示に力点を置いている。しかし、なぜ嘘も方便という露骨な用語が似つかわしくなく「人は守りたいものに嘘をつくの」という思わせぶりなキャッチコピーが適切なのか。それはこの映画の基底にあるものが、まさに現実ではなくムードという虚構的現実の舞台であるからだ。
珍しく、この映画は昭和レトロの下町を舞台とせずに、中間所得者層が暮らしている住宅街で、瀟洒な白を基調としたマンション風住宅に囲まれ、二人の部屋のベランダからこの無国籍な住居群が風景となって眺められる。妻の趣味なのか、寝室はローソクの灯りをともし、朝起きると消すようになっている。ねじ巻きの柱時計とか、レトロな品物があちこちに置かれている。朝食には大きな白い皿にトーストやらバターやらがちょっぴり置かれたムード食である。コーヒーはサイフォン式で入られる。妻はテディベアの製作者で、これもレトロ作品だ。住宅はおそらく妻の好みによって、完璧なほどレトロ調カフェにされているのだ。夫はここから、IT関連会社に出勤していく。帰宅すると、自分の部屋に入り、液晶大型スクリーンのパソコンゲームとそのサラウンド大音響に包まれて時間を過ごす。夫と妻の連絡は、携帯電話が使用されている。ごく自然にまったく当たり前にである。
前回、ぼくはパソコンメールやインターネットがどの街にいようが、アメリカに暮らしていようが、距離感なく瞬時に連絡可能のショックを書いたが、隣室の夫とワシントンの知人との連絡がまったく同レベルであるとは、あらためて衝撃的な事実なのだと思えるのであった。隣室もアメリカ首都も距離感は消滅してしまうのだ。カフェと化してしまった夫婦の住居からは、生活のもつ実感ではなく、虚構というムード的生活が主体を動かしているのだ。しかし、夫も妻もそれに気づくことができない。なぜか。かれらは消費社会というブロイラー、もしくは飼育農場の主体的存在である牛や豚や鶏の生活を強いられているからである。その動物たちとおなじように運命を知りえないのである。飼育動物には餌が、人にはムードが与え、られつづけられる。
以下次回へつづく。











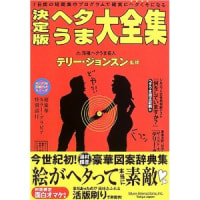












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます