ディートリッヒ・ボンヘッファー(Dietrich Bonhoeffer: 1906-1945)。(国際ボンヘッファー協会のサイト。)
ドイツの神学者。ボンヘッファーは、ヒトラーが政権を取った当初から、ヒトラー批判を公にしていた。キリスト教徒によるナチスに対する抵抗運動「告白教会」に加わった後、亡命のために米国に渡る。しかし間もなく身の安全を省みず、ドイツへときびすを返す。そしてヒトラー暗殺計画に加わった。計画は失敗に終わって、捕えられ、終戦のわずか1月前に処刑された。
ドイツで「教会アジール(Kirchenasyl)」の調査をしているとき、さまざまなところでこのボンヘッファーの名に接した。礼拝の説教で頻繁に引用される。またある教会に併設された文化センターは「ディートリヒ・ボンヘッファー・ハウス」と名づけられている。別の教会に牧師さんを訪ねると、オフィスの机上にボンヘッファーの本が置かれていた。
昨年9月にベルリンで滞在したときには、この人についてちゃんと調べてみようと、キリスト教専門書店に行った。するとボンヘッファーのコーナーが設けられていて、たくさんの本が並んでいた。今年で生誕100年だから、それを記念する出版物も出始めていた。今ではもっと増えているだろう。
ボンヘッファーという人物への関心は、少なくとも僕が知り合ったドイツ人のキリスト教関係者の間では非常に高いようだ。彼らはボンヘッファーに、ナチス以後、もしくはホロコースト以後のドイツで、キリスト者として生きるモデルを求めているのだろう。
かつてドイツの多くのキリスト教徒はナチスに迎合し、ユダヤ人への暴力に見てみぬ振りをし続けた。そんな中で、ボンヘッファーはヒトラーの危険を当初から見抜き、そのユダヤ人政策を批判し、最後には文字通り命をかけてナチスという「暴走する車を止めようとした」。なぜそれが可能だったのか。そう現代ドイツのキリスト者は真摯に問い、その答えを実践に結び付けようとしている。
「他者のための教会」が、ボンヘッファーの一つのキーワードだ。調べていくと、ボンヘッファーが「他者」という概念を神学に導入したことは実はすごいことだということが分かってきた。ここで「他者」にはユダヤ人も含まれている。反ユダヤ主義は、ヨーロッパのキリスト教を母胎に育っていった側面がある。ユダヤ人は、ヨーロッパがキリスト教化される中で、神学的にそして社会的に排除の対象とされてきた。だからボンヘッファーのこのテーゼは、キリスト教の世界できわめて異彩を放っているのだ。第二次世界大戦後のキリスト教徒とユダヤ人との和解は、ボンヘッファーのこの立場を一つの基礎に展開したようだ。
ボンヘッファーの「他者」概念は、真剣に検討する価値がある。バフチン、レヴィナス、サイードらの他者概念と比べてみるとどうだろうか。また文化人類学を「他者」に関する学問と規定するとき、ボンヘッファーから何を学ぶことができるだろうか。
ボンヘッファーに関する日本語の本として、村上伸氏による伝記『ボンヘッファー』(清水書院)は読み応えがあった。ボンヘッファーは「汝殺すなかれ」を戒めとするキリスト者であり、かつ非暴力主義者ガーンディーの影響も受けていた。それなのになぜ彼は、独裁者ヒトラーとは言え一人の命を奪う計画に参画したのか。村上氏はこの問いと正面から格闘している。その考察を読み進めることは非常にスリリングな体験であった。
ボンヘッファーの伝記としてスタンダードなものはベートゲ(Eberhard Bethge)による"Dietrich Bonhoeffer: Eine Biographie"(邦訳『ボンヘッファー伝』)だ。このベートゲは、ボンヘッファーの姪の夫であり、戦後、キリスト教神学と反ユダヤ主義との関係を反省する作業を推し進めた人物だ。
ボンヘッファーのほとんどの著作は邦訳されているようだ。「他者のための教会」というテーゼは、ボンヘッファーが獄中で書いた草案の一部であり、村上伸氏が精魂込めて完成した訳書『ボンヘッファー獄中書簡集「抵抗と服従」増補新版』(新教出版社、1988年)の439ページに収められている。
日本では、上記の村上伸氏の他に、雨宮栄一氏、森野善右衛門氏、宮本光雄氏らによってボンヘッファー(および「告白教会」とドイツ教会闘争)の研究が進められてきた。僕は不勉強でその多くを読んでいない。わずかに目にしたもののうちでは、雨宮氏の『ユダヤ人虐殺とドイツの教会』(教文館)が印象に残った。何よりこの方のポジショニングに共感を覚えた。現場に立脚しながらの研究なのだ。「あとがき」から引用させていただこう。
「この書物の執筆は牧会、伝道は当然のことながら、筆者の居住するこの地域の在日外国人の指紋押捺制度撤廃運動、あるいは山谷兄弟の家伝道所の住民支援活動に参加しながらなされた。学者の静かな書斎の産物ではない。この貧しい書物に、もしもかりに誇りうるところがあるとするならば、教会に仕える一人の牧師が、地域の人権問題へのささやかな取りくみから、これが生まれたというところにあるのかも知れない。」(p.274)












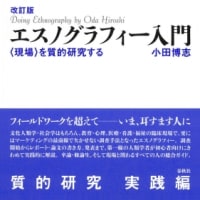








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます