このブログ、さきほど40,000カウントを越えました。ごひいきにしていただいてありがとうございます。ホームページの方ももうすぐ40,000越えです。
ずいぶん更新ができませんでした。ベルリンから戻ってすぐに新学期に突入。息つく暇も無い毎日でしたが、ようやく落ち着いてきました。
半年間の海外生活で印象に残ったことは数あれど、アフリカ(ナミビア)の体験はとても強烈でした。ヨーロッパ(ドイツ)が違って見えてきました。それでこのところ、アフリカや植民地主義関係の文献を読むことが多いです。
その中で、『新書アフリカ史』(講談社現代新書)のレベルが高い。一般啓蒙書の域を越えて、ヨーロッパから一方的に「歴史が無い」と言われてきたアフリカの歴史を書くという試みにチャレンジして、それに成功していると思います。
それから、ナミビアを占領支配していた南アフリカの概要を知ろうと手に取った『南アフリカ―「虹の国」への歩み』(峯陽一、岩波新書)も簡明で高水準な好著でした。
専門書としてとりわけ重要だと思ったのが『「植民地責任」論』(永原陽子編、青木書店)。
「戦争責任」という概念はすでに人口に膾炙しています。ところが、二つの世界大戦をはじめ20世紀の主要な戦争の一要因は、日本も含めた列強の植民地獲得競争です。植民地にされた地域の人々は、土地を収奪され、強制・奴隷労働に駆り出され、人種差別を受け、文化を破壊され、恣意的な境界線で分断され――と過酷な運命を強いられたのでした。
ほとんどの旧植民地が国家として独立した今でも、そのつけを支払わされています。その責任を、旧宗主国(イギリス、スペイン、オランダ、フランス、ベルギー、ドイツ、日本…)がどう取っているのか、かねがね疑問でした。この問いに正面から取り組んだのがこの『「植民地責任」論』です。
現状では旧宗主国はその植民地責任をほとんど取っていないという答になってしまいます。しかし、旧植民地側からの責任追及の声は強くなっていき、無視できなくなるでしょう。その声は、例えばこういう声です。「「人道に対する罪」の概念で第二次世界大戦中の蛮行が裁かれたが、われわれが受けた被害はどうなるのか?」
この声に応答しようとするとき、本書で提起されている「植民地責任」の概念は重要な里程標となるでしょう。












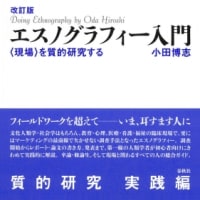







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます