アントニオ猪木は本当に強かった。だから、ハルク・ホーガンのアックスボンバーで舌を出して失神負けしたときはショックだった。長州力にリキラリアットで倒され、フォール負けしたときもそうだった。珍しく『ニュースステーション』で結果を報じた藤波辰巳との一騎打ちも、興奮しながら観た。だが、それらはすべて、結果の決まったショー、いわゆるプロレスであった。
柳澤健『完本 1976年のアントニオ猪木』(文春文庫、2009年)は、そのことを淡々と検証するように書いている。解説で海老沢泰久が述べているように、これは歴史書なのかもしれない。
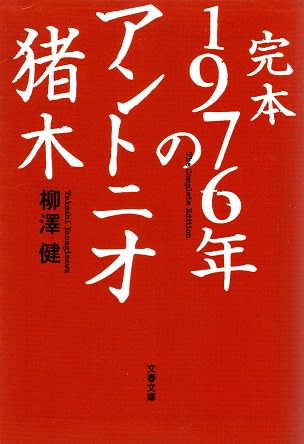
なぜ1976年なのか。答えは、その年にのみ、リアルファイトが行われたからである。世界の英雄でありムスリムの英雄であるモハメッド・アリ、韓国の英雄パク・ソンナン、パキスタンの英雄アクラム・ペールワン。アリ戦が「世紀の凡戦」と酷評されたように、リアルファイトであったからこそ、盛り上がりに欠け、異常な試合となった。これ以降の猪木は、再び「プロレス」に戻ったというのが、著者の主張だ。
いまさらプロレスがショーであることくらい、誰でも知っている。だからと言って、プロレスラーが弱いということにはならない。相手の技を受けてやり、それに対して変奏曲を奏で、互いのプロセスを高めていく。これを猪木は「○○○○と同じだ」と表現した。あるいは、ソロの順を決めたところでジャズはヤラセではない、そのこととも似ている。
それでも、歴史として断言されてしまうと、わかっていたにも関わらず何だか幻想を剥ぎ取られて痛い。デューク・エリントン風にいえば、世の中には2種類の人間がいる。プロレスを認める人間と認めない人間だ。私は前者である。わかっていながらも幻想を楽しんでいるのだ。だから、ハッスルのようなショー性を前面に押し出す試みは、幻想を持つことが許されないものであるから、観たくも何ともないわけである。こればかりは、少年時代、新日本プロレスの中継に毒されてしまったから仕方がない。(何しろ、初代タイガーマスクの実家に電話をかけてしまったことも・・・。)
初めて聞く話はいろいろある。ホーガンとの試合での失神は、プロレスの凄さを演出するための猪木の芝居だった。アリとの試合があのような形になったのは、猪木がカール・ゴッチからタックルを教わらなかったことも原因のひとつであった。勿論、本当かどうかわからないし、おそらくはアリとの試合の分析は数限りない人たちによってなされていて、無数の見解があるのだろう。
それ以上に興味深いのは、プロレスを支えた大衆の幻想と、それを利用した権力の動きだ。日本のプロレスは、右翼や暴力団と密接な関係にあった。韓国のプロレスは、朴正煕に利用され、保護された。パキスタンのプロレスは、ムガル帝国に仕えるレスラーの末裔であり、やはり政治と深い関係にあった。そして猪木は、1976年のリアルファイトにより、韓国のプロレスも、パキスタンのプロレスも、その後の凋落に追い込んでしまった。逆に日本では、不思議なことにプロレスを切り離さない形での総合格闘技興隆の流れをつくった。
ここまで冷静にプロレスの歴史を振り返られても、なぜかプロレスを観たくなってしまうのが不思議である(とは言え、もはやプロレスよりもノゲイラやヒョードルのほうを観たいのだが)。著者も冷静を装いつつ、プロレスという偉大な演出空間を愛しているようだ。その本当の気持ちは、以下の文章に表れている。
「ヒールが常識から逸脱した行為を行うことで、観客の中に興奮が生まれる。
ベビーフェイス(正義の味方)がヒールを罰することで正義が回復され、観客は満足する。
どちらの役回りがよりクリエイティブかといえば圧倒的にヒールである。そもそも興奮が生まれなくては鎮めようがない。
ヒールとベビーフェイスの関係は、推理小説における犯人と探偵の関係に近い。正義の味方である探偵(ベビーフェイス)は、犯人(ヒール)の思考と行動の筋道を後追いすることしかできない。
事件のすべてを作り出すのが犯人であるように、プロレスのアイディア、物語、言葉のすべてを握っているのはヒールなのである。」




















