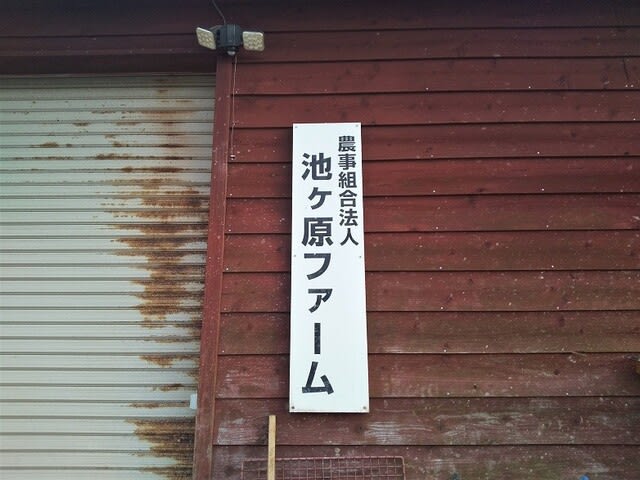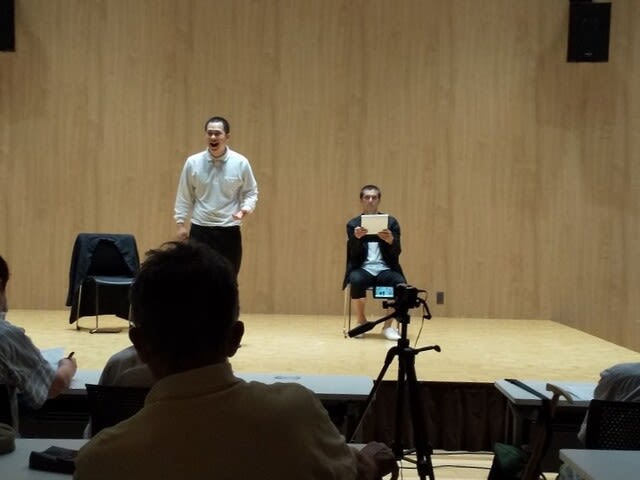<前回投稿の続篇>
一夜明けた2023年8月14日の朝、僕は大津市から北へハンドルを切った。
目指すは、滋賀県の南東部に位置する「東近江市(ひがしおうみし)」。
「滋賀県平和祈念館」が目的地である。

ここにお邪魔するのは2度目。
前回は、周辺をドライブ中に偶然同施設の看板を見つけてやって来たが、
今回は、ちょうど終戦記念日間近のタイミングでもあり、
実に10年ぶりの再訪となった。
「滋賀県平和祈念館」の芽吹きは、ある男性の体験と思い。
1960年5月、日本遺族会の戦地巡拝行事に後の滋賀県知事が遺族の一人として参加。
彼の父は、中部太平洋方面に派兵され、戦死していた。
その時の立ち寄り先の一つ、沖縄戦最後の激戦地で住民や兵士が自決した洞穴を訪問。
数多くの遺骨が残り、頭蓋骨はまるでこちらをぐっと見据えているかのように感じ、
帰りの船上では、海の底から戦死者の叫びが聞こえてくるように思えたとか。
父亡き後の母の苦労、息子を失った祖父の悲しみを傍で見聞きしていた彼は、
1998年から2期務めた知事時代、
「戦時の様子を正確に伝え、平和を祈念し続ける拠点が必要」と訴えた。
折からの財政難もあり任期中に実現はしなかったが、後を継いだ首長が継承。
東近江市役所の旧支所を再利用することで2012年、開館にこぎつけた。

館内では滋賀県内自治体別の戦没者、軍事施設、学童集団疎開などをパネルで紹介。
戦争体験者49人が語る映像も上映されている。
様々な展示がなされていて、すべてを紹介することは叶わない。
以下にほんの一端を取り上げてみようと思う。

信楽焼の陶製地雷と手りゅう弾。
戦時中、信楽の製陶業は危機に瀕していた。
火鉢や置物などの民生品は「不要不急」とされ、生産が中止されたのである。
そこで産業存続のため、軍部に金属探知機に反応しない陶製地雷を進言。
これが採用され、戦争末期に製造を開始。
物資不足を反映した手りゅう弾用陶製容器も手掛け、
沖縄や硫黄島などの激戦地でも使用されたという。

灯火管制マニュアル。
戦時中の夜、空襲の目標にならないようにと屋内の光を外にもらさない灯火管制が敷かれた。
真下だけ明るく照らすように塗料を塗った電球を使ったり、
黒い布で電灯の周りを囲んだり、電灯カバーをかぶせたり、窓に黒いカーテンを引いたりした。
しかし、米軍機にとって何ら支障はなかった。
灯火管制で真っ暗な市街地は、レーダーで丸見え。
夜間の空襲で膨大な犠牲者が出ていることはご存じの通り。
灯火管制は「戦争参加意識(戦意高揚)の演出」に過ぎなかった。

赤紙(召集令状)複製。
徴兵検査の結果現役兵とならなかった人や、除隊後に予備役になっていた人など、
在郷軍人に召集をかける際に発行された。
郵送ではなく、役場の兵事係が直接家まで届けるのが習わし。
「召集令状をもってまいりました。おめでとうございます」
紋切り型の口上と共に差し出された書類の受け取り拒否は許されない。
「おお、俺にも来たか。待っていたぞ」と意気込んでみせる人。
「これで肩身の狭い思いをしないですむ」と言い目を赤く腫らした父親。
「ご苦労さまでした」と言ったきりじっと赤紙を見つめた新妻。
縦15センチ、横23センチの薄紅色をした質の悪い紙は、
無数の物哀しいドラマを内包している。
他にも充実した展示が並ぶ「滋賀県平和祈念館」は、何と観覧無料。
素晴らしい。
更に、企画展も行っている。
第33回のそれは「滋賀県民が見た中国の戦場」。
<中国との長期にわたる戦争では、滋賀県からも多くの方が召集されて戦場に赴きました。
昭和初期、中国(当時の満洲国を含む)で戦死された滋賀県民は、7千人以上にのぼります。
また、慰問などのために中国戦線を訪ねられた滋賀県民もおられます。
今回の展示では、当時の中国やその周辺地域において、
滋賀県民が体験した戦争に関する記憶を、
当館が長年にわたり収集してきた関係者の体験談や関連資料などで紹介します。>
(※< >内「滋賀県民が見た中国の戦場」紹介文)

中華国恥(こくち)掛図。
発行年が書かれていませんが1930年前後に中国で作られた地図と考えられます。
この当時、何種類もの国恥地図が発行されており、
欧米諸国や日本によって奪われた範囲を図示して、
国民教育に利用されたもののようです。
(※展示に添えた短いキャプションから引用)
北は満州全域~ロシア極東~樺太。
東は沖縄~南西諸島。
南は台湾~インドシナマレー半島~ボルネオ北部までをカバーしている。

満州国 国旗。
かつて現在の中国東北部にあった「満洲国」は、
戦前~戦中にかけ日本が莫大なカネと人を投じた政治的、経済的、軍事的な拠点。
その国旗は5つの色からなる。
黄色は満州の大地、王の仁徳。
赤は火と南方、熱情などの諸徳。
青は木と東方、青春・神聖を。
白は金と西方、平和・純真公儀を。
黒は水と北方、堅忍・不抜の諸徳を表す。
黄、紅、青、白、黒が、日・満・漢・朝・蒙の五族協和を象徴するという説もあり。
今回、初めて実物を目にした。
そして、初めて存在を知った過去の施設がある。
「八日市飛行場」だ。

大正3年(1914年)現・東近江市・沖野に日本初の民間飛行場が開設された。
大正11年(1922年)陸軍航空第三大隊が配備され軍用施設へ変貌を遂げ、
戦時中にも拡張が続き、終戦間際には特攻隊の中継基地として重要な役割を果たす。
八日市飛行場も米軍の爆撃を受けるようになると、
貴重な飛行機を守るためのシェルター「掩体壕(えんたいごう)」が築かれた。
まだ、一部が残っているというではないか。
僕は現地へ向かった。

それは、旧八日市飛行場の南に位置する丘陵地、細い道沿いの藪の中ににあった。
立地が私有地のため、これ以上近付くことはできない。
やや離れた位置から観察し、シャッターを切った。
案内看板によると掩体の鉄筋は非常に少なく、コンクリートに沢山の石が混ざるなど、
物資不足の中で造られたことが分かる。
それは、当時の日本軍がいかに追い込まれていたかを示す無残なモノ。
同時に、それでも何とかしようとした先人達の努力の跡でもあるのだ。
ひっそり佇む出来損ないの施設は、僕の胸を打った。

--- さて、半日以上の観光を終え「びわこ競艇場」へ舞い戻る。
上空は前日(2023/08/13)とは打って変わり一面の厚い雲。
台風7号接近の影響だ。

主宰者は既に翌日の中止順延を発表。
帰りの道中を心配しながらもレース予想を楽しんだ。
まあまあ的中が多く、胸を撫で下ろす。
また、嬉しかったのはガラポン抽選。
この場での好物「ホルモンうどん」を食べたところ、抽選参加券を1枚もらう。
それを手に抽選機を回すと青い玉がポトリ。
景品は、現金3,000円。
いい旅の締めくくりになった。