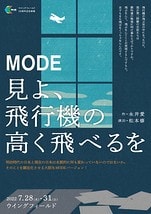
ウイングでこういう大作を見られるというのはうれしい。それってほんとに久しぶりのことだ。コロナ禍で作品自体も減っていたし、公演される芝居はどうしても少人数の上演時間の短い作品が中心になる。堂々たる大作は、狭い空間で密になるここではリスクがあまりに大きすぎるからだ。だからこれは久々の試みとなる。2時間45分(休憩10分を含む)、20名に及ばんとするキャストが見せる大作。
以前、この戯曲を吉田美彦先生が劇団大阪で手掛けた作品を見た。確か4,5年前のことだ。あの芝居はとても素晴らしかった。若いキャスト達の輝きがまぶしい。キラキラした芝居だった。定年退職まで高校生たちとずっと芝居を作り続けてきた彼だからこそ作れる初々しい作品で、それをベテラン集団である劇団大阪が手掛けたという妙。教師陣はもちろん劇団大阪のメンバーが演じた。舞台中央に階段を配して、その上下運動や、広い空間(会場は一心寺シアター倶楽)を縦横に使うことで、まず、彼女たちの若々しさ、生き生きした姿が活写された。少女たちはそこで自由に学園生活を謳歌する。だが、お話は徐々に彼女たちの置かれている世界は自由ではなく、さまざまな制約を持つことが明確になっていく。そんな中で少女たちがいかに戦うことになるのか、それが描かれていく。
だが、今回はウイングである。この狭い舞台では同じような見せ方はできない。だからMODEの少女たちは、最初からあまり無邪気ではない。抑えられている。本作は、結果的にこの閉ざされた学園での少女たちの苦悩にスポットを当てて描いた。彼女たちが挫折する姿を静かに見せていく。徐々に追い詰められていくさまがゆっくりとしたテンポで描かれる。終盤の運動会のシーンが象徴的だ。ふたりきりのストライキのむなしさ。明るい陽ざしの中で、みんなは楽しそうに運動会をしている。エリート集団であるこの女子師範学校の女の子たちは自分たちの力を過信している。優しい先生たちに囲まれて、自分たちが世界を変えることができるのだと夢想する。でも、所詮は籠の中の鳥でしかない。
芝居は終始冷静で静かな会話で綴られる。(最初の部分は少しはしゃぐが、それは台本がそうなっているのだから仕方ない)この松本修演出による作品は、吉田作品のようなハイテンションではないのだ。同じ台本を使いながら両者では描こうとするものが微妙に違うことは明白だろう。そこが面白い。衣装も明治時代のものではなく現代のままで演じる。彼女たちの話す言葉とその衣装との間にはかなりのギャップがあるはずなのに、なぜか自然で違和感はない。そこが不思議だ。これは遠い過去の時代のお話ではなく、どこででもない、どこにでもある普遍的な出来事としてこの物語では語られていく。彼女たちの敗北を静かに受け止める。でも、それはなぜか清々しい。そんな芝居だった。

























