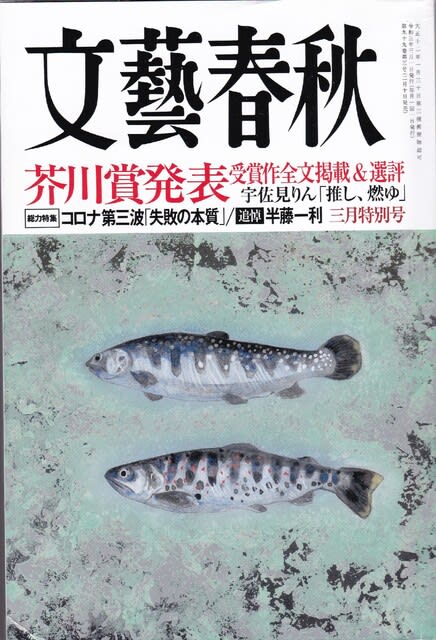小川洋子の「密やかな結晶」を読み直す。といっても、以前読んだのは、私がまだ大学生の頃だったと思う。その時は、ハードカバーの分厚い新刊を購入したのだが、それがいつの間にか手元から離れてしまい、上の写真は新しく買った文庫本。
でも、それも何年も前で、長いストーリーを読みきることができず、途中やめにしてしまった……なのに、最初に読んだ時の鮮烈な感動は強く、ストーリーも物語の雰囲気もくっきり覚えていたもの。
コロナで、私たちの住む地方はかなり深刻な状況に陥っている――外出も思うようにできない日々、ふと、この本のことを思い出し、門の横の小さな小屋にある本棚から取り出してきた。
ストーリーは、それこそ密やかで、どこか諦めに似たムードが全体を支配している。はじめ、これを読んだ時はディストピアという表現こそは浮かばなかったものの、北欧の静かで寂寥感に満ちた映画のシーンを思い浮かべてしまった。
どこかにあるはずの島が舞台なのだが、ここでは秘密警察という恐ろしい機関が存在し、島の人々を監視している。この島では一つずつ、何かが消滅し、人々はそのなくしたものの記憶さえも失ってしまう。時に、消滅の記憶を失わない人たちがいて、秘密警察はその人たちを連行し、抹殺する。そして、消滅したものも、すべて消去するのが彼らの仕事だ。
主人公の「わたし」は若い作家の女性なのだが、彼女も一つ一つ記憶を失ってゆく。胸に空洞がぽっかり開いてゆくのを自覚するものの、それをどうすることもできない。「わたし」の母は彫刻家だったが、記憶をなくすことができないため、秘密警察に連行され殺されてしまった――そんな彼女の心の支えは、両親が健在だった頃から家に出入りしていた、器用で心優しいおじいさん(もと、フェリーの運転手)。
このわたしとおじいさんの心の交流が、繊細な優しさに満ちていて、それがこの沈んだ物語を導く灯りとなっている。わたしは、自分の小説の最大の理解者である編集者Rが、記憶を失うことができない人間の一人であることを知る。このままでは、秘密警察の「記憶狩り」に追われてしまう。だから、おじいさんの手を借りて、自分の家の秘密の小部屋に彼をかくまうのだが、島から大事なものは、どんどん消滅してゆく――というのが、大体の筋。
ここに登場する「秘密警察」が、ナチスそっくりであることや、彼らの「記憶狩り」の有様はユダヤ人抹殺を思わせることは、この物語を読んだ人には一目瞭然のはず。おじいさんは途中で死ぬし、「わたし」も最後には自分自身を消滅させてゆくしかない。けれど、こんな希望のない話であるはずなのに、この「密やかな結晶」はとても美しく、いつまでも、この世界に身を浸していたいとさえ思わせるほどだ。
これは、小川洋子の文章の魔力のせいなのだろう。「わたし」がストーブの上で煮るシチューや、乏しい野菜で作る料理。半地下となった洗濯室や、母親の遺品の彫刻――すべての描写が、キラキラするというのではなく、真珠の光沢を思わせるほのかな輝きに満ちているのだ。
おじいさんと、彼の住んでいたフェリーが海に沈みかけているのを見ながら交わす会話さえ、何とも言えず素晴らしい。
北の物憂い海と、深い静けさに満ちた島の情景が目に浮かびそうなほど。「わたし」もおじいさんも現状に対して怒り狂うということはなく、静かな諦念を抱いているかのよう。
世界が終わる時というのは、阿鼻叫喚すさまじい光景がある訳ではなく、こうした沈んだ色に包まれているのかもしれない。
と、ここまで読んでいて、気が付いてしまった。この「密やかな結晶」を何十年ぶりかに読み返したくなったのも、この島で消滅するということに耐えながら、生きている「わたし」やおじいさんの状況が、今のコロナ禍に重なる部分があったからだと、いうことに――。
だからこそ、この作品が昨年ブッカー賞の翻訳部門にノミネートされたのだと思う。(発表されてから、三十年近くも経つというのに)