去年の夏、東京言語研究所の夏期講座で早稲田大学の福澤一𠮷先生の講義を聴く機会がありました。その内容は『議論のレッスン』という本にまとめられています。それをもとにしながら意見文を書く指導の参考にしています。
よく意見を書くときにはその根拠をしめしなさいと指導します。意見だけでは論理的な文章になりません。必ず根拠が必要だと教えるわけです。それに対して福澤先生の主張はその根拠の部分を「根拠」と「論拠」に分けます。
「根拠」は事実です。意見が生まれるそのもとになる事実です。「論拠」はその「根拠」から「意見」にいたるまでの中間のものにあたります。これは事実ではありません。あくまで主張者の考え方が示されるものです。
わかりにくいと思われますので、具体例で説明します。
「昨日はラーメンを食べた。だから今日はカレーを食べよう。」
という文において「昨日はラーメンを食べた。」という部分は事実であり、「根拠」になります。そして「今日はカレーを食べよう。」は意見になります。実はここには「論拠」が隠されています。「2日連続でラーメンは飽きる。」という内容です。これが論拠になります。
根拠 昨日はラーメンを食べた。
論拠 2日連続でラーメンは飽きる。
意見 今日はカレーを食べよう。
この論拠は事実ではありません。事実から生じる発言者の判断です。だから同じ根拠でも論拠の部分を変えれば別の意見になりえます。
根拠 昨日はラーメンを食べた。
論拠 ラーメンはおいしい。
意見 今日もラーメンを食べよう。
上記の意見も十分成立するものです。同じ根拠でもまったく別の意見が生まれてきます。そこには「論拠」という意見者の判断が働いているのです。
意見文を書く指導をしているとき、この「論拠」の存在を意識すると説明がとてもうまくいきます。これまでは意見の根拠を明確にして文章を書きなさいということしか言ってこなかったのですが、これでは根拠の部分の書き方が明確ではありませんでした。だから実際には生徒は困っていたはずです。これまで「根拠」と言っていた部分を「根拠」と「論拠」に分けることによって、うまく整理することができます。これは目からウロコ的な発見でした。
根拠」と「意見」が近すぎ、「論拠」が入る余地がないような意見は、当たり前すぎて言うまでもない意見ということになります。「根拠」と「意見」があまりにも離れすぎ、「論拠」をしめしてもつながらないような意見は、だれにも理解されない独りよがりな独断ということになります。
この「根拠・論拠・意見」を意識して文章を書く、あるいは文章を読むということはとても論理力をつけることになります。この指導を試行錯誤しながら実践しています。
よく意見を書くときにはその根拠をしめしなさいと指導します。意見だけでは論理的な文章になりません。必ず根拠が必要だと教えるわけです。それに対して福澤先生の主張はその根拠の部分を「根拠」と「論拠」に分けます。
「根拠」は事実です。意見が生まれるそのもとになる事実です。「論拠」はその「根拠」から「意見」にいたるまでの中間のものにあたります。これは事実ではありません。あくまで主張者の考え方が示されるものです。
わかりにくいと思われますので、具体例で説明します。
「昨日はラーメンを食べた。だから今日はカレーを食べよう。」
という文において「昨日はラーメンを食べた。」という部分は事実であり、「根拠」になります。そして「今日はカレーを食べよう。」は意見になります。実はここには「論拠」が隠されています。「2日連続でラーメンは飽きる。」という内容です。これが論拠になります。
根拠 昨日はラーメンを食べた。
論拠 2日連続でラーメンは飽きる。
意見 今日はカレーを食べよう。
この論拠は事実ではありません。事実から生じる発言者の判断です。だから同じ根拠でも論拠の部分を変えれば別の意見になりえます。
根拠 昨日はラーメンを食べた。
論拠 ラーメンはおいしい。
意見 今日もラーメンを食べよう。
上記の意見も十分成立するものです。同じ根拠でもまったく別の意見が生まれてきます。そこには「論拠」という意見者の判断が働いているのです。
意見文を書く指導をしているとき、この「論拠」の存在を意識すると説明がとてもうまくいきます。これまでは意見の根拠を明確にして文章を書きなさいということしか言ってこなかったのですが、これでは根拠の部分の書き方が明確ではありませんでした。だから実際には生徒は困っていたはずです。これまで「根拠」と言っていた部分を「根拠」と「論拠」に分けることによって、うまく整理することができます。これは目からウロコ的な発見でした。
根拠」と「意見」が近すぎ、「論拠」が入る余地がないような意見は、当たり前すぎて言うまでもない意見ということになります。「根拠」と「意見」があまりにも離れすぎ、「論拠」をしめしてもつながらないような意見は、だれにも理解されない独りよがりな独断ということになります。
この「根拠・論拠・意見」を意識して文章を書く、あるいは文章を読むということはとても論理力をつけることになります。この指導を試行錯誤しながら実践しています。












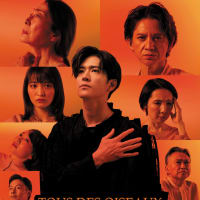
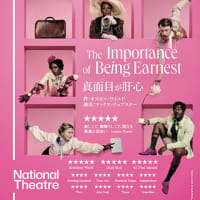



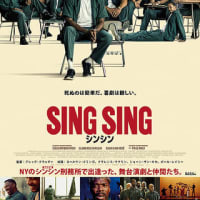









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます