
アカデミー賞で、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した話題の映画『ノーアザーランド』を見ました。世界の中にはっきりと目に見える形で存在する、差別、横暴な国家権力、それらを生む歴史など、様々なことを考えさせられる映画でした。
バーセル・アドラーという名の若いパレスチナ人活動家によるドキュメンタリー映画です。彼らが住む村はイスラエル領となり、突然イスラエル軍の軍事練習場にさせられます。そこに住むパレスチナ人は強制移動させられることになります。住民は抵抗するのですが、イスラエル軍は徐徐に住民を切り崩し、住民は少しずつ減少していきます。その様子をアドラーは映像に残していきます。
イスラエルのパレスチナ人に対する差別意識には看過しがたいものがあります。今起きているガザ地区への攻撃もだれがどうみてもやりすぎです。許しがたい。ただし、一方ではイスラエル人がかつてヨーロッパで受けてきた差別も忘れてはいけないものです。憎しみは連鎖するとよく言われます。この連鎖から抜け出すためにも、こういうひずみに目を向けることは絶対に必要なことです。
国家権力の横暴にも目を向ける必要があります。経済優先社会となった現在、国家権力を強化させることによって、効率的な国家を作り上げることが世界のトレンドになっています。強いリーダーが長期に政権を担い、国家的な戦略をもとに国民が動員されていきます。このことによって、被権力の立場にいる人が迫害されていきます。中東においてはパレスチナ人であり、日本においては地方であり、中小企業であり、女性や子供たちです。中央でいい暮らしをしている人間が、地方の状況がわからないまま偉そうにふるまう、それが当たり前になっているのです。そこには正しい論理はありません。
この映画でもう一つ見逃してはいけないのは、そういう危機が日常の生活のすぐそば、いいえ、日常の生活そのものとなっているということを伝えてくれるということです。あたりまえの現実が突然銃声によって終わりをつげる、そんな日常の中に生きている人がたくさんいるという現実をみつめなければいけません。
脈絡をつかむのがむずかしい映画ですが、しっかりと見つめる必要がある映画でした。












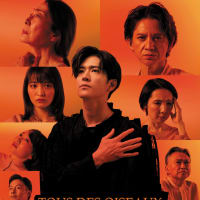
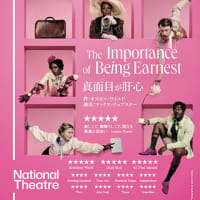



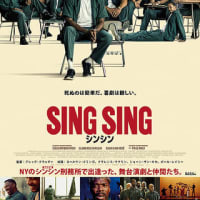









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます