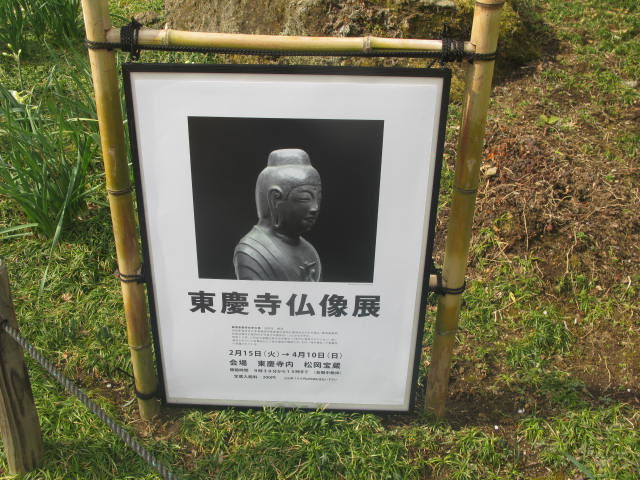まだ残雪でもあるかなと、三島由紀夫の”春の雪”の舞台(侯爵邸として)になった鎌倉文学館に出かけた。まず、庭園から見学した。今の時期には、薔薇園もすべて剪定されていて、殺風景だったが、品種名、”春の雪”の薔薇の根元にわずかばかりの雪が残っていて風情を出していた。昨日、テレビで観た、懐かしの歌謡曲、”なごり雪”なんぞを思い出したりした。♪・・ 季節外れの雪が降ってる、 東京で見る雪はこれが 最後ねと、 寂しそうに君 がつぶやく、なごり雪 も降る時を知り、 ふざけすぎた、季節の後で、 今春が来て・・♪ と、唄いながら、文学館に向かう途中、福寿草がいくつか花開いていた。今朝の散歩の大長寺の掲示板のご住職の句を思いだした。”今年こそ心地よくさけ福寿草”




文学館では、鎌倉ゆかりのシナリオ作家、劇作家の展覧会をやっていた。昨年、お亡くなりなられた井上ひさしさんの”追悼展示”と銘うってあった。一部がシナリオの世界、二部が戯曲の世界という展示構成であった。
シナリオの一番手は、小津安二郎、野田高悟コンビだ。茅ヶ崎館にこもって東京物語をはじめ、名作の数々の脚本をつくった。小津の、野田との相性のよさの言葉が面白い。酒量も、肴の好みも、宵っ張りの朝寝坊であることもぴったりで誠に具合が良い。(ぼくも酒飲みだからよくわかる)。でもぼくは早起きだから、小津さんとは合わないかもしれない(爆)。”秋日和”の創作ノートなどが展示されていた。野田高悟は浄明寺(地名)に住んでいたらしい。原節子さんと同じだ。松竹大船撮影所コーナーもあり、そこには、小津の愛用した、白いピケ帽、赤いロケ用三脚(カニと呼ばれた)、そして”彼岸花”で使用した、赤いやかんと湯呑(自分でも使っていたものらしい、赤が好きなのだ)なども展示されていた。
倉田文人のコーナーで、ちょっと懐かしい映画が出てきた。”ノンちゃん雲に乗る”だ。鰐淵晴子が出演している。彼女はぼくと同年輩の子役スターで、人気者だった。東横線の新丸子に住んでいて、ぼくのいとこがすぐ近くだったのでよく見かけたと言っているのを聞いて、うらやましく思ったものだった(汗)。あれ、と思ったのは、少年時代には全く、気付かなかったが、この映画に原節子が出演していたことだった。
第二部の主役は井上ひさしだ。劇団こまつ座の季刊誌”the 座”が展示されていた。創刊号は”頭痛肩こり樋口一葉”で紀伊国屋ホール初演のものだった。その7号は”泣き虫、なまいき石川啄木”。そのほか、花よりタンゴ(爆)、人間合格(爆)、国語元年、日本人のへそ(井上ひさし追悼公演の最後を飾り、この3月、渋谷のBUNKAMURA シアターコクーンで開催の予定で、浅草ストリップの華、ヘレン天津一代記です、観にいこうかなと思っています)。有名な言葉、”むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをゆかいに、ゆかいなことをまじめに、書くこと”の色紙も展示されていた。
大船フラワーセンターの近くにお住まいだった、北条秀司は、”北条政子”の台本や源氏物語の”浮舟”の長谷川一夫と京マチ子のポスターなどが展示されていた。久坂栄二郎は”わが青春に悔いなし”。映画化もされ、黒澤明監督で原節子主演、木下恵介監督では杉村春子主演だった。戦後の鎌倉アカデミア(大学校)の紹介もあった。その他、ぼくには知らない劇作家の方々(最後のちらしの写真でみてください)の展示品も興味深くみさせてもらった。
常設展(ときどき展示替えする)では、その鎌倉アカデミアで学んだ山口瞳の書があった。漱石の”こころ”の一節だ、そして、虚子の子、星野立子の俳句の色紙も、あらたに展示されていた。心に残ったので紹介しておきます。
・・・
漱石こころ/山口瞳 写
私は淋しい人間ですが
ことによると
貴方も淋しい人間では
ないですか
星野立子 句
雛(ひな)かざりつつふと命惜しきかな
桜貝拾ひし時がただ楽し
うぐいすに包まれ過ぎし日もありし