便利な時代になったもので、ネットのユーチューブを使えば、いつでも、名人の落語を視聴できる。昨日は、古今亭志ん生と志ん朝の”火焔太鼓”をつづけて聞いた。何故、聞く気になったかは、あとで述べるとして、まず、演目の”火焔太鼓”について。以下のような内容である。昨年、近くのホールで、古今亭菊之丞で聞いているので、そのときのブログ記事を貼りつけておく。
古道具屋の甚兵衛は商売気がなく、古タンスを買おうとした客に、”6年も置きっぱなし(売れない)”、”引き出しが開かない”などと言って、お客を帰らせてしまう。利口なかかあがいるから、何とか商売を続けている。ある日、甚兵衛が古くて汚い太鼓を一文で仕入れてきたが、かかあに馬鹿にされる。あまりにも汚いので、店先で丁稚にハタキをかけさせていると、手を滑らせて音をドンドンと鳴らしてしまう。そこへ、一人の侍があわてたように飛び込んで来た。怒られるのかと思ったら、籠で通りかかった主君がこの太鼓の音を気に入ったのだと言う。ぜひ実物を見てみたいから屋敷まで太鼓を持って来るようにとお達しがあった。そして、これが国宝級の火焔太鼓であって、なんと、300両で購入するという。うきうきして帰る甚兵衛。五十両ずつ、懐から小判を出す、甚兵衛に対する、かかあの評価が段階的に上がっていく。すっかり上機嫌の甚兵衛は、音がするものがいい、今度は火の見櫓の半鐘を仕入れようと言うと、かかあは、”半鐘はいけないよ、おジャンになるから”と締める。
これを志ん朝できくと、同じ演目でもこうも違うのかと思うほど、噺の流れがなめらかで、スピード感があり、かつ、きれがある。最後まで息もつかせぬという感じ。さすが、当時、東の志ん朝、西の枝雀といわれただけはある。
そして、つづいて、志ん生。これがまた、一味違う。志ん生といえば、落語界の神さまみたいな存在。絶妙な語り口は誰も真似できない。とくに、この”火焔太鼓”は、志ん生おはこの演目だ。
では、何故、つづけて聞いたか。それは、先週、ぼくの、お気に入りの番組、”アナザーストーリーズ”を見たから。今回のテーマは”落語を救った男たち 天才現る!古今亭志ん朝の衝撃”。
1961年暮れ、古今亭志ん生が病に倒れ、落語は衰退の危機を迎えていた。それを救ったのが、翌年、先輩19人をごぼう抜きで真打に昇進した古今亭志ん朝だった。
この大抜擢を決めたのが当時の重鎮たち。円生、文楽そして志ん生。
すでにテレビドラマ等で活躍していた志ん朝を落語界に引き戻したい意向があったようだ。しかし、ごぼう抜きされた先輩たちの反発は大きかった。その中には、のちに大成する談志や円楽、円蔵らも含まれていた。結果的に志ん朝の抜擢で、その後、次々スターが育ち、落語界は隆盛期を迎えることになる。
真打になれ(志ん生)、勘弁してくださいよ(志ん朝)。
しかし、若いながら実力は誰にも認められていた。そして、自分でもひそかに自信をもっていた。こんな文章も書いている。
そして、晴れの志ん朝の真打昇進披露公演が昭和38年(1962年)3月、上野鈴本で行われる。何と、初日の演目が志ん生の十八番”火焔太鼓”、そして、四日目に文楽のおはこ、”明烏(あけがらす)”。同期の馬風がそのときの驚きを隠さない。まるで名人に挑戦状をつきつけるかのような演目、それがまた、二人と違った語り口で、うまいんだなぁ。それを聞いて、次の時代をリードする落語家だと確信したよ。
鈴本に残る、志ん朝の真打披露公演初日の演目。志ん生は病いに伏せ、真打昇進披露興行には出席できなかった。口上は文楽が述べた。
以上が、”火焔太鼓”を志ん生と志ん朝で聞いてみたいと思った理由です。
ぼくが好きな志ん生の逸話をひとつ。
師匠の酒好きは有名だった。大正12年、関東大震災があった日のこと。”酒が地べたに呑まれちまうんじゃ、もったいねえ”と近所の酒屋に飛び込む。”酒え売ってください” ”ゼニなどようがす、私ら逃げますので自由にお呑みなさい” 師匠は4斗樽の栓をぬき、1升5合ほどいただき、へべれけになって、帰宅した。その手にはなお一升瓶を大事そうに抱えていたそうだ。
志ん生夫婦の生活は、赤貧洗うがごとくだった。師匠の、呑む・うつ・買うのせいだったらしい。でも、夫婦仲むつまじく、喧嘩をしたのをみたことがないと、長女は言っている。師匠が得意とする噺”替り目”の中に、”ほんとうの貧乏を味わったものでなけりゃ、ほんとうの喜びも、面白さも、ひとの情けもわからない”というせりふが出てくるが、実生活を彷彿させるようだ。こういう貧乏生活の中から、ご子息の、馬生と志ん朝という名人も育った。






















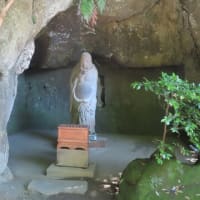




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます