
いつも賑わう鎌倉の小町通りがそろそろ終わろうとする辺りを横切る小道を左に折れると、それまでの喧騒がうそのような、静かな住宅街の一画に鏑木清方記念館がある。晩年、清方がすごした旧居でもある。清方は、神田で生まれ、隅田川沿いの築地で育った、ちゃきちゃきの江戸っ子である。東京の下町も賑やかな商店街から一歩、奥の脇道に入ると、結構静かな、落ち着いた雰囲気があるが、ここ、雪の下も似たような風情で気に入り、終の棲家とした。
ぼくもときどき、この辺りを徘徊していて、この美術館には何度も来ているが、いつもブログに載せているわけではない。今回、紫陽花の季節でもあるし(清方は紫陽花が大好きで、紫陽花舎主人と称していた)、清方がいつもみていた、そしてぼくも好きな隅田川がテーマの展覧会なので、紹介することにした。
まず、大正3年作の”墨田河舟遊”。六曲一双の屏風絵に圧倒される。挿絵画家から、初めて大画面に臨んだ記念すべき作品だそうだ。野坂昭如は、鏑木清方の大フアンで、その時代をありのままに描いた、これほどの人はいないと激賞しているが、その通りで、当時の舟遊びの様子が見事に描かれている。右半双は、人形芝居を観ながら舟遊び、優雅ですね。たくさんの美人に囲まれて。いいな(汗)。

清方自身は、左半双の方にむしろ興味があったようだ。櫓でこぐ隠れ家のような小舟での舟遊び、船先の猿が目印の吉原の遊びに行く小舟、もっと小さなボートのような舟などがていねいに描かれている。大川端で育った清方ならでの観察眼といえるだろう。

”山谷堀” 今戸から山谷に至る掘割りで、かって、日本堤にあった新吉原に通う遊客でにぎわったという。

墨田川両岸(梅若塚・今戸)。わが子が死んだこと知らず、捜しまわる母親(右)。左の絵の背景に、今戸焼きの窯がみえる。むかしは隅田川の風物詩だった。

記念館のコーナーに、鏑木文庫がある。はじめ小説家になろうとしたくらいなので、文才もあり、”こしかたの記”などたくさんの著作がある。これらの本をここで読むのも楽しみだ。”市人の暮らし”(昭和45年)の中にこんな文章があったので紹介しておく。
・・今、私がしきりと描きたいもの、また描いておきたいものは昭和の半ばまで続いていたいた市人のおだやかな暮らし、それはもう二度とめぐって来ないように思われる、心ゆくまで写しとどめたい・・
窓の外の、庭の紫陽花がちょうど見頃を迎えていた。




















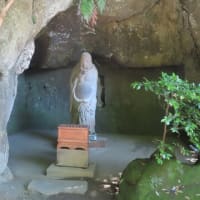




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます