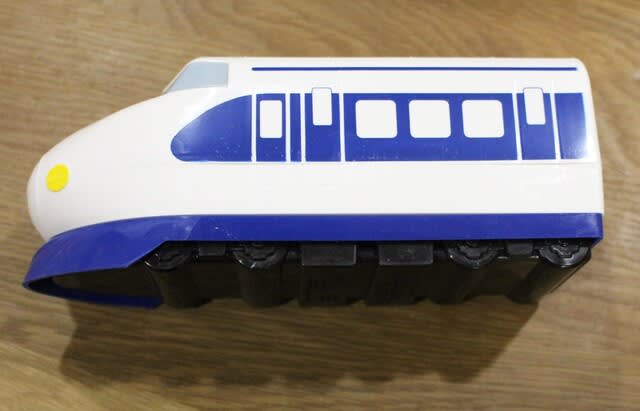鉄道模型と実物の鉄道を扱う雑誌「とれいん」が12月号で600号に、1月号で創刊50周年を迎えました。おめでとうございます。

600号では京急600形を特集し、今号では東急を特集しています。毎年1月号は大きな特集号となりますが、今回はかなりのボリュームです。鉄道ファン誌などは100号の区切りにそれに因んだ特集が組まれますが、日米欧の有名な機関車を100種ずつ模型で紹介した100号はともかく、節目の号で特別なことを、という感じではありません。それでも1月号については質・量ともにたいへんなボリュームで、歴史があって、地方に譲渡車も多く、となりますと、実物・模型共にかなり幅も広くなるかなと思います。
それぞれのモデラーがさまざまな時代の車輌を作り、ゲージを問わず充実した内容となっています。「1985年の8500系」を作られた方もいましたし(私も1986年の8000系を作ってブログ上でご紹介していますが)、真鍮・プラ含めてさまざまなキットが出ているので、時代も、路線も選び放題です。
実物の記事で言えば、表紙を飾った5050系が「車輛の視点」で詳説されています。この形式(兄弟車もいますが)も登場から20年ということで、新車だと思っていたらそれなりに時間も経っているのですね。グリーンマックスの完成品を早いうちに購入した記憶があります。横浜高速のY500も買っていて、まだ新宿にもあった天賞堂(ただし住友三角ビルからオークタワーに移った後ですが)さんで「お客さん、基本セットだけ買うってことはないでしょ(笑)?」と聞かれ、8輌編成がやってきたことを覚えています。
東急というと以前も書きましたが高校生の頃には東横線沿線に通学していましたし、部活でたまに新玉川線にも乗りました。また、仕事で目黒線、多摩川線、大井町線、池上線、世田谷線にもお世話になり、外回りをしながら完乗しています。
先週くらいまで仕事がとても忙しく、ゆっくり本も読めなかったのですが、ようやく読めるな、なんて思っていたら、豚児が熱心に見ています。たまに行く横浜で東急は少しばかりなじみがあるのと、乗り入れが多いため各社の車輌の写真も多く掲載されており、それも含めてよく眺めています。豚児よ、少々お高かったのだから大事に見るんだよ。
とれいん誌と出会ったのはたぶん小学生の頃ですから、判型は大きいものの「鉄道模型趣味」誌に比べて薄かった頃です。大人のお洒落な雑誌という感があり、日本型だけでなく、外国型の記事も多く、私などは背伸びをしながら覗いているような、そんな感じがしました。一時期真剣にアメリカ型HOゲージの方に足を踏み入れようとしたことがあり、アサーンのボックスカー(有蓋車)を組んだのも同誌にそういった記事が出ていたからでしょう。実物の車輛の撮影についても同誌で写真術の連載があって、そこで基礎から勉強しました。
やがて自分が大人になり、執筆陣も、編集者もだいぶ入れ替わりましたが、アメリカ型、ヨーロッパ型を問わず、依然外国型の記事が載りますし、最近では台湾の鉄道の記事も載っています。また「Nキット上達の道」のように、GMの「板状キット」を基礎から組んでいく連載もあり、私も勉強させていただいています。それから「おとなの工作談義」のように、名うてのモデラーたちの座談が連載になっており、こちらも読んでいて楽しいです。
私も初めてこの雑誌と出会ってから随分経ち、年齢もそれなりに重ねておりますが、同誌がこれからも鉄道好きの子供を背伸びさせ、また「元子供」たちにも模型の楽しさ、鉄道の楽しさを改めて教えていただけることを期待したいと思います。