2月26日 14時から17時、高知市議会棟 第一委員会室で、高知ホタル シンポジューム 開催しました。

開会あいさつ をする、宮本さん。ホタルパトロール隊をつくって、ホタル保護を呼び掛けながらのご挨拶…
まず形から・・・と、こんな目立つパトロール隊の服でどうでしょう…宮本さんらしいユニークなご挨拶でした。

基調報告
先進地「北九州市下水道河川部水環境課ほたる係」の取り組みの紹介を、羽迫博巳さん(福岡市在住・2年前まで高知市民で活動していた人)にしていただきました。

先進地の「北九州市下水道河川部水環境課ほたる係」などの紹介を参考にしながら、「ホタル条例」に端を発した今回の取り組みが、ホタル保護と共に河川の環境保全と川に親しむ取り組みや、環境問題の大きな前進の第一歩となることを目的として、開催しました。
報告では、
自立した活動をしていた所は、ずっと元気に活動が続いているが、行政主導でやっていたところはほとんどが活動が停滞しているという話もあり、考えさせられました。

テレビ局3社が取材に来て下さり、「ホタル条例」を通しての、ホタル保護にエールを送ってもらえました。
多くの皆様に関心を持ってもらう良い機会になりました。

根木勢介 さんの記事・・・龍馬その5:長岡謙吉特集第5回目八策は、「十一策」だった?
日曜日に魚梁瀬森林鉄道や馬路村の地域振興に尽力中の若者(34歳)のはなし
を聞く機会がありました。
NHK総合テレビの番組で「嵐の桜井翔」が馬路村を訪れて間伐体験などを
体験する番組が放送されました。いい番組だったと記憶しております。
この番組の放映後、馬路村への来村者が、増加しているそうです。
その彼は、テレビの影響・効果は、大きいと話していました。
さて、「長岡謙吉」特集を今回も続けたいと思います。
なお、赤字部分は、根木によるものです。
■坂本龍馬 五つの新常識:文藝春秋スペシャル2012季刊夏号・48pより
④「船中八策」は十一策あった(菊地明・幕末維新研究家執筆)
慶応三年(1867)五月十二日、京都で薩摩藩の島津久光、宇和島藩の伊達
宗城(むねなり)、福井藩の松平春嶽、それに土佐藩の山内容堂が合同し、政局
を議する「四侯会議」が開かれました。容堂は親幕派ですが、久光は反幕、宗城
と春嶽は幕府体制の維持には消極的な立場にありました。
当然、容堂は孤立してしまい、その後の会議をボイコットして、二十七日には
病気を理由に帰国の途についてしまいます。
しかしこのままでは土佐藩の存在意義がなくなってしまいます。そこで容堂は
帰国に先立って、長崎滞在中の後藤象二郎に事態を打開するため、上京を命じて
いました。
後藤象二郎が長崎から船で大坂に向かったのは、六月九日のことです。これには
後藤の依頼によって、やはり長崎にいた龍馬が同行していました。
この航海中に龍馬が提示したとされるのが、大政奉還と議会制を柱とした、
いわゆる「船中八策」です。同行していた海援隊の長岡謙吉が起草したと
いいます。
ところが、この「船中八策」も「亀山社中」同様、昭和になってからの名称
なのです。
しかも、当初は「八策」ではなく、「十一策」だったとされていました。
明治二十九年の『阪(坂)本龍馬』は、「長岡謙吉」をして建議案十一箇条を
草せしめたり」、大正元年の『維新土佐勤王史』は「世にいわゆる坂本の八策なる
もの」「第九、第十、第十一」の文字は、世に伝わらず」とあります。
これが「八策」とされるのは大正三年の『坂本龍馬』からで、そこには「長岡を
して左の八策を草せしむ」とあり、昭和元年の『雋(しゅんけつ)傑坂本龍馬』
では「世にいわゆる龍馬の八策」とあります。
※雋(しゅん、すぐれているの意)
そして昭和四年刊行の平尾道雄の『坂本龍馬海援隊始末』によて、初めて「時勢
救済策として八箇条を議定した。いわゆる船中八策と称されるもので・・・・」と
「船中八策」という名称が使用されたのです。
後藤象二郎が山内容堂に上京を命じられてから、長崎を出立するまで、ある程度の
日数があります。
このとき後藤と龍馬は盟友関係にあり、上京命令を受けた後藤は、龍馬の意見を
求めたはずです。後藤に対応能力がないということではなく、自分とは異なった
経験を重ねている龍馬による、別角度からの打開策の有無を探ったに
違いありません。
その結果に有効性があると考えれば取り入れ、なければ却下すればいいのです。
とにかく、反幕的方向に進んでいた政局において、親幕派の土佐藩が存在感を
示すことは非常に困難な状況にありました。
それなのに後藤は、乗船するまで龍馬に相談しなかったというのでしょうか。
龍馬は相談を受けていたとしても、船に乗るまでは何も語らなかったというので
しょうか。
そう考えるのであれば、それは「船中」という言葉に引きずられた結果に過ぎず、
そのようなことがあったはずはないのです。
後藤と話し合った龍馬は、一つの答えを見いだします。それが、一見すると
親幕的でないものの反幕的雄藩の政治参加を認めるというものでした。
つまり、幕府が政権を朝廷に返還し、徳川家が一つの藩として新政権に加わると
いう大政奉還です。
もちろん、龍馬のオリジナルではありません。前述したように、海舟・松平春嶽・
横井小楠らはそうした構想を抱いており、龍馬はそれに興味を持って彼らと接触し、
海舟の門下生となったのです。
長崎出立前の五月二十八日、龍馬はお龍に手紙を書きました。現存する唯一のお龍
宛てのものです。
そこに龍馬は「このたびの上京は誠にたのしみにて候」と書いています。
このことは、龍馬が乗船後に大政奉還策を提示したものでないことを、如実に物語
っています。
龍馬が「たのしみ」にしていたのは、京都見物でも知人との再会でもなく、大政
奉還という政策に京阪の親幕派の土佐藩士や反幕派の諸藩士がどのように反応
するか、そこに興味があったのです。
結果的に、土佐藩は大政奉還を藩論とし、幕府に建白することとなり、反幕派の
薩摩藩もそれを認めました。
そして、時の将軍・徳川慶喜は建白を受け入れ、徳川幕府は消滅することと
なるのです。
根木勢介 携帯:090-2825-2069
根木勢介 さんの記事・・・土佐の戦国七守護その1:若宮八幡宮
我が妻は、牧野富太郎に厳しい見方をする。富太郎の奥さんの最後が「哀れ」だと
言う。『うどんが、ごちそう』の苦しい時期を支えたのは、奥さんであり、
そして、彼の家族だった。植物研究のための本の購入をすこし控えれば、うどんが
ごちそう、だというようなすさまじい生活をしなくてよかったのだから。
牧野植物園のSさんによると、『奥さんは、牧野富太郎の「同志」であった』から
最後までついて行けた』という。
牧野富太郎の「植物画」は、有名である。画家を志しておれば、おそらく独特な
「絵画」の境地に到達していただろう。画家としても、一流の画家になったに
違いない。
彼が、好んで使用していたという「ネズミの毛の筆」のことが、出ていたので紹介
します。おそらく当時も「ネズミの筆」は高価だったでしょう。
赤字は、根木によるものです。
●文藝春秋・三月特別号(2013・3)
・輪島塗の下支え 文:神津カンナ、写真:高田浩行
・・・。
線描用の驚くほど細い根朱筆(ねじふで)。左手の親指に縄でくくりつけた、
絵画で言えばパレットのような爪盤(つめばん)、作品をしまっておく湿風呂
(しめふろ)と言われる棚。どれもめずらしく、思わず見入ってしまう。
「伝統工芸を支えるのは伝統工芸なんです。蒔絵師が存在しても、筆を作る
人、紙を漉く人、炭を作る人がいなくなるとなりたたない。」
ネズミの背骨の横にすっと出ている立ち毛で作る根朱筆(ねじふで)。
一本作るのに最低でもネズミの皮は五枚必要だという。しかもどんなネズミでも
いいわけではなく、今はなかなか手に入らず、この筆も一本数万円以上はする。
ローテーションで何本かを使い回しし、消耗しないようにしているが持つのは
三ヶ月程度。塗物を平らにするための作業工程は炭研ぎといわれるが、・・・。
今日は、五月連休のシャトルバスについての研修がありました。
その研修の中で、若宮八幡宮について「疑問点」が出されました。
以下の記述がよくわからない、との疑問です。赤字は、根木によるもの。
■高知観光ガイドブック3 108pより
・若宮八幡宮
八幡宮は武家の守護神として昔から崇拝された。鎌倉時代の文治元年(1185)
、源頼朝が吾川郡を吾川荘として京都の六条若宮八幡宮に寄進したとき、その
八幡宮をあらためてこの地に勧請(かんじょう)したものと伝える。
祭神は応神天皇(おうじんてんのう)、神功皇后(じんぐうこうごう)などの
五柱である。
長宗我部元親は、永禄3年・・・。
帰りに図書館で調べてわかったことを皆さんに紹介します。参考になれば幸いです。
赤字・青字は、根木によるものです。
■長宗我部地検帳の神々(廣江 清執筆) 14pより
・・・。
吾川郡長浜村(高知市)の若宮八幡宮は、
「京都六条若宮八幡宮の勧請したるものと見たり。六条若宮を今左牡牛八幡と云。
往昔頼朝公の時六条為義の宅地を追福の為且国家安鎮に八幡宮を鎮め祭られ若宮
八幡といふ。土佐国吾川郡を一円に寄附せられし由東鑑に見たり」
(『詒謀記事(だいぼうきじ?!』)
『東鑑』には、
「文治元年十二月卅(三十・そう)日己卯以土佐国吾川郡令寄附六条若宮」
とある。
六条若宮の社領に分祀された八幡であるから別宮であるが、本社が若宮であるから
若宮八幡と称えたものであろう。
『地検帳』には単に若宮とあるが、
若宮ノ御宮床
一ゝ卅(三十)代 本社三間四間板つき(フきカ) 若宮宮床
カヤフキ
舞殿二間五間
横殿二間八間ノ跡横殿ハナシ
なかなかりっぱな社殿で、社領も一町二反二十六代一歩ある。
長宗我部元親が出陣の時に祈願をこめたと言い伝えられているだけのことはある。
祭神は応神天皇・神功皇后・市杵島姫神・田心姫神・㟨(たん)津姫神の五柱
(『神社明細帳・吾一』)と記されているが、
『土陽淵岳志』は、
「吾川郡長浜村若宮八幡宮ハ里人云伝ヘテ、悪源太義平ヲ祭ルト云。俗説信ス
ヘカラス」
『南路志』は何によったかわからないが、
「或云昔長楽院罹₂火災₁失₂旧記₁、其詳不ㇾ可₂得而知₁矣(い・※註)。
云言悪源太義平之祠或云吉良冠者希義之祠(下略)」
と記している。これは「若宮」からきた連想であろう。
若宮には四種ある。(『一三)若宮の項参照)が、その一つに非業の死を遂げた人
の霊をまつった社がある。
この若宮八幡に義平や希義がまつられているという伝説が生まれたのは、両人とも
悲運に倒れている上、何れも源家にゆかりがあるからであろう。
(このあとに、「一覧表」があるが、省略)
※矣(い)=置き字といわれる。普通は、読まない。
きっぱりと言い切る語気をあらわす。
祠=原文では、「ネ+司」の漢字。打ち出せないので「祠」を当てた。
根木勢介 携帯:090-2825-2069
根木勢介 さんの記事・・・龍馬その4:長岡謙吉特集第4回目・「維新、大政奉還」の由来
添付の画像は、横浜に「脱藩中」の龍馬を見かけたと二男が送ってくれました。
偶然、横浜の赤レンガ倉庫のところで見かけたそうです。

先日は、少し風邪気味なので家に閉じこもっていました。
読もうと思っていた文藝春秋・三月特別号:「司馬さんが見たアジア」が読めました。
今日は、その文藝春秋の中から・・・。赤字は、根木によるものです。
■日本、中国、韓国 歴史の風景:司馬遼太郎・昭和46年より
・・・。(途中略。)
・現金競争に敗けた幕府
それで徳川期いっぱいが続いて、明治維新になって農業国家がだいそれたことに
軍艦も製鉄所も持つ。
ところが外国に売るべきものは生糸しかない。いま考えてもぞっとするほどによく
やったものだと思います。
考えてみますと、明治維新成立の段階での日本というのは東アジアどの国の農村
よりも豊かですね。むろん豊かさといっても相対的なものですけれども。
ところで儒教的中国体制の中国の農村からは物事は起こらない、韓国の農村からは
絶対に物事は起こらないですけれども、日本の農村は五十軒に三軒は富農です。
それはさっきからいっている競争の原理によって、田圃(たんぼ)がふえていく。
江戸時代の百姓でもお寺の過去帳などを見ますと、五代前は貧乏だったのが五代後
には富農になっていたりします。
また冨が持続するわけではなくて、極道者が出れば没落するし働き者が出れば家が
興る。猛烈に働いて荒地を開墾していくわけだからそのたびにお米がとれる場所が
ふえていくわけです。
幕末でも、長州や島津のように殖産興業とか干拓をやった所は、米はもういい、
こんどは現金がほしくなったというわけで、現金をうるには殖産興業がいい。
それは割に古くからやっています。幕府だけはやっていなかった。
幕府だけにかわいそうなことに一種の儒教的ムードがあったためです。
これは儒教体制ということではありません。この儒教的ムードのために、農民を
大事にしろとか、農というものを基本にせよということが、儒教以外の別の事情
からきていますけれども、江戸時代の初期からあって、幕府直轄領では最後まで
殖産興業をしなかった、だから現金収入がない。
現金収入はかろうじて天領の博多、堺とか横浜という新旧の港から吸い上げる金
くらいです。だから競争に敗けるわけですね。
長州と徳川家とは競争していたんだということが、結果論からいってもいえる
わけです。現金を蓄める競争を。で、長州はそれに勝った、むろん薩摩も勝って
いるわけです。
だからこんな狭い、といってもヨーロッパの国から普通だけれども、アジア的な
規模でいえば狭い国で一つの天下が千数年成立しており、今も日本人は天下だと
思っている。
それが外に押し出すときには倭寇になり、豊臣秀吉の朝鮮出兵になったり日中事変
になったり、やぶれかぶれになると太平洋戦争になるわけです。
・・・。
ヨーロッパの帝国主義には帝国主義なりの歴史と成熟とエネルギーが出来上がって
ゆきますけれど、日本のはそんなものとはまったく関係なしで、国内の競争原理
そのままで行くわけですから倭寇の形ですよ。だから日中戦争までは倭寇です。
・・・。
●この同じ雑誌より:儒教への厳しい目・宮城谷昌光より
・・・。(途中略。)
・中国人の姿は未来の日本人か
・・・。
もちろん司馬さんだけではなく、日本人全体が、中国の言葉を借りて思想に転化
してきました。いま使われている「維新」も『詩経』にある。
周雖舊邦(周は旧邦といえども)
其命維新(その命はこれ新し)
「周という国は、以前からある古い国ではあるが、いまこうして殷(いん)の
王朝を倒したゆえに、新しい国になりましたよ」という意味で、明治という国の
新しさを世の中に伝えるとき、明治の日本人は、殷と周の革命を引き合いに
出して説いたわけです。
また、「大政奉還」という言葉も古代中国の故事からきた言葉です。周王朝の
建国者、武王が亡くなってしまったため、弟の周公旦が政治をとりしきったが、
革命期の混乱を乗り越えた後は成年になった武王の子、成王に政治権力を還した
、というものです。
政治であれ思想であれ、中国の歴史にない事例はないし、それを日本はお手本に
してきました。いま日本人が批判する中国人の言動は、数百年後、数千年後の
日本人の姿かもしれない。
とはいえ、これまでの日本人は、中国から採り入れるもの、入れないものを
分けています。
たとえば、科挙や宦官(かんがん)といった制度は採用しなかったし、仏教は
入れても、道教は定着していません。儒教は入れたけれど、中国人や朝鮮の人
たちのように、生活の中まで入りこむことはなく、あくまで学問の世界に
とどまった。
そうした理由を考えることは、まさに司馬さんが生涯をかけて挑んだテーマです。
司馬さんがいらっしゃらない現在、こんどは私たちが司馬さんの目をかりて
、中国、そして日本を眺めることが必要なのかもしれません。
根木勢介 携帯:090-2825-2069
根木勢介 さんの記事・・・龍馬その3:長岡謙吉特集3回目
今日の高知市は、朝から気温が低く、たいへん寒いですが、「春の訪れ」の
ニュースを83(はちみつ・蜂さん)プロジェクトのNさんから、お聞きしました。
Nさんの知人が、香南市吉川(旧吉川村)に置いてある「みつばち群」から、先月末
に「分蜂」があった、そうです。
分蜂とは、「新」女王蜂の誕生により「旧」女王蜂の元からその一群が「巣立つ」
ことをいいますが、普通は、温かくなった春から夏の時期に分蜂します。
この寒い時期に分蜂があったのは、いくつかの好条件が重なったからでしょう。
もともとこの巣箱(蜂群)は、気温の低い・山間部の「土佐町」から、温かい海辺の
町・香南市吉川に「疎開」させたものだそうです。
移動先の(旧)吉川村が、海辺に近く温かい・巣箱の場所も温かった、からでしょう。
温かいところでは、菜の花などももう咲いており、「蜜源」植物が、冬でも豊富です。
余談ですが、一般的教科書・参考書では、分蜂する場合、「旧女王蜂群(の巣箱)」
から「新女王蜂群」が、”巣立つ”ようです。
ところが、本日の83プロジェクトの「蜂さん談議」では、逆もある、との話が会員
から出されました。
自然界のふしぎさ・奥深さ、を感じました。
さて、高知県歴史辞典では、「船中八策」の長岡謙吉の関わる箇所がどうなっているか、
転記してみました。(赤字は、根木によるもの)
■高知県歴史辞典:410pより
・船中八策(の事項)
坂本龍馬が、慶応三年(1867)六月九日藩船夕顔丸で長崎港を出て兵庫に
向かう船中で、同船の後藤象二郎に示したものといわれ、筆記者は海援隊文司
長岡謙吉、その趣旨は龍馬の懐抱した王政復古案である、八ヵ条から成り、第一条で
政権を朝廷に奉還、政令は朝廷から出ることをまず示し、第二条で万機公議で
決するために上下議政局を設けること、第三条で人材登用と冗官(※)の整理を、
第四条で外国との新しい国交樹立を、第五条で新法典の編纂を、第六条で海軍拡張を、
第七条で帝都守衛の新軍隊編成を、第八条で世界共通の貨幣、物価の制度樹立を
述べたうえ、これを総括して、この他には日本の危機を打開する道はないと
言い切っている。
第一条は直接に土佐藩の進めた大政奉還への道であり、第二条は「五箇絛の御誓文」
からやがて起る民権運動を展望させるものであり、さらに、第三条以下は明治政府の
推進した開国和親と富国強兵策である。
近代日本は龍馬の胸に描かれた八策の示すように歩んだということができよう。
(この項は、横川末吉さん執筆)
※冗官(じょうかん)=むだな役人 また、不必要な官職
また、別の本では、どうなっているでしょうか。(赤字は、根木によるもの)
■日本の近代1:開国・維新(1853~1871)松本健一著 266pより
・「船中八策」を後藤象二郎へ
・・・。
(途中略)
龍馬はこの長崎から上京する船のなかで、新しい国家のグランド・デザインを語った。
それが、「船中八策」だった。これを筆録したのは、龍馬が後藤(=土佐藩)の援助の
もとに新しく発足させた海援隊の書記役、長岡謙吉である。
この「船中八策」には、横井小楠の『国是三論』の思想を引き継ぎつつも、それを
大政奉還によって維新国家へと完成させてゆく具体的綱領がすべて述べられていた。
・・・。
※本日紹介の二つの本は、いずれも「筆記者」、「筆録」となっており、長岡謙吉の
「関与度合い」が、低い表現となっている。
次回も、もう少し、他の本を紹介したい。
根木勢介 携帯:090-2825-2069
物部川こども祭(実行委員会)の活動紹介
2012年8月26日、第1回 物 部 川 こ ど も 祭 を、香美市香北町にあるアンパンマンミュージアム前広場で開催しました。途中、通り雨にも見舞われたりしながらも、予想外の良い天気に恵まれ、約3,500人の親子ずれで賑わいました。11か所ある駐車場も空きを待つ車が並ぶこともあったようでした。

2013年2月5日14時から17時、高知市市民活動サポートセンター大会議室にて、、第7回鏡川流域情報交流会で「ホタル条例」などの情報交換をしました。
(鏡川流域の関係の皆様へ、 2月5日(火)第7回鏡川流域情報交流会 開催のお知らせです)

1、2013年の流域での取り組み情報
① 第3回潮江こども祭&防災フェスティバル 4月7日(日)わんぱーくこうち芝生広場(わんぱーくこうち20周年記念事業・チューリップ祭とタイアップして実施)
② 鏡川早朝ウォーキング(毎月第2日曜 朝7時、みどりの広場集合で実施)
〇3月は、歩く途中で潮江天満宮によって、梅を観察し宮司さんのお話を聞く。
〇4月は、歩く途中で築屋敷の桜並木で、樹木医・野島幸一郎さんのお話を聞く。
③ ほたる祭・ほたる観察会
久礼野地区のとりくみを、橋詰辰男さんより・・・ 務めながら稲作をしている地元住民としての、気張らずちょっとだけホタルのためにもなっている草刈の話などをされました。この取り組みに参加者の皆さんが注目していました。
6月7日天気に恵まれ、第2回鏡川 ホタルの学校in 久礼野 観察交流会 開催しました
元鏡村長で市会議員の川村貞夫さんより、高知市鏡の「吉原ふれあいの里」でのほたるまつりの様子を話していただきました。今年は6月15日を予定とか。
6月9日、第4回 吉原ふれあいの里ほたるまつり(鏡地区)、楽しみました(その1)
6月9日、第4回 吉原ふれあいの里ほたるまつり(鏡地区)、楽しみました(その2)
6月9日、第4回 吉原ふれあいの里ほたるまつり(鏡地区)、楽しみました(その3)
鏡川ホタルネットワーク代表の大石さんから、高知小学校のホタルを育てるビオトープ作りに協力していることがはなされました。
④ 鏡川自然塾
石川妙子さんから、環境の杜こうち主催の「鏡川自然塾」について、人材養成の取り組みなどを話していただきました。
⑤ 第4回鏡川こども祭 9月29日(日)or 10月6日(日) 鏡川トリム公園
⑥ その他
高橋啓さんより、鏡川下流域 干潟での観察会や貝を育てる会の取り組み、水質検査の状況など、長年の取り組み経過で、鏡川の様子の変化を知ることが出来ました。
鏡川こども祭実行委員長の森田俊彦さんより、鏡川こども祭や森のようちえんについて、話がありました。アジロ山の森のようちえんの素晴らしい取り組みに学んで、神田での森の遊び場づくりを進めていることなど・・・
このほか鏡川沿いに、センダイヤザクラの並木をつくれないか・・・の話の件も出されました。
高知市が昨年実施(鏡川上流の吉原川)したエコツアー、応募者が殺到して大変好評だった。できれば今年も7月の最初の日曜日に実施したい…の話も。
朝倉堰で、天然アユの遡上が妨げられていた分野で、改修工事に伴い関係機関に働きかけて、魚道を確保できたことの話が発展して、
1月31日付けの高知新聞「県内魚道9割機能せず」の話題が盛り上がり、天然アユの遡上をはじめとした、多様な生物が生息する鏡川を、市民の手で推進することが話し合われました。
水が少ない時でも機能する魚道確保の取り組みを、近自然工法などの施策が展開されている鏡川から話題にしていくことが、確認されました。

2、「ホタル条例」をめぐる意見交換
条例改正への経過説明や、パブリックコメント(意見公募)、捕獲等の禁止の除外規定などについて、高知市環境保全課の担当者より説明をしていただきました。
交流会の事務局より、高知新聞の3つの記事のコピーも 配布され、参加した全員が様々な視点で意見が出され、出席された市会議員の皆様からも、大変勉強になりました・・・とのお話をいただきました。

3、「ホタル・シンポ」の開催提案
ホタル保護の実効を目的に、捕獲を原則禁止する「ホタル条例」化の動きが進んでいます。パブリックコメント(意見公募)でも多くの市民の声が寄せられ、ホタルを通した子ども達の環境教育や環境問題が盛り上がっています。
先進地の「北九州市下水道河川部水環境課ほたる係」などの紹介を参考にしながら、「ホタル条例」に端を発した今回の取り組みが、ホタル保護と共に河川の環境保全と川に親しむ取り組みや、環境問題の大きな前進の第一歩となることを目的として、開催することが確認されました。
(高知県メタンハイドレート開発研究会、鈴木朝夫理事長からの新年のご挨拶)
高知県メタンハイドレート開発研究会(理事長 鈴木朝夫)
明けましてお目出度うございます。昨年はどのような年でしたでしょうか。新しい年が皆様方にとって明るく実り多き年であることを、心からお祈り申し上げます。
ところで、皆様はどのような初夢をご覧になったでしょうか。土佐湾沖のメタンハイドレート掘削に成功し、高知新港が賑わい、香長平野が忙しくなるといった夢を画く人も居たかも知れません。私の初夢は? 私の感じた地球の未来は?
日本の将来は? 高知の先行きは? を述べてみます。
昨年の10月末に「計測展2012 OSAKA、計測と制御で創る未来の地球」がグランキューブ大阪で開かれました。特別講演講師に招かれたのです。講演題目は「新エネルギー資源の使い方、 メタンハイドレート、地熱発電、そしてストレージ」です。後半の内容を見出しで紹介すると、5) 日本は資源大国(黄金の国、ジパング)、6) スマート・グリッドとビッグデータ、7) 事故は必ず起きる、8) 右肩下がりの下山の先は、です。メタンハイドレートが採れても成長戦略を基本に置くべきではないが論点です。
暮れの12月29日(土)、9:00~10:00にNHK総合で放映された「エネルギーシフトの挑戦 省エネ最新技術”自然エネ宝庫の日本、エイモリー・ ロビンスからのメッセージ」を見ました。ドイツやデンマークを例に挙げながら、「気象条件に左右される様々な再生可能エネルギーは各種の先端 技術との組合せで生きてくること」が骨子となっています。収益性を保ちつつ、エネルギー効率を上げること、再生可能エネルギーに恵まれた資源 大国の日本であるとの自信を持つこと、膨大な数の分散型エネルギー供給源のスマートな結合が優れているとの意識改革が必要なこと、従来の官僚 的・独占的なエネルギー政策の慣習を捨てて、オープンなものとすること、日本には世界をより健康で、安全で、心豊かな方向へ引っ張っていける 原動力をもっていること、などが論旨です。
12月16日の衆議院議員選挙では、当然のことながら、全ての政党が様々な景気刺激策を提案し、プラスの経済成長率を約束する公約ばかりでした。また、主要各国の指導者の交代が行われましたが、そこでも新機軸は出てはいません。勿論、直近の政策と長期的視野の政策とでは対象が異なり、仕方ない ことかも知れません。昨年、情報プラットフォームに{右肩下がりの下山の先は}
(No.298,7,2012)で述べたような危機感は何処に も見当たりません。さらに{人間社会もメタボでなければ}(No.302,11,2012)で長期的な目標設定の困難さを示しました。
元旦の高知新聞の「ズバリ!経済予測ダービー」では、6人の専門家の直近の2013年の経済予測を述べています。為替相場、日経平均株価、経済成長率などの予測です。連年ハズレの専門家は藤巻健史氏です。「水の入ったコップはテーブルの端まで来ている」と警鐘を鳴らしています。昨年に続いて経 済成長率を前期比4%マイナスと予測しているのです。危機感を持っているのは藤巻氏だけです。我々に経済学の勉強が必要です。
「池上彰のやさしい経済学」が目に止まりました。京都造形芸術大学で行った14回分の特別講義を ”BSジャパン”で年末から年初に掛けて再放送したものです。財政政策と金融政策との関連の重要性を示唆していました。「ブラックマンデー」や「リーマ ン・ショック」の話も印象的でした。確率統計の知識が重要であることも教えてくれました。この内容は日本経済新聞社から出版されており、年明 けに上下2冊を買ってきました。皆で勉強するには絶好の教科書と感じましたし、会員の中には専門家も居るはずと思いました。
ロングテール、ジップの法則、パレートの法則など、「ベキ分布」に関わる確率の知識が必要です。ベキ分布の具体例を示せば、乾燥したビス ケットを床に落としたとき、壊れた破片の大きさの分布です。小さな破片(粉)は無数、非常に大きな欠片(かけら)も混ざっています。巨大地震 や巨大事故は確率は低くても必ず発生することを示しています。「アクシデント、事故と文明」はポール・ヴォリオの著書です。ここで彼は「文明 は事故を発明する」と述べているとのことです。低確率巨大地震・津波や原発事故は何故想定外なのかを知りたいものです。皆で勉強する必要があ ります。また、「予言の自己成就」、「合成の誤謬」など、心理学との関わりも大きいようです。調べる必要があります。また、温故知新の実践と して、歴史の勉強も必要です。
ここで昨年のご挨拶の繰り返し、今年のご挨拶につないで行きます。この会は、メタンハイドレートを中心に、他の海底資源にも関心を向けて、技術開発・基礎 研究、インフラ整備に対する、高知県、高知県企業、高知県民の熟度を上げていくことを目的として発足いたしました。県民全員で勉強していきま しょう。
今後の会の展開方向は幅広いテーマについて活動するとしました。メタンハイドレートに限定するのではなく、より広い範囲を包括出来るようにしていくことが得策と考えています。県民を挙げて理解を深めましょう。
講演会だけではなく、講習会、実習・見学など形式にとらわれない活動を広く勧めていきす。皆様のお知恵を発揮して下さい。情報の共有の仕組みの構築とし て、ネット交流とオフ会の組み合わせを考えましょう。預託を受けた基金の有効な活用を検討しましょう。
県内外を問わず、活動している他の団体との協働を積極的に進めましょう。
「国際戦略部会」、「技術開発部会」などの未設置の部会の立ち上げを早めるための 支援・協力を行っていきましょう。国家プロジェクトと連携を密にしていくことが必要です。
本会の名称も広く考え直したいと思って居ます。どのような名称が望ましいか知恵を下さい。今年が発展につながる年であることを祈念いたします。
私の初夢は「世の中の問題には、受験勉強やクイズ番組とは異なり、専門家でも正解は出せないことを知り、それぞれが好奇心を持って調べ、意見を出し合い、 条件による最適解を決めている。ドイツやデンマークのように。」であり、「日本では高知がその先頭を走っている。」といったものです。人類の 軟着陸の手段として「メタンハイドレート」や「地熱エネルギー」を使いたいものです。高知から世界中に情報発信がで来る体勢を創りたいもので す。今年も宜しくお願いいたします。
磁器上絵付けを、 楽しみませんか?

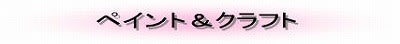
ペイント&クラフト
磁器上絵付けは、もともとは上絵付け絵の具(粉末)を専用オイルでといてペイントするものでしたが、近年いろいろな材料が出来て、筆を持つのが苦手な方でも気軽に絵付けすることが出来るようになりました。
その一つが、「転写紙」という絵の具をフィルム状にしたものです。
水にくぐらせて台紙との接着をゆるめて外し 磁器に貼り付けます。


転写紙には、絵がプリントされているものと 無地のものと、2種類あります。
無地のものは、ハサミで切って貼り付けるだけですので、小さなお子さんでも簡単に楽しく作ることが出来ます。切る形はお好み次第!どなたでもオリジナルでユニークな作品が出来ます。

また、最近では様々な形のクラフトパンチという型抜きが売られていますので、それを利用しても簡単でキレイな作品を作ることが出来ます。




ご連絡・お問い合わせ先、088-842-3821(川田)
情報てんこもり サイトマップ 「高知ファンクラブ1」(新設) 「高知ファンクラブ」 データーベース「高知ファンクラブ2」
磁器上絵付けを、 楽しみませんか?


磁器上絵付けとは・・・?
釉薬のかかった磁器に、絵付けをすることで、
・ ポーセリンペインティング(英語で磁器のこと)
・チャイナペイント(俗称 チャイナ(中国)=磁器)
・ポーセラーツ(商標) などで呼ばれています。
白磁やボーンチャイナなどの 食器や人形・インテリア用品等に、
専用の上絵具を用いて美しい花や愛らしい動物など様々なモチーフを描きます。
描き終えた作品は、専用の窯で 約800℃前後で焼成します。
すると、絵具が溶けて、磁器の表面と一体化しますので焼き上がった後は、
ご家庭で、食器としても使えるものになります(電子レンジ可)。

市場に出回っている絵のついた磁器は、そのほとんどがプリント貼り付けで作られていますが、世界中で愛用されている有名ブランドの食器、中でもマイセンやヘレンドの器は、華麗な色彩を高度な技術と労力を要し、専門のマイスター達がすべてを手描きで行うのですから高価なのは当然のことと言えます。

趣味としてのポーセリンアート
ホビーとしては、自分の好みの花や動物・想い出の風景、文字などのメッセージ等 自由なデザインのオリジナル作品が作れる点が人気です。
まずは、ご自分の身の回りのものやインテリアとしての飾り物、そしてご出産祝いや新築祝いなどのプレゼント・・・ etc。
世界に たった一つの「私の作品」を 創ってみませんか?



出産祝い 誕生祝い


マイカップ &マイプレート
ご連絡・お問い合わせ先、088-842-3821(川田)
情報てんこもり サイトマップ 「高知ファンクラブ1」(新設) 「高知ファンクラブ」 データーベース「高知ファンクラブ2」
根木勢介 さんの記事
根木さんの「鏡川ML」 その6 鏡川<変なオンちゃんの定義>
根木さんの「鏡川ML」 その5 鏡川・年収は、300万円と三人扶持切米五石
根木さんの「鏡川ML」 その4 鏡川:高知県って、どんなところ?
根木さんの「鏡川ML」 その3 <土佐人顔><鏡川河川工事>
根木さんの「鏡川ML」 その1 変なおんちゃん、が奇妙になつかしい。
坊さんが、かんざしを買ったお店、のこと
大人の・竹とんぼ教室(全3回)開催のお知らせ
堂々めぐり、から、銅像めぐり!
「クスノキと龍馬・・・明治維新を支えた木」・・・その1 はじめに
根木勢介さんの「龍馬十景」「龍馬の日常風景」 シリーズ
龍馬の日常風景・・・(一)軍鶏のいる風景
近江屋対談:龍馬&弥太郎 を開催します。
根木勢介さんの「龍馬十景」 ⑩ いのち・・・龍馬の手紙から
根木勢介さんの「龍馬十景」 ⑨ 長崎・・・頭の中の地図と樟脳
根木勢介さんの「龍馬十景」 ⑧ 京都・・・龍馬の五つの顔
根木勢介さんの「龍馬十景」 ⑦ 江戸・・・選択?洗濯の龍馬
根木勢介さんの「龍馬十景」 ⑥ 脱藩・・・龍馬の魅力
根木勢介さんの「龍馬十景」 ⑤ 鏡川・・・龍馬の原風景
根木勢介さんの「龍馬十景」 ④ 春夏秋冬・・・晋作と龍馬
根木勢介さんの「龍馬十景」 ③
根木勢介さんの「龍馬十景」 ②
根木勢介さんの「龍馬十景」 ①
根木勢介さんの「龍馬十景」 シリーズ
情報てんこもり サイトマップ 「高知ファンクラブ1」(新設) 「高知ファンクラブ」 データーベース「高知ファンクラブ2」
















