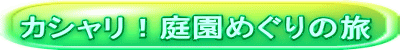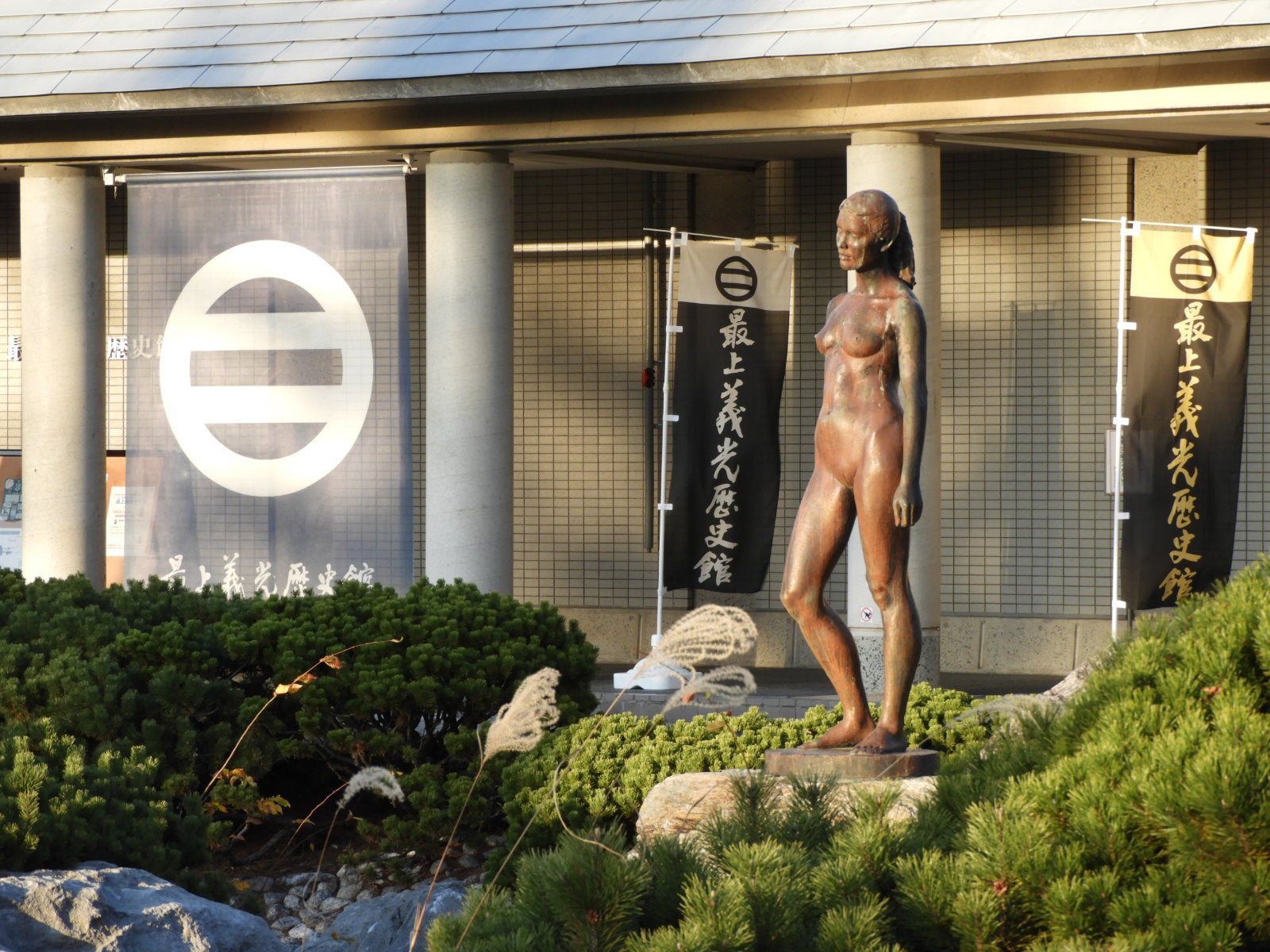■【あたりまえ経営のすすめ】2部管理編1章03 報連相を通じてノウハウを蓄積する

多様化の時代になり、ホンモノ智恵が求められる昨今です。
世の中には、「専門家」とか「プロ」と呼ばれる人が多数いらっしゃいます。
ところが、残念なことに、その大半というのが、「エセ専門家」「エセプロ」なのです。
管理職も、“真”のプロ管理職にならなければなりません。
ホンモノのプロ、要は「“真”のプロ」とは、どの様な人を指すのでしょうか。
エセプロの多くは、「あたり前のことが、あたり前にできる」ということを軽視しています。
「今の時代、最新の経営理論に基づく経営が重要である」と「あたり前」を蔑視をしている人もいるほどです。
では、「あたり前」とは、なんでしょうか?
「“真”のあたり前」を知らずして、あたり前を軽視して欲しくないですね。
あたり前は、その辺に転がっているのではなく、「あたり前は創るもの」です。
1970年代から、半世紀近くの経営コンサルタント経験から、最善の策ではないにしても、ベターな策を講じるための智恵をご紹介してまいります。
![]()
■ 2部 【管理編】 プロの管理職のあり方
本シリーズは、経営士・コンサルタントなどの経営専門業・士業の先生方を対象として、第1部の【経営編】をお送りしてきました。しかし、その内容は、視点を変えれば経営者・管理職のためのお話でもあります。ビジネス界においては、フレキシブルな視点の持ち方をできる人が高く評価されるのです。
筆者は、経営コンサルタントという仕事柄、しばしば管理職研修も実施してきました。その時に、必ずといって問うことは、「管理とは何でしょうか?」ということです。
管理職の皆さんは、よく勉強していて、私より立派な回答が返ってきます。
「では、それをどの様に実務に活かしていらっしゃいますか」と問いますと、期待するような回答が返ってきません。
難しいことを勉強しすぎているのではないでしょうか。知識と実務が乖離していますと、せっかくの知識が知恵として活かせません。
管理職として、「あたりまえ」なことが、実務で行われているのかどうか、謙虚に自分自身を見ることも大切なのではないでしょうか。
管理職は、「管理とは何か」「温かい管理」を正しく理解しなければ、部下からも、上司からも、社会からも正しく評価されません。
温かい管理とは
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/8b7833c2ebc019660a3813e9dedbf92f
ここでは、管理職なら誰もが知っているようなことを整理してみました。
知識としてはご存知のことでしょうが、それを実務に活かすにはどうしたらよいのかを考えてくださる契機となると幸いです。
■ 第2部1章 リーダーシップあるプロの管理職の発想と行動
“真”のプロは、“真”の管理ができなければなりません。“真”の管理は、「温かい管理」が基本です。
「管理」の基本について、考えてみましょう。
■2-03 報連相を通じてノウハウを蓄積する
別項で、双方向コミュニケーションにつきまして記述しています。
ここで、ご紹介します双方向コミュニケーションは、文書と口頭の両者を併用することが、一般的に言われていますやり方と異なるところです。
双方向コミュニケーションで交流されました情報を、文書と記録を残して行きますと、それが財産として残り、それを再活用することができます。
年度や月度の計画を立てるときに、行き詰まりますと、なかなか、その壁を突破することができません。その時に、ヒントとなりますのが、計画立案マニュアルです。
計画立案マニュアルは、はじめから大上段に構えて「マニュアルを作る」と考えなくても良いのです。繰り返される計画立案時におけます苦労や問題点などを、PDCAの一環として蓄積して行くことにより、自然と記録となり、それを整理しながら、マニュアルらしくして行けばよいのです。
日常業務も、業務報告書をベースに双方向コミュニケーション・報連相を行ったときに、業務報告書だけではなく、双方向コミュニケーションでの会話のポイントを報告書に吹きして行けばよいのです。
それらをもとに、整理しますと、ノウハウ集が、マニュアルとして成長して行きます。日常業務で、困ったことが起こったときに、そのマニュアルがヒントを与えてくれます。
日常業務は、PDCAに基づき、報告が成されます。文書で作成された報告書や関連する資料を目の前にして、双方向コミュニケーションを行い、双方向コミュニケーションで交わされた会話のポイントを、報告しに記録しておきます。それを整理することにより、マニュアルとして、いつでも、誰でもが会社のノウハウに接することができます。
その時に、管理職は、管理職の立場として、どのように部下の報告を聴き、どの様なアドバイスをしたら良いのかも、記録を整理すれば「管理職としての指導マニュアル」ができるのです。
文書としての記録が残っていませんと、個の経験が、その関係者だけの財産として偏重し、組織の財産となりません。
どの様なことが起こったときに、どの様な考え方をすればよいのか、どの様な取り組み方策があるのかなど、多くの示唆を得ることができるようになるでしょう。
「継続は力なり」という名言がありますが、私は、それをもじりまして「蓄積は力なり」と言っています。

【 注 】 詳細は、それぞれの当該する項をご参照ください。
<次号に続く>
■【あたりまえ経営のすすめ】 バックナンバー
あたり前の重要性を知る ←クリック
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理職編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>
■【プロの心構え】 バックナンバー
プロとして、いかに思考すべきか ←クリック