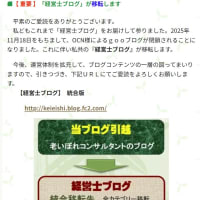■【連載小説】竹根好助の経営コンサルタント起業8章 6 資格試験の合格は難しい
■ 【小説】 竹根好助の経営コンサルタント起業
私は、経営コンサルタント業で生涯現役を貫こうと思って、半世紀ほどになります。しかし、近年は心身ともに思う様にならなくなり、創業以来、右腕として私を支えてくれた竹根好助(たけねよしすけ)に、後継者として会社を任せて数年になります。 竹根は、業務報告に毎日のように私を訪れてくれます。二人とも下戸ですので、酒を酌み交わしながらではありませんが、昔話に時間を忘れて陥ってしまいます。
これからコンサルタントを目指す人の参考になればと、私の友人が、書き下ろしで小説風に文章にしてくれています。 原稿ができた分を、原則として、毎週金曜日に皆様にお届けします。
*
【これまであらすじ】
竹根好助は、私の会社の後継者で、ベテランの経営コンサルタントでもあります。
その竹根が経営コンサルタントに転身する前、どのような状況で、どの様な心情で、なぜ経営コンサルタントとして再スタートを切ったのかというお話です。
*
1ドルが360円の時代、すなわち1970年のことでした。入社して、まだ1年半にも満たないときに、福田商事が、アメリカ駐在事務所を開設するという重大発表がありました。
角菊貿易事業部長の推薦する佐藤ではなく、初代駐在所長に竹根が選ばれました。それを面白く思わない人もいる中で、竹根はニューヨークに赴任します。慣れない市場、おぼつかないビジネス経験の竹根は、日常業務に加え、商社マンの業務の一つであるアテンドというなれない業務もあります。苦闘の連続の竹根には、次々と難問が押し寄せてくるのです。
その竹根が経営コンサルタントに転身する前、どのような状況で、どの様な心情で、なぜ経営コンサルタントとして再スタートを切ったのかというお話です。
*
1ドルが360円の時代、すなわち1970年のことでした。入社して、まだ1年半にも満たないときに、福田商事が、アメリカ駐在事務所を開設するという重大発表がありました。
角菊貿易事業部長の推薦する佐藤ではなく、初代駐在所長に竹根が選ばれました。それを面白く思わない人もいる中で、竹根はニューヨークに赴任します。慣れない市場、おぼつかないビジネス経験の竹根は、日常業務に加え、商社マンの業務の一つであるアテンドというなれない業務もあります。苦闘の連続の竹根には、次々と難問が押し寄せてくるのです。
日常業務をこなしながら、アテンドという商社マンにつきものの業務を自分なりに見つめ直す竹根です。慣れないニューヨークを中心としたアメリカでのビジネスですが、時として折れそうになってしまいます。そのようなときに、若い竹根の支えとなってくれたのが、本社で竹根をフォローしてくれるかほりでした。彼女の父親は地元の名士ということから、竹根などに娘をやるわけにはいかないと厳しかったのです。かほりと竹根の努力で、結局、父親は折れざるをえず、晴れて結婚が認められました。
たった一人でニューヨークで苦闘してきた、若者、竹根好助(たけねよしすけ)も5年の任期を終え、東京に戻り、本社勤務に戻りました。5年という歳月で自分の置かれている立場が急激に変化してきたことを実感している竹根です。その最大の変化が、まさか自分の身に降りかかると思ってもみなかったヘッドハンティングです。
*
◆8章 半歩の踏み込み
*
◆8章 半歩の踏み込み
ニューヨークでの5年の任期を終え、東京に戻り、商社マンとして中堅どころに足を踏み入れた竹根です。東京本社勤務が始まったばかりというのに、ヘッドハンティングという、想定だにしなかった話が舞い込みました。
一方で、竹根の仕事ぶりは、常人とはかけ離れた発想での仕事ぶりでした。
*
※ 直前号をお読みくださるとストーリーが続きます。
直前号 ←クリック
*
◆8-6 資格試験の合格は難しい
中小企業診断士受験向けの参考書は書店に並んでいるが、こちらの資格の受験参考書はほとんど市販されていない。竹根は中小企業診断士向けの参考書を斜め読みして、基礎知識の整理をすることはしたが、むしろ経営者向けのノウハウ本を片っ端から読むようにした。日常の身近なことから学び初めて、次第にその道の奥義にまで到達するという意味を持つ「下学(かがく)上達(じょうたつ)」を地でいく竹根であった。アメリカで培った速読術がここでは大いに役に立つことになった。
二次試験は、記述式の問題で、限られた時間にその設問に対する回答をするのは、まとめる力と構成力や文章力とともに、早く書けることが重要である。竹根は、ニューヨークで連日何十ページというレポートを本社に送っていたし、それに加えて毎夜かほり宛に手紙を書いてきたので、文章を早く書くことには自信があった。
第三次試験は、企業診断実習とそれに基づく勧告書の提出である。実際に企業に行き、ヒアリングを通じたり、決算書などの財務資料などを分析したりして勧告書を書くのである。それも、試験会場で作成するのではなく、昼間は会社で仕事をして、そのあとのプライベートな時間に作成するのである。この点でも、竹根はかほりと福田商事の商社とメーカー問題や、海外営業部企画課の仕事をやってきたので、その延長線上のような感覚で取り組めた。気持ちの上では、非常に楽であったために、のびのびとした発想ができた。
十月に第三次試験の発表があった。合格率は、二十分の一、すなわち五%である。幸い、竹根は、受検者すべての中の二番目の成績で合格ができた。順位まで発表されるという厳しさである。一位は、私立の名門大学のマーケティングの教授であった。竹根は、原町田というその教授に負けたことが悔しかった。原町田教授は、多数の著書もある、有名な先生であることは竹根も知っている。しかし、自分も曲がりなりにもアメリカの大学院でマーケティングを専攻してきたのである。相手が大学の教授であっても、その人に負けたことは、竹根にとっては大きな屈辱であった。
<続く>
*
◆8-6 資格試験の合格は難しい
中小企業診断士受験向けの参考書は書店に並んでいるが、こちらの資格の受験参考書はほとんど市販されていない。竹根は中小企業診断士向けの参考書を斜め読みして、基礎知識の整理をすることはしたが、むしろ経営者向けのノウハウ本を片っ端から読むようにした。日常の身近なことから学び初めて、次第にその道の奥義にまで到達するという意味を持つ「下学(かがく)上達(じょうたつ)」を地でいく竹根であった。アメリカで培った速読術がここでは大いに役に立つことになった。
二次試験は、記述式の問題で、限られた時間にその設問に対する回答をするのは、まとめる力と構成力や文章力とともに、早く書けることが重要である。竹根は、ニューヨークで連日何十ページというレポートを本社に送っていたし、それに加えて毎夜かほり宛に手紙を書いてきたので、文章を早く書くことには自信があった。
第三次試験は、企業診断実習とそれに基づく勧告書の提出である。実際に企業に行き、ヒアリングを通じたり、決算書などの財務資料などを分析したりして勧告書を書くのである。それも、試験会場で作成するのではなく、昼間は会社で仕事をして、そのあとのプライベートな時間に作成するのである。この点でも、竹根はかほりと福田商事の商社とメーカー問題や、海外営業部企画課の仕事をやってきたので、その延長線上のような感覚で取り組めた。気持ちの上では、非常に楽であったために、のびのびとした発想ができた。
十月に第三次試験の発表があった。合格率は、二十分の一、すなわち五%である。幸い、竹根は、受検者すべての中の二番目の成績で合格ができた。順位まで発表されるという厳しさである。一位は、私立の名門大学のマーケティングの教授であった。竹根は、原町田というその教授に負けたことが悔しかった。原町田教授は、多数の著書もある、有名な先生であることは竹根も知っている。しかし、自分も曲がりなりにもアメリカの大学院でマーケティングを専攻してきたのである。相手が大学の教授であっても、その人に負けたことは、竹根にとっては大きな屈辱であった。
<続く>
■ バックナンバー