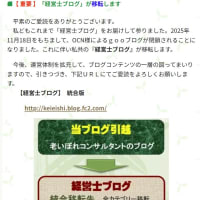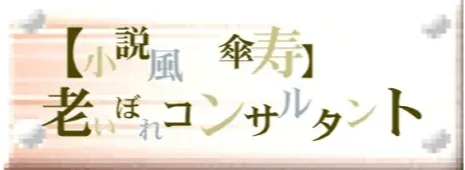
■【老いぼれコンサルタントのひとり言】 7月15日 ◆退職代行サービス ◇お彼岸のお中日に説法を聴く ◇徒然草とマズローの欲求5段階説
「老いぼれていては困ります」
お叱りのような、励ましのような言葉を、後身のコンサルタント・士業からいただきます。
生来、「お節介焼き精神」の塊のような生き方をしてきて「コンサルタントのためのコンサルタント」などと持ち上げられて、その気になって、日暮パソコンに向かひて、よしなしごとをつぶやいています。
お耳汚しのことを、今日もまた、つぶやいています。
■【けふのつぶやき】
◆ 退職代行サービス
マスコミが、退職代行サービスについて取り上げることが多くなっています。売り手市場である現在、たいして重大ではない理由で転職をすることがあるのではないでしょうか。
パワハラなど、深刻な状況に陥っている人が利用するということはあり得るかも知れません。
しかし、軽度な不調ならば、会社に相談すれば、治療しながら就業を継続することもできるでしょう。それが難しくても休職という選択肢もあります。石の上にも三年という言葉もあります。
労働の流動性が高い昨今であっても、短期間で転職を繰り返していれば弊害もあるはずです。もし、私が就職担当者であれば、そのような人は、自分の会社でもすぐ辞めるのではないかと心配になり、採用を控えるでしょう。
代行サービスなどを使わなくても、法的には退職できます。業者にお金を払ってまで会社と絶縁するという手段は、社会人としてもいかがなものでしょうか。
一方、視点を変えて、弁護士以外が行う退職代行サービスという代行業務は、たとえ労働組合が行う場合であっても、弁護士法に違反するのではないでしょうか。

■【評判の良いブログ】
最近、アップロードしたブログで、とりわけ人気度の高いブログをご紹介します。

■【経営コンサルタントの独り言】
半世紀にわたる経営コンサルティング経験を思い出しながら、あるいは、直近に起こったことなどを元に、随筆風に記述しています。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
◆ お彼岸のお中日に説法を聴く 715
本日は、お彼岸のお中日です。
檀那寺(だんなでら:信徒が属す寺)である臨済宗建長寺派の某寺で説法を聴いてきました。
京都府舞鶴市松尾にある西国第二十九番札所青葉山松尾寺(まつのおでら)の「人生往来手形」の話を聴いてきました。
人間は、縁(えにし)あってこの世に生を受けた、「この世の間借り人」であるといいます。
間借り人ですので、好き勝手に生きて良いわけではありません。
三度の食べ物に文句をいわないで
美味(おいしい)と誉め
人と気まずいことがあっても
我が身の至らぬせいと思い
愚痴なく、
怒らず
むさぼらず
そして、最後は「ほどよく、この世に暇乞いして、元のあの世に帰る」とのことでした。
人間は、死ぬと気になって幸せな人生であったかどうかが解ると言われています。
周囲の人に迷惑を掛けない、良い死に際でありたいものです。
*
■ お中元と盂蘭盆会、宗教というのは複雑ですね
7月15日は、お盆の「お中日」です。この日は、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」でもあります。
先祖を、偲びあう仏教の重要な行事です。【Wikipedia】によりますと「父母や祖霊を供養したり、亡き人を偲び仏法に遇う縁とする行事」とあります。
この時期には「お中元」の贈答を行う人が多いでしょう。
このお中元ですが、仏教の関連かと思いきや・・・
*
7月13日に盆入りで、迎え火を焚いてご先祖様の霊をお迎えしましたが、7月16日は、そのご先祖様をお送りするために送り火が焚かれます。
京都の大文字焼きは送り火のひとつとしての行事です。
迎え火は、ご先祖の霊が、キチンと自分達のところに帰って来て下さるように、その目印として焚きます。
送り火は、ご先祖様が帰ってきて下さったことへの感謝の気持ちを持ち、見送るということを表しています。
送り火は、夕方に同じ場所で、焙烙にオガラを折って積み重ねて燃やします。
お墓で迎えたり送ったりするのが正式といわれています。
お迎えの時には提灯に明かりを灯して、霊を家まで導いて帰ります。
近年は、マンションなどでは火をたけませんので、盆提灯を迎え火や送り火の代わりと見なせるそうです。
(ドアノブ)
*
◆徒然草とマズローの欲求5段階説
第38段3 名利に使われて 名誉や利欲を求めることは?
*
【原文】 名利に使われて
智恵と心とこそ、世にすぐれたる誉も残さまほしきを、つらつら思へば、誉を愛するは、人の聞きをよろこぶなり、誉むる人、毀る人、共に世に止まらず。
伝へ聞かん人、またまたすみやかに去るべし。誰をか恥ぢ、誰にか知られん事を願はん。
誉はまた毀りの本なり。
身の後の名、残りて、さらに益なし。これを願ふも、次に愚かなり。
*
【用語】
心: 人格、品性
誉(ほまれ): 名誉 ←→ そしり:非難
人の聞き: 評判
身の後: 死後
*
【要旨】 名利に使われて
知恵と心というものは、世間で優れた名誉として見られ、それを残したいというのは人情です。しかし、よくよく考えてみますと、「名誉を愛する」ということは、人の評判を喜んでいるに過ぎません。誉める人も、非難する人も、両者共に、この世に長く生きているわけではなく、
また、その評判を伝え聞く側の人も、すぐにこの世を去ってしまうのです。
だれに対して恥じることも必要なく、まただれに知られることを願う必要もないのです。
名誉はまた非難のもとでもあります。
死後に名声が残っても何のメリットもないのです。こういう名誉を頗うこともまた、一番好ましくないと考える「高位高官を望む」ということに次いて、愚かなことです。
*
【 コメント 】 名利に使われて
この段を読んでいて、マズローの欲求5段階説を思い浮かべました。
五段階の最高位は、「承認の欲求」といいますか、人から認められることが、人間の欲求の中で最終的なものであるとマーケティングの時間に学び、また、その通りであると思ってきました。
兼好は言います。
評価される方も、する方も、長い時の流れからしますと、一瞬のことですので、だれに対して恥じる必要がありましょうか。だれかに良く思われ、それを知られるということを好ましいと思い、それを願う必要があるのでしょうか。
「人の噂も七十五日」
人生もまた短いのですから、名誉名声を求めても、悠久の時間の流れからすると塵にもならないというのです。
そう言われますと、確かにそうなのですが、やはり煩悩から離れることができない自分が、この世に存在しているのです。その矛盾を楽しむことが、人生を楽しむことに繋がると自分を納得させている、自分があります。「いと恥ずかし」

■【老いぼれコンサルタントのひとり言】 バックナンバー
http://keieishi.blog.fc2.com/blog-category-75.html

■【ご案内】
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
私どものブログは、下記のような複数のブログ・プラットフォームよりお届けしています。
経営士ブログ(経営管理・コンサルティング等)
http://ameblo.jp/keieishi-kyokai/
経営士ブログ別冊(旅行・写真・映像・趣味等)
経営士ブログ総合版(上記2ブログを包含)
大変勝手ながら、上記の中より、ご都合のよろしいブログをご覧下さるよう、お願い申し上げます。
© copyrighit N. Imai All rights reserved