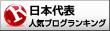その日は、メンバーでいらっしゃる著名なジャーナリストの牛木素吉郎先生も参加されていた。牛木先生のことは、日本で何らかのサッカー関連に携わっておられれば、知らない人がいないだろうと思う、ジャーナリストの大御所のお一人だ。
現在も「ビバ!サッカー研究会」や「日本サッカー史研究会」といった勉強の場を作られ、旺盛な活動を続けておられる。まだ、ご存じない方はぜひyahooのキーワード検索で「ビバ!サッカー研究会」や「日本サッカー史研究会」と打ち込んでいただき、ご覧いただきたい。
私も「サロン2002」でご一緒するまでは面識がなかったが、サッカー専門誌をはじめ、さまざまな場で執筆活動をされていたので、お名前は存じ上げていた。
その牛木先生が「サロン2002」に参加された感想をコメントの形でメンバー宛てのメールシステムに寄せてくださった。
それを読ませていただいたら、「映像記録の収集保全と公開について」という項目を起こしてくださり、私が紹介した取り組みについてコメントしてくださった。
それによると、まずもって、私の取り組みに驚かれたとのこと。
そして日本サッカー協会でも小倉純二会長当時、90周年記念事業として映像収集を指示された経緯があり、その後どうなっているだろうか?と感じていらっしゃるという。
最後に、集めた映像を公開の場で観覧するときに、著作権、映像権などの問題をどう処理するのだろうか? と指摘してくださった。
なんと光栄なことか。牛木先生ほどの著名なジャーナリストの方に関心を示していただいただけで、お話した甲斐があったというものだ。
先生がご指摘のとおり、公開に際しての、著作権、映像権などの問題は、現時点では、何も手つかずの状態だ。いまはまだ、映像資料をデジタル変換してデータベースにすることで精一杯なのと、なんといっても前例のないことなので。
ただ、スポーツ文化、とりわけサッカー文化の成熟度をあげていくにも、いずれは、前例のないことだからこそ、手続き的に制度化して、法的処理ができるようにしたいと思っている。
皆さんのお知恵もお借りしながら前進させたいと思う。
ちなみに牛木先生は、昨年8月下旬、テレビ東京の番組「FOOT×BRAIN」で2週にわたり、今回FIFAバロンドール会長賞を受賞された賀川浩先生と対談企画に出演されている。ご紹介しておきたい。