
読書愛あふれる小説。
本を読んで本を読みたくなる本だ。ためらいがちな成長物語はやっぱり、いいな。
中学で学校に行けなくなった一橋沙羅は、通信制の高校で幼馴染みの近藤万葉に出会う。
万葉は家庭の事情で叔父と共に暮らすようになり、叔父の古書店でバイトをしている。
読書家の万葉に誘われていくように、沙羅も読書の世界に入っていく。沙羅と万葉がそれぞれに出会った人、
出合った本を通して少しずつ新たな世界に歩きだす。その世界が開かれていく様子を描いた小説。
本を読むことが持つ自由さ(解放区)の獲得と、読書という、ある意味閉鎖空間から、現実世界のただ中に
歩きだしていく姿が、大切な時間を慈しむように描かれている。
小学校の教科書に載っていて、小学生が案外悩む(教えている大人のほうが悩むのかも)、
というのも解答を求めたがるから悩んでしまう宮沢賢治の小説「やまなし」の「クラムボン」についての感想や、
「ごんぎつね」のごんの気持をめぐる会話。
万葉が、叔父の過去にからむ柳川をめぐるときに、重なっていく福永武彦の小説「廃市」。
むしろ「廃市」をベースに作りだされた物語は福永の小説へのオマージュのようにも感じられる。
そういえば、「廃市」は1年ぐらい前に読書会で採り上げて、大林宣彦の映画も観て、ああ、いいなと
思ったなこととかも思い出した。夏目漱石の『三四郎』についての話もさりげなく出てくる。
違う本を読んで語り合うのも楽しいけれど、同じ本を読んでそれぞれ思ったことを話す、その違いが楽しい。共感がうれしい。
それって、豊かな感じだなと思った。
読書することで現実自体もなんだか、きっと厚みのようなものが出てくるのではないかとも思えた。
とか、別に効果などではなくて、素朴にただただ、本を読んでいる時間は、いい。
個性は本の選び方じゃなく、読んだ感想に出る。
同じ本を読んでも、読んだ人の数だけ感想があるだろう。
確かに。そんなあたりまえを語りあったりできるのはすがしい時間だと思う。
遠藤周作の『砂の城』を読んでみたくなった。










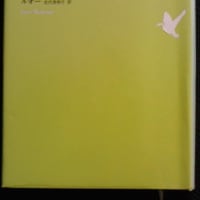
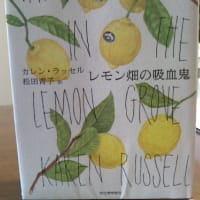
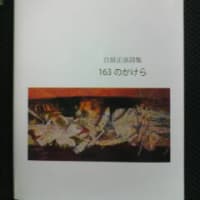
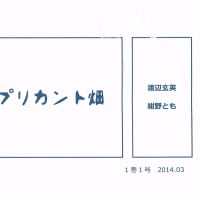
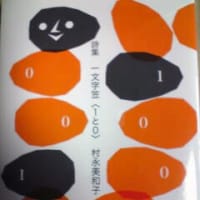
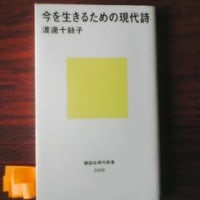









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます