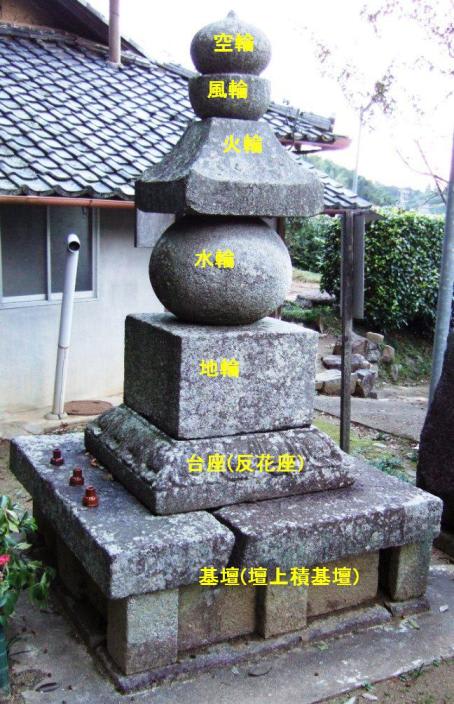各部の名称などについて(その2)
次に格狭間(こうざま)について、石造物に限らず、木造の建造物や金属工芸品、特に仏堂などの須弥壇などによく見られます。 川勝博士によると「曲線の集合より成る装飾彫刻で、原則として物の台座に付けられる」とされ、起源についての確実な説はないようですが「台座の束の両側に付けられた持送りの上部が伸びて連絡し、二つの持送りによって包まれた形が格狭間を生み出したと考えるのが自然」とされています。古くは法隆寺の玉虫の厨子や正倉院の器物などの下端に見られるようなものが祖形だと考えられています。石造物というよりは工芸品類の台脚の補強材ようなものが発展した意匠と小生も理解しています。ちなみに奈良国立博物館の正倉院展目録の用語解説では「机の脚部や器物の床脚等では、しばしば脚を固定するための持送りという材がつけられるが、この持送りには牙状の突起が刳られることが多い。この突起付きの持ち送りが作る間を格狭間と
川勝博士によると「曲線の集合より成る装飾彫刻で、原則として物の台座に付けられる」とされ、起源についての確実な説はないようですが「台座の束の両側に付けられた持送りの上部が伸びて連絡し、二つの持送りによって包まれた形が格狭間を生み出したと考えるのが自然」とされています。古くは法隆寺の玉虫の厨子や正倉院の器物などの下端に見られるようなものが祖形だと考えられています。石造物というよりは工芸品類の台脚の補強材ようなものが発展した意匠と小生も理解しています。ちなみに奈良国立博物館の正倉院展目録の用語解説では「机の脚部や器物の床脚等では、しばしば脚を固定するための持送りという材がつけられるが、この持送りには牙状の突起が刳られることが多い。この突起付きの持ち送りが作る間を格狭間と 称する。」とあります。石造ではありませんが有名な中尊寺金色堂の内陣須弥壇の側面を見ると、壇上積み基壇と同じ形になって、羽目には豪壮な格狭間があって、格狭間の内側には孔雀のレリーフがあしらわれています。格狭間に囲まれた部分は本来は空洞であるべきですが、羽目板によって塞がれ、すでに台の脚とその補強材という意味合いは失われ、一種の装飾になっています。石造美術にみる格狭間も同様に、側面の装飾としての意匠と考えることができると思われます。恐らく木造建造物や工芸品の装飾からヒントを得て石造物にも導入された意匠表現ではないかと思います。基礎側面だけに限らず、台座の側面や露盤の
称する。」とあります。石造ではありませんが有名な中尊寺金色堂の内陣須弥壇の側面を見ると、壇上積み基壇と同じ形になって、羽目には豪壮な格狭間があって、格狭間の内側には孔雀のレリーフがあしらわれています。格狭間に囲まれた部分は本来は空洞であるべきですが、羽目板によって塞がれ、すでに台の脚とその補強材という意味合いは失われ、一種の装飾になっています。石造美術にみる格狭間も同様に、側面の装飾としての意匠と考えることができると思われます。恐らく木造建造物や工芸品の装飾からヒントを得て石造物にも導入された意匠表現ではないかと思います。基礎側面だけに限らず、台座の側面や露盤の 側面などさまざまな場所に大小にかかわらずしばしば見られます。格狭間の形状を見ると、上部は花頭曲線と呼ぶ曲線(=弧)と「牙状の突起」つまり茨(=カプス)と呼ばれるとんがった部分が組み合わさり左右の側線がカーブしながら脚部につながっています。古い格狭間は、曲線にたわんだようなところがなく、茨のとんがりがあまり顕著でないものが多く、側線がスムーズで角
側面などさまざまな場所に大小にかかわらずしばしば見られます。格狭間の形状を見ると、上部は花頭曲線と呼ぶ曲線(=弧)と「牙状の突起」つまり茨(=カプス)と呼ばれるとんがった部分が組み合わさり左右の側線がカーブしながら脚部につながっています。古い格狭間は、曲線にたわんだようなところがなく、茨のとんがりがあまり顕著でないものが多く、側線がスムーズで角 張ったりふくらみ過ぎるところがなく上部の花頭曲線の中央が広くまっすぐ水平に伸びて肩が下がらないものが古く、新しくなるにつれてこうした部分がくずれていく傾向があります。(あくまで傾向で絶対ではありません。)戦国時代頃には子どもが描いたチューリップのような「模様」になってしまいます。さらに、格狭間の内側は彫り沈め、しかも微妙に膨らみをもたせ丁寧に仕上げるものが本格的で、次第に彫りが平板になっていき最後は線刻になってしまいます。大雑把にいうと脚と持ち送りという祖形に近いものが古く、それをきちんと踏まえた装飾であったものが次第に元の意味が忘れられ、単なる模様になっていくと考えると理解しやすいかもしれません。(続く)
張ったりふくらみ過ぎるところがなく上部の花頭曲線の中央が広くまっすぐ水平に伸びて肩が下がらないものが古く、新しくなるにつれてこうした部分がくずれていく傾向があります。(あくまで傾向で絶対ではありません。)戦国時代頃には子どもが描いたチューリップのような「模様」になってしまいます。さらに、格狭間の内側は彫り沈め、しかも微妙に膨らみをもたせ丁寧に仕上げるものが本格的で、次第に彫りが平板になっていき最後は線刻になってしまいます。大雑把にいうと脚と持ち送りという祖形に近いものが古く、それをきちんと踏まえた装飾であったものが次第に元の意味が忘れられ、単なる模様になっていくと考えると理解しやすいかもしれません。(続く)
写真左上:14世紀後半の例、写真右上:滋賀県蒲生郡日野町比都佐神社宝篋印塔に見られる14世紀初頭の美しい格狭間。さすがに中尊寺金色堂の優美な孔雀には比ぶべくもありませんがここにも格狭間内に孔雀のレリーフがあります。三茎蓮花や開敷蓮花に代表される近江式装飾文様にあって、まさに真打といったところでしょうか。いいです、ハイ。ちなみに比都佐神社に近い伝蒲生貞秀塔の基礎下に組み込まれてしまった宝塔と思しき基礎の孔雀文はさらに一層の優れモノです、ハイ。一方くずれてきた格狭間、写真左下:15世紀後半、写真右下:15世紀中頃、ブロッコリーみたいな変な「模様」になって元の意味がわかってないんじゃないですかといいたくなります。子どもが釘か何かででカリカリ削って落書きしたチューリップじゃないの!といいたくなるようなもっとひどいのもあります。