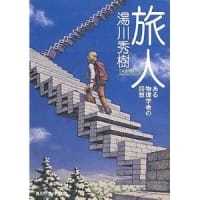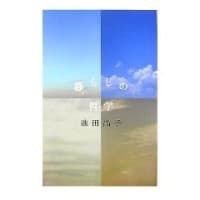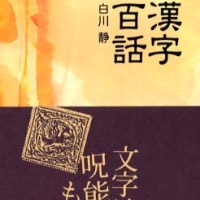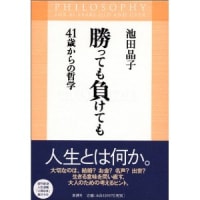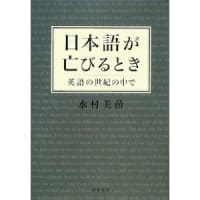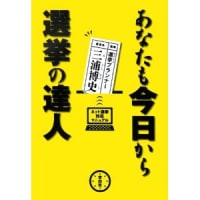3月10日、石巻市立大川小学校の児童の家族が仙台地方裁判所に提起せざるを得なかった裁判は、東日本大震災という出来事そのものだと思います。この誠実な論理こそが、あの日の大震災というものなのだと、改めて慄然とさせられます。この論点の中心を射抜く現実の直視に比すれば、「絆」「前進」「未来」「笑顔」などは明らかな論点ずらしであり、現実逃避の論理であると感じます。また、「復興」ですらも、震災そのものを正視する論理ではないと思います。
周囲からどんなに「過去は変えられない」「未来は変えられる」と言われたところで、人の人生の形式というものは、「どうしてもこの問題に向き合って苦しまなければ人生が成立しない」という論理であらざるを得ないと思います。片が付かないかも知れないことを前提として、そのことに抗い続けなければ心の区切りをつけられるか否かすらもわからず、そのわからないことに集中しなければ前に進めるか進めないかもわからない、このような限界的な論理です。
裁判を起こすより他に方法がなくなったという震災そのもの論点の前には、「未来」「前進」など生温い気休めですし、何をすっきり終わらせようと急かしているのか、論点ずらし以上のものではないと感じます。また、終わらせたいのではなく始まってしまった人生の形式にとっては、「復興が進む」「笑顔が戻る」という価値の押し付けは暴力的だと思います。誰に何を言われようが、他人ではなく自分の人生であり、世間的価値で誤魔化せる話ではないからです。
このような訴訟に対しては、「不満の矛先をどこかにぶつけたいのはわかるが、学校を悪者にするのは筋違いである」との意見を多く耳にします。これは、当事者ではない人間の感想として自然でしょうし、私も心のどこかでそう思っています。この心情は、筋が通らない気持ち悪さから逃れたい無意識だと思いますが、なぜ天災によって人間同士が争うのか、それが紛れもない現実であり、この裁判こそが震災そのものであると、自戒を込めて確認したいと思います。