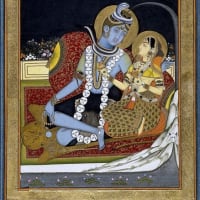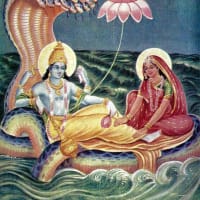※金子武蔵(カネコタケゾウ)『ヘーゲルの精神現象学』ちくま学芸文庫(1996)(Cf. 初刊1973)
Ⅱ本論(三)「理性」1「観察」(その7)(174-176頁)
(37)-3 「有機体」における「外は内の表現である」という命題:(ハ) 「感受性」と「反応性」と「再生」の三者(※「機能」)と、「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)との関係!
★以上、《 (ロ)「感受性」と「反応性」と「再生」との関係》が本来の意味における「内なるもの」の内容だが、そこへ《 (ハ) 「感受性」と「反応性」と「再生」の三者(「機能」)と、「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)との関係》の問題がからまってくる。(174頁)
★「内なるもの」とは「機能」(「感受性」と「反応性」と「再生」)であり、「外なるもの」とは「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)だ。(174頁)
☆すなわち「外なるもの」とは、感受性に対する「神経組織」、反応性に対する「筋組織」、再生(繁殖)に対する「内臓組織」だ。(174頁)
☆「内なるもの」とは「機能」であり、「外なるもの」とは「組織」であるわけで、この点からすると、「『外なるもの』は『内なるもの』の表現である」というのは、「『組織』が『機能』を表現している」ことにほかならない。(174頁)
(37)-3-2 「内なるもの」の3つの契機(「感受性と反応性と再生」)の関係:「再生」が「内なるもの」で、この「内なるもの」の「表現」として、「感受性」と「反応性」が「外なるもの」だ!
★さらにヘーゲルは「『外なるもの』は『内なるもの』の表現である」という法則は、「内なるもの」すなわち「機能」(「感受性」と「反応性」と「再生」)の相互の間にも成り立つと考える。(174-175頁)
☆つまり「機能」である《「感受性」と「反応性」と「再生」》との3つの間にも、相互に他を表現する関係が成り立つという。(175頁)
☆ヘーゲルは、「再生」の能力が基礎だという。「再生」が「内なるもの」で、この「内なるもの」の「表現」として、「感受性」と「反応性」が「外なるもの」だとする。Cf. 「『外なるもの』は『内なるもの』の表現である」!(176頁)
☆この考え方は生物学者キールマイヤー(K. F. Kielmeyer)(1765-1844)が1793年に主張し、それがシェリング(1775-1854)等に受け入れられ、ヘーゲル(1770-1831)に影響した。(175頁)
☆キールマイヤーによれば①動物が「下等」になれば「再生」能力(「繁殖」力)は増加するが、「感受性」はにぶく(Ex. 「触覚」だけしかない動物もある )、その種類も少なくなる。「有機体」が「低級」になるにしたがい、「感受性」はにぶく、また種類は少なくなる。①-2人間のように動物が「高等」になれば、「感受性」は非常に高度化する。すなわち「視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚」の能力、さらに「記憶や構想」の能力も生じる。(175頁)
逆に②「繁殖」力(「再生」能力)が多いほど、「反応性」の種類も少なく、また「感受性」の能力も鋭敏でなく種類も少なくなる。
しかし③(「反応性」の)「種類」に関してでなく「持続性」に関しては、「反応性」は「感受性」の増加(動物が「高等」であること)に反比例し、したがって「再生」の増加(※動物が「下等」・「低級」であること)に正比例する。(175頁)
☆キールマイヤー&ヘーゲルの議論は、判りにくいが、事柄は別にむずかしくない。「個体」を、また「種族」を維持し「再生」するには、食物などを外界から摂取しなくてはならないから、刺激を「感受」する能力(「感受性」)、また感受に応じて「反応」する能力(「反応性」)が必要であるのは当然だ。(175-176頁)
☆「心理的能力」(※「記憶や構想」の能力、広義の「感受」・「反応」の能力)は、「生理的能力」の上にさらに「心像(イメージ)」をもつことから生まれてくる。しかしそのときにも、今日のサイコアナリスィス(精神分析)が性欲を重視するように、やはり「再生」の能力が基礎になる。(金子武蔵)(176頁)
★ヘーゲルの(イ)(ロ)(ハ)の議論をまとめよう。「有機体」においては、(A)「感受性と反応性と再生」という「内なるもの」が、「神経組織と筋組織と内臓組織」という「外なるもの」との関係に立ち、「外なるものは内なるものの表現である」。(B)「内なるもの」の3つの契機(「感受性と反応性と再生」)が相互に「内」と「外」として他を表現しうる。「再生」が「内なるもの」で、この「内なるもの」の「表現」として、「感受性」と「反応性」が「外なるもの」だ。(176頁)
《参考》「基本法則」は「『外なるもの』は『内なるもの』の『表現』である」ということだ。(161頁)
☆これには、次のような場合がある。(161頁)
(イ)「有機体」と「環境」との関係
(ロ)「感受性」と「反応性」と「再生」との関係
(ハ) 「感受性」と「反応性」と「再生」の三者(※「機能」)と、「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)との関係
(ニ)「比重」(※質量)と「凝集力」との関係
(ホ)「論理学的心理学的法則」(※「論理学的法則」と「心理学的法則」)
(ヘ)「人相術」
(ト)「骨相術」
(注)なお(イ)から(ト)まで、順序はヘーゲル『精神現象学』のテキストのままだが、表現は必ずしもそのままでない。(161頁)
Ⅱ本論(三)「理性」1「観察」(その7)(174-176頁)
(37)-3 「有機体」における「外は内の表現である」という命題:(ハ) 「感受性」と「反応性」と「再生」の三者(※「機能」)と、「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)との関係!
★以上、《 (ロ)「感受性」と「反応性」と「再生」との関係》が本来の意味における「内なるもの」の内容だが、そこへ《 (ハ) 「感受性」と「反応性」と「再生」の三者(「機能」)と、「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)との関係》の問題がからまってくる。(174頁)
★「内なるもの」とは「機能」(「感受性」と「反応性」と「再生」)であり、「外なるもの」とは「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)だ。(174頁)
☆すなわち「外なるもの」とは、感受性に対する「神経組織」、反応性に対する「筋組織」、再生(繁殖)に対する「内臓組織」だ。(174頁)
☆「内なるもの」とは「機能」であり、「外なるもの」とは「組織」であるわけで、この点からすると、「『外なるもの』は『内なるもの』の表現である」というのは、「『組織』が『機能』を表現している」ことにほかならない。(174頁)
(37)-3-2 「内なるもの」の3つの契機(「感受性と反応性と再生」)の関係:「再生」が「内なるもの」で、この「内なるもの」の「表現」として、「感受性」と「反応性」が「外なるもの」だ!
★さらにヘーゲルは「『外なるもの』は『内なるもの』の表現である」という法則は、「内なるもの」すなわち「機能」(「感受性」と「反応性」と「再生」)の相互の間にも成り立つと考える。(174-175頁)
☆つまり「機能」である《「感受性」と「反応性」と「再生」》との3つの間にも、相互に他を表現する関係が成り立つという。(175頁)
☆ヘーゲルは、「再生」の能力が基礎だという。「再生」が「内なるもの」で、この「内なるもの」の「表現」として、「感受性」と「反応性」が「外なるもの」だとする。Cf. 「『外なるもの』は『内なるもの』の表現である」!(176頁)
☆この考え方は生物学者キールマイヤー(K. F. Kielmeyer)(1765-1844)が1793年に主張し、それがシェリング(1775-1854)等に受け入れられ、ヘーゲル(1770-1831)に影響した。(175頁)
☆キールマイヤーによれば①動物が「下等」になれば「再生」能力(「繁殖」力)は増加するが、「感受性」はにぶく(Ex. 「触覚」だけしかない動物もある )、その種類も少なくなる。「有機体」が「低級」になるにしたがい、「感受性」はにぶく、また種類は少なくなる。①-2人間のように動物が「高等」になれば、「感受性」は非常に高度化する。すなわち「視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚」の能力、さらに「記憶や構想」の能力も生じる。(175頁)
逆に②「繁殖」力(「再生」能力)が多いほど、「反応性」の種類も少なく、また「感受性」の能力も鋭敏でなく種類も少なくなる。
しかし③(「反応性」の)「種類」に関してでなく「持続性」に関しては、「反応性」は「感受性」の増加(動物が「高等」であること)に反比例し、したがって「再生」の増加(※動物が「下等」・「低級」であること)に正比例する。(175頁)
☆キールマイヤー&ヘーゲルの議論は、判りにくいが、事柄は別にむずかしくない。「個体」を、また「種族」を維持し「再生」するには、食物などを外界から摂取しなくてはならないから、刺激を「感受」する能力(「感受性」)、また感受に応じて「反応」する能力(「反応性」)が必要であるのは当然だ。(175-176頁)
☆「心理的能力」(※「記憶や構想」の能力、広義の「感受」・「反応」の能力)は、「生理的能力」の上にさらに「心像(イメージ)」をもつことから生まれてくる。しかしそのときにも、今日のサイコアナリスィス(精神分析)が性欲を重視するように、やはり「再生」の能力が基礎になる。(金子武蔵)(176頁)
★ヘーゲルの(イ)(ロ)(ハ)の議論をまとめよう。「有機体」においては、(A)「感受性と反応性と再生」という「内なるもの」が、「神経組織と筋組織と内臓組織」という「外なるもの」との関係に立ち、「外なるものは内なるものの表現である」。(B)「内なるもの」の3つの契機(「感受性と反応性と再生」)が相互に「内」と「外」として他を表現しうる。「再生」が「内なるもの」で、この「内なるもの」の「表現」として、「感受性」と「反応性」が「外なるもの」だ。(176頁)
《参考》「基本法則」は「『外なるもの』は『内なるもの』の『表現』である」ということだ。(161頁)
☆これには、次のような場合がある。(161頁)
(イ)「有機体」と「環境」との関係
(ロ)「感受性」と「反応性」と「再生」との関係
(ハ) 「感受性」と「反応性」と「再生」の三者(※「機能」)と、「組織」(「神経組織」と「筋組織」と「内臓組織」)との関係
(ニ)「比重」(※質量)と「凝集力」との関係
(ホ)「論理学的心理学的法則」(※「論理学的法則」と「心理学的法則」)
(ヘ)「人相術」
(ト)「骨相術」
(注)なお(イ)から(ト)まで、順序はヘーゲル『精神現象学』のテキストのままだが、表現は必ずしもそのままでない。(161頁)