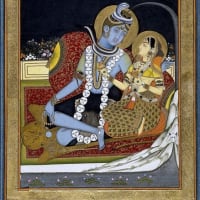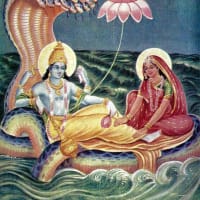※金子武蔵(カネコタケゾウ)『ヘーゲルの精神現象学』ちくま学芸文庫(1996)(Cf. 初刊1973)
Ⅱ本論(三)「理性」1「観察」(その7-2)(176-178頁)
(37)-4 「有機体」における「外は内の表現である」という命題:(ハ)-2 「生命」は「機能」の面から「感受」・「反応」・「再生」の3つに分けるがこれらは「三一的統一」をなすべきものだ!「観察的理性」はバラバラに分離し、それらの間に「数量的な関係」を「法則」としてたてようとする!
★《 (イ)「有機体」と「環境」との関係》、《 (ロ)「感受性」と「反応性」と「再生」との関係》、《 (ハ) 「感受性」・「反応性」・「再生」の3「機能」と、「組織」(「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」)との関係》との議論が済んだが、ここでヘーゲルは「法則」を定立しようとする「観察的理性」の立場に対して次のような批判をくだす。(176頁)
☆「生命」は「機能」の面から「感受」・「反応」・「再生」の3つに分けることができるが、しかしヘーゲルによれば、これらは「三でありながら一」であるから、それら3つはバラバラに分離できない性質のものである。(176頁)
☆ところがここで「理性」は、「観察」の立場いいかえれば「対象意識」の立場をとっているから、これらの3つをバラバラに切り離してしまい、「内面的関係」はなく「外面的な皮相な関係」しか残らないとヘーゲルは言う。かくておのずと「数量的関係」が求められ「法則」が定立される。しかしヘーゲルによれば、本当を言えばこれらの3つ(「感受」・「反応」・「再生」)は「三一的統一」をなすべきものである。(176頁)
★また「機能」(「感受」・「反応」・「再生」)に対する「組織」の側面においても、「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」というように「組織」をもちろん区別できるが、これら3つも相互に浸透し合っているから、「神経組織」は「感受性」だけを、「筋組織」は「反応性」だけを、「内臓組織」は「再生」能力だけをつかさどることはないとヘーゲルは言う。(176-177頁)
★しかるに「理性」(「観察的理性」)は、「感受」・「反応」・「再生」を、また「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」を、バラバラに分離するから、それらの間に「数量的な関係」を「法則」としてたてようとする。そういう意味で「観察的理性」の見方が間違っていることを、ヘーゲルはしきりに批判する。この批判に当ったところのあるのは明らかだ。(177頁)
☆例えば、「眼」は、(ア)視覚の器官(「感受」)であるに違いないが、(イ)「再生」能力がなくては眼も「見る」(「感受」)ことはできないし、また(ウ)眼で「見る」(「感受」)からこそ、手で働きかける(「反応」)こともできる。(エ)働きかける(「反応」)ことから切り離して「見る」(「感受」)こともない。(177頁)
☆確かに「内」(「機能」:「感受」・「反応」・「再生」)と「外」(「組織」:「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」)、いずれの面からいっても、「生命」が「三一的統一」を形づくるのは事実だ。(金子武蔵)(177頁)
(37)-4-2 ヘーゲルはあまりにも「論理化」しすぎる!マルクスの『精神現象学』批判!「純粋な論理的関係」と同じような「完全な統一」は、「有機的自然」(「有機体」)においてはありえない!それぞれの「器官」or「組織」が、それぞれ別個の「機能」をつかさどることは、これを認めなくてはならない!
★「純粋な論理的関係」においては、「個別」は「普遍」なくしてなく、「普遍」は「個別」なくしてないから、「個別」の否定は「普遍性」の否定であることが、「完全な統一」である。(177頁)
☆しかし「有機的自然」であるかぎり、「純粋な論理的関係」の場合と同じようには、「完全な統一」をもたない。やはりいろんな「器官」(「組織」)や「機能」には区別がある。例えば①「胃」は「消化」(「再生」)の機能をつかさどる「器官」(「組織」)であって、殴るというような「反応」の機能を営むことはできない。②殴るというような「反応」の機能を営むには、手という「器官」(「組織」)が必要だ。(177頁)
☆ただ③「胃」という「器官」(「組織」)の「消化」(「再生」)能力がいちじるしく減退して、「からだ」また「手」という「器官」(「組織」)を動かす(「反応」)ことができなくなったというようなときにのみ、ヘーゲルの考えていること、すなわち「有機的自然」(「有機体」)における「内」(「機能」:「感受」・「反応」・「再生」)と「外」(「組織」:「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」)の「完全な統一」が成立する。(177頁)
☆かくてそれぞれの「器官」あるいは「組織」が、それぞれ別個の「機能」をつかさどることは、これを認めなくてはならない。(177-178頁)
☆ヘーゲルはあまりにも「論理化」しすぎる。マルクスの『精神現象学』批判も、要するに、あまりにも「論理化」しすぎるということにある。これは当たっていると思う。(金子武蔵氏)(178頁)
(37)-4-3 ヘーゲルは「主観の方だけが見方を変える」のでなく、「『対象』の方も変わる」と言うが、これは、我々を悩ますところだ!
★さて(ア)「観察的理性」の「対象固定的見方」がいけないのか?(イ)「対象」もやはり「個別と普遍との相互浸透」というようなものになってしまわなければならないのか(ヘーゲルの考え)?どちらが正しいのかという疑問がある。(178頁)
☆しかし「対象」には、やっぱり「認識対象も変わる」(ヘーゲルの考え)とは言いきれないところ、いいかえれば「観察的理性の見方にも正しいものがある」ことを証明するような性質があるのではないか。(金子武蔵氏)(178頁)
☆「変わっていく」のは「見方」だけであって「対象」ではなく、「見方」が変わるに応じて、それに都合のいいような「対象」にだんだん移って行くだけである。(金子武蔵氏)(178頁)
★ところがヘーゲルは「主観の方だけが見方を変える」のでなく、「『対象』の方も変わる」と言う。(178頁)
☆これは、我々を悩ますところだ。(金子武蔵氏)(178頁)
☆先述したように(Cf. 169-172頁)、「クリスト教的前提、即ち神が世界を造ったということ」があれば、「『対象』の方も変わる」ということも確かにある程度まで納得できる。(金子武蔵氏)(178頁)
☆だがこの前提を離れると理解は不可解だ。ここに「ヘーゲル哲学」の制限があることは明らかだ。(金子武蔵氏)(178頁)
《参考1》「精神」が「ある段階から次の段階に移った」ときに、「認識主観の方だけがその見方を変える」のか、それとも「認識対象も変わる」のか?「物」も、我々の「精神」とか「自己」とかと格別異なったものではない?ヘーゲルにおける「クリスト教的前提」:「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」!(169-172頁)
☆じつはここに重要な問題が介在する。それは一般的にいうと、「精神」が「ある段階から次の段階に移った」ときに、(あ)「認識主観の方だけがその見方を変える」のか、それとも(い)「認識対象も変わる」のかという問題だ。(169頁)
☆たとえば(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移っていくときのことを考えてみよう。(A)「対象意識」の段階が「事物」の認識を、(B)「自己意識」の段階が「相互承認」という形で「人格と人格との関係」を問題にしている。(169頁)(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(あ)「主観の方だけが見方を変える」にすぎないとすれば、それは「事物」の認識をやめて、「人間のことだけ」を問題にするということだから、この場合には問題はない。(169頁)
☆だが(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(い)「対象自身もその姿をかえる」とすると、すなわち「一見、『物』のように見えても、本当の姿においては『物』も我々の『精神』とか『自己』とかと格別異なったものではない」というように「対象も正体を変える」とすると、非常に困難な問題が起って来る。(169-170頁)
☆実際ヘーゲルでは、(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(あ)「主観の方だけが見方を変える」にすぎないとするのか、(い)「対象自身もその姿をかえる」とするのか、曖昧だ。(あ)「意識の方だけ変わる」と言っている時もあるし、(い)「対象の方まで変わる」と言っている時もある。(170頁)
☆だが結局は(い)「対象の方も変わる」というのが、ヘーゲルの意見と思われる。(金子武蔵)(170頁)
《参考2》(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(い)「対象自身もその姿をかえる」(※「一見、『物』のように見えても、本当の姿においては『物』も我々の『精神』とか『自己』とかと格別異なったものではない」というように「対象も正体を変える」)とすると、「このコップが自分と同じものだ」と考えることになる。しかしこれは、到底困難だ。(金子武蔵)(170頁)
☆だが「ヘーゲル哲学の根底にクリスト教がひそんでいる」ことを想起すべきだ。(170頁)
☆もしこの前提を容れるとすると、ヘーゲルは以下のように考えていたと思われる。「(a)神はこの世を造った。(b)この世におけるすべては神を映現している。むろん(c)人間は神の肖像(似姿)として精神的である。だが(d)人間以外のものもすべて神の御手によって成ったものだから神の叡知をなにかの形において示したものだ」。(170頁)
☆かくて「『コップ』の正体もやっぱり『精神的なもの』だ」ということになる。(170頁)
☆非常に困難だが、「クリスト教的前提」を認めたとすれば、つまり(「神」による)「始点と終点」を認めたとすれば、「そういうこと」(Ex.「コップ」も「精神的なもの」だ)も成立しえないわけでもない。(170頁)
☆むろん「外物」(「事物」)と比べれば、「人間」の方が「神の似姿」として造られたものとして、より「精神的」であり、これに対し「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」ことになる。とにかく「クリスト教的前提」を容れれば理解は何とかつく。(170頁)
《参考3》ヘーゲルの「クリスト教的前提」からすれば、「対象意識を自己意識に帰一させる」ことも考えられないわけではない!(171頁)
☆『精神現象学』の全体を通じて、根本的なのは(A)「対象意識」と(B)「自己意識」の区別だが、「対象意識」が「事物」を相手とする意識であるのに対し、「自己意識」は「他人」を相手にする意識だ。(171頁)
☆これら2つ(「対象意識」と「自己意識」)は、一応は区別されるが、現実には互いにからまる。例えば(「自己意識」における)「親と子の関係」といっても、「精神的な人格的な関係」だけではなく、「同じ家で毎日寝起きして一緒に食事をしている」とかいうように「事物との関係」(※「対象意識」)も入ってくる。「事物との関係」を抜きにして「人格的関係」もない。(171頁)
☆かくて宗教的な境地(すなわち「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」との「クリスト教的前提」)からすれば、「対象意識を自己意識に帰一させる」ことも考えられないわけではない。(171頁)
☆「クリスト教的前提」に立ったとして、大体、ここいらまでがギリギリのところではないかと思う。(金子武蔵)(171頁)
☆かくて「キリスト教的前提」を切り離してしまうと、「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」とのヘーゲルの見解は、非常に困難なことになる。(171頁)
☆しかしヘーゲルを含めすべての哲学者に時代的な制限がある。(171頁)
☆人間の尊厳をあれほどまでに自覚し、自由な立派な考えをもっていたプラトンとかアリストテレスでさえ、奴隷制を認め、奴隷をもって人間の道具だとしている。このような時代的な制限があるからといって、プラトン哲学が全体として無意味になるわけでない。(171頁)
☆これと同じようにヘーゲルにも「欠陥」(※「キリスト教的前提」)はある。しかし同時に、いろんな考え方に関して、特に「ある立場から他の立場への転換」に関して『精神現象学』が我々を指導する力をもっていることはこれを認めなくてはならない。(171頁)
☆これはヘーゲルにかぎらないことで、いかなる哲学者の場合でも、「非常に時代的かぎられた点」と「時代を越えた普遍的な面」と両方がある。(171-172頁)
Ⅱ本論(三)「理性」1「観察」(その7-2)(176-178頁)
(37)-4 「有機体」における「外は内の表現である」という命題:(ハ)-2 「生命」は「機能」の面から「感受」・「反応」・「再生」の3つに分けるがこれらは「三一的統一」をなすべきものだ!「観察的理性」はバラバラに分離し、それらの間に「数量的な関係」を「法則」としてたてようとする!
★《 (イ)「有機体」と「環境」との関係》、《 (ロ)「感受性」と「反応性」と「再生」との関係》、《 (ハ) 「感受性」・「反応性」・「再生」の3「機能」と、「組織」(「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」)との関係》との議論が済んだが、ここでヘーゲルは「法則」を定立しようとする「観察的理性」の立場に対して次のような批判をくだす。(176頁)
☆「生命」は「機能」の面から「感受」・「反応」・「再生」の3つに分けることができるが、しかしヘーゲルによれば、これらは「三でありながら一」であるから、それら3つはバラバラに分離できない性質のものである。(176頁)
☆ところがここで「理性」は、「観察」の立場いいかえれば「対象意識」の立場をとっているから、これらの3つをバラバラに切り離してしまい、「内面的関係」はなく「外面的な皮相な関係」しか残らないとヘーゲルは言う。かくておのずと「数量的関係」が求められ「法則」が定立される。しかしヘーゲルによれば、本当を言えばこれらの3つ(「感受」・「反応」・「再生」)は「三一的統一」をなすべきものである。(176頁)
★また「機能」(「感受」・「反応」・「再生」)に対する「組織」の側面においても、「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」というように「組織」をもちろん区別できるが、これら3つも相互に浸透し合っているから、「神経組織」は「感受性」だけを、「筋組織」は「反応性」だけを、「内臓組織」は「再生」能力だけをつかさどることはないとヘーゲルは言う。(176-177頁)
★しかるに「理性」(「観察的理性」)は、「感受」・「反応」・「再生」を、また「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」を、バラバラに分離するから、それらの間に「数量的な関係」を「法則」としてたてようとする。そういう意味で「観察的理性」の見方が間違っていることを、ヘーゲルはしきりに批判する。この批判に当ったところのあるのは明らかだ。(177頁)
☆例えば、「眼」は、(ア)視覚の器官(「感受」)であるに違いないが、(イ)「再生」能力がなくては眼も「見る」(「感受」)ことはできないし、また(ウ)眼で「見る」(「感受」)からこそ、手で働きかける(「反応」)こともできる。(エ)働きかける(「反応」)ことから切り離して「見る」(「感受」)こともない。(177頁)
☆確かに「内」(「機能」:「感受」・「反応」・「再生」)と「外」(「組織」:「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」)、いずれの面からいっても、「生命」が「三一的統一」を形づくるのは事実だ。(金子武蔵)(177頁)
(37)-4-2 ヘーゲルはあまりにも「論理化」しすぎる!マルクスの『精神現象学』批判!「純粋な論理的関係」と同じような「完全な統一」は、「有機的自然」(「有機体」)においてはありえない!それぞれの「器官」or「組織」が、それぞれ別個の「機能」をつかさどることは、これを認めなくてはならない!
★「純粋な論理的関係」においては、「個別」は「普遍」なくしてなく、「普遍」は「個別」なくしてないから、「個別」の否定は「普遍性」の否定であることが、「完全な統一」である。(177頁)
☆しかし「有機的自然」であるかぎり、「純粋な論理的関係」の場合と同じようには、「完全な統一」をもたない。やはりいろんな「器官」(「組織」)や「機能」には区別がある。例えば①「胃」は「消化」(「再生」)の機能をつかさどる「器官」(「組織」)であって、殴るというような「反応」の機能を営むことはできない。②殴るというような「反応」の機能を営むには、手という「器官」(「組織」)が必要だ。(177頁)
☆ただ③「胃」という「器官」(「組織」)の「消化」(「再生」)能力がいちじるしく減退して、「からだ」また「手」という「器官」(「組織」)を動かす(「反応」)ことができなくなったというようなときにのみ、ヘーゲルの考えていること、すなわち「有機的自然」(「有機体」)における「内」(「機能」:「感受」・「反応」・「再生」)と「外」(「組織」:「神経組織」・「筋組織」・「内臓組織」)の「完全な統一」が成立する。(177頁)
☆かくてそれぞれの「器官」あるいは「組織」が、それぞれ別個の「機能」をつかさどることは、これを認めなくてはならない。(177-178頁)
☆ヘーゲルはあまりにも「論理化」しすぎる。マルクスの『精神現象学』批判も、要するに、あまりにも「論理化」しすぎるということにある。これは当たっていると思う。(金子武蔵氏)(178頁)
(37)-4-3 ヘーゲルは「主観の方だけが見方を変える」のでなく、「『対象』の方も変わる」と言うが、これは、我々を悩ますところだ!
★さて(ア)「観察的理性」の「対象固定的見方」がいけないのか?(イ)「対象」もやはり「個別と普遍との相互浸透」というようなものになってしまわなければならないのか(ヘーゲルの考え)?どちらが正しいのかという疑問がある。(178頁)
☆しかし「対象」には、やっぱり「認識対象も変わる」(ヘーゲルの考え)とは言いきれないところ、いいかえれば「観察的理性の見方にも正しいものがある」ことを証明するような性質があるのではないか。(金子武蔵氏)(178頁)
☆「変わっていく」のは「見方」だけであって「対象」ではなく、「見方」が変わるに応じて、それに都合のいいような「対象」にだんだん移って行くだけである。(金子武蔵氏)(178頁)
★ところがヘーゲルは「主観の方だけが見方を変える」のでなく、「『対象』の方も変わる」と言う。(178頁)
☆これは、我々を悩ますところだ。(金子武蔵氏)(178頁)
☆先述したように(Cf. 169-172頁)、「クリスト教的前提、即ち神が世界を造ったということ」があれば、「『対象』の方も変わる」ということも確かにある程度まで納得できる。(金子武蔵氏)(178頁)
☆だがこの前提を離れると理解は不可解だ。ここに「ヘーゲル哲学」の制限があることは明らかだ。(金子武蔵氏)(178頁)
《参考1》「精神」が「ある段階から次の段階に移った」ときに、「認識主観の方だけがその見方を変える」のか、それとも「認識対象も変わる」のか?「物」も、我々の「精神」とか「自己」とかと格別異なったものではない?ヘーゲルにおける「クリスト教的前提」:「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」!(169-172頁)
☆じつはここに重要な問題が介在する。それは一般的にいうと、「精神」が「ある段階から次の段階に移った」ときに、(あ)「認識主観の方だけがその見方を変える」のか、それとも(い)「認識対象も変わる」のかという問題だ。(169頁)
☆たとえば(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移っていくときのことを考えてみよう。(A)「対象意識」の段階が「事物」の認識を、(B)「自己意識」の段階が「相互承認」という形で「人格と人格との関係」を問題にしている。(169頁)(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(あ)「主観の方だけが見方を変える」にすぎないとすれば、それは「事物」の認識をやめて、「人間のことだけ」を問題にするということだから、この場合には問題はない。(169頁)
☆だが(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(い)「対象自身もその姿をかえる」とすると、すなわち「一見、『物』のように見えても、本当の姿においては『物』も我々の『精神』とか『自己』とかと格別異なったものではない」というように「対象も正体を変える」とすると、非常に困難な問題が起って来る。(169-170頁)
☆実際ヘーゲルでは、(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(あ)「主観の方だけが見方を変える」にすぎないとするのか、(い)「対象自身もその姿をかえる」とするのか、曖昧だ。(あ)「意識の方だけ変わる」と言っている時もあるし、(い)「対象の方まで変わる」と言っている時もある。(170頁)
☆だが結局は(い)「対象の方も変わる」というのが、ヘーゲルの意見と思われる。(金子武蔵)(170頁)
《参考2》(A)「対象意識」から(B)「自己意識」に移ったとき、(い)「対象自身もその姿をかえる」(※「一見、『物』のように見えても、本当の姿においては『物』も我々の『精神』とか『自己』とかと格別異なったものではない」というように「対象も正体を変える」)とすると、「このコップが自分と同じものだ」と考えることになる。しかしこれは、到底困難だ。(金子武蔵)(170頁)
☆だが「ヘーゲル哲学の根底にクリスト教がひそんでいる」ことを想起すべきだ。(170頁)
☆もしこの前提を容れるとすると、ヘーゲルは以下のように考えていたと思われる。「(a)神はこの世を造った。(b)この世におけるすべては神を映現している。むろん(c)人間は神の肖像(似姿)として精神的である。だが(d)人間以外のものもすべて神の御手によって成ったものだから神の叡知をなにかの形において示したものだ」。(170頁)
☆かくて「『コップ』の正体もやっぱり『精神的なもの』だ」ということになる。(170頁)
☆非常に困難だが、「クリスト教的前提」を認めたとすれば、つまり(「神」による)「始点と終点」を認めたとすれば、「そういうこと」(Ex.「コップ」も「精神的なもの」だ)も成立しえないわけでもない。(170頁)
☆むろん「外物」(「事物」)と比べれば、「人間」の方が「神の似姿」として造られたものとして、より「精神的」であり、これに対し「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」ことになる。とにかく「クリスト教的前提」を容れれば理解は何とかつく。(170頁)
《参考3》ヘーゲルの「クリスト教的前提」からすれば、「対象意識を自己意識に帰一させる」ことも考えられないわけではない!(171頁)
☆『精神現象学』の全体を通じて、根本的なのは(A)「対象意識」と(B)「自己意識」の区別だが、「対象意識」が「事物」を相手とする意識であるのに対し、「自己意識」は「他人」を相手にする意識だ。(171頁)
☆これら2つ(「対象意識」と「自己意識」)は、一応は区別されるが、現実には互いにからまる。例えば(「自己意識」における)「親と子の関係」といっても、「精神的な人格的な関係」だけではなく、「同じ家で毎日寝起きして一緒に食事をしている」とかいうように「事物との関係」(※「対象意識」)も入ってくる。「事物との関係」を抜きにして「人格的関係」もない。(171頁)
☆かくて宗教的な境地(すなわち「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」との「クリスト教的前提」)からすれば、「対象意識を自己意識に帰一させる」ことも考えられないわけではない。(171頁)
☆「クリスト教的前提」に立ったとして、大体、ここいらまでがギリギリのところではないかと思う。(金子武蔵)(171頁)
☆かくて「キリスト教的前提」を切り離してしまうと、「事物」は「不完全ではあるにしても、しかしやはり『神によって造られたもの』として『精神的なもの』をもっている」とのヘーゲルの見解は、非常に困難なことになる。(171頁)
☆しかしヘーゲルを含めすべての哲学者に時代的な制限がある。(171頁)
☆人間の尊厳をあれほどまでに自覚し、自由な立派な考えをもっていたプラトンとかアリストテレスでさえ、奴隷制を認め、奴隷をもって人間の道具だとしている。このような時代的な制限があるからといって、プラトン哲学が全体として無意味になるわけでない。(171頁)
☆これと同じようにヘーゲルにも「欠陥」(※「キリスト教的前提」)はある。しかし同時に、いろんな考え方に関して、特に「ある立場から他の立場への転換」に関して『精神現象学』が我々を指導する力をもっていることはこれを認めなくてはならない。(171頁)
☆これはヘーゲルにかぎらないことで、いかなる哲学者の場合でも、「非常に時代的かぎられた点」と「時代を越えた普遍的な面」と両方がある。(171-172頁)